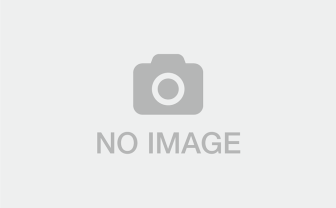概要
基本的にアナログで遊ぶカードゲームのみを指すことが多く、『Hearthstone』『Shadowverse』といったPCやスマートフォンアプリで遊ぶカードゲームについては、システムに交換という概念がなくとも、デジタル・トレーディングカードゲーム(デジタルTCG、またはDCGと略される)と区別されて呼ばれることが多い
英語圏ではコレクタブルカードゲーム(略称:CCG)とも呼ばれる。
歴史
世界初のトレーディングカードゲーム『Magic: The Gathering』の誕生
世界初のトレーディングカードゲームとして知られているのは、アメリカの数学者リチャード・ガーフィールドがデザインした『Magic: The Gathering』である。
ウィザーズ・オブ・ザ・コースト社から1993年8月に発売され、その競技性の高さから高額な賞金がかけられた大会が定期的に開催されている。
日本でも、『ポケモンカードゲーム』や『遊戯王OCG デュエルモンスターズ』などからトレーディングカードゲームの文化が広がり、子どもから大人までプレイされて続け、様々なシリーズかリリースされている。
1990年代の拡大
MTGの成功に続き、日本を中心に多くのTCGが登場した。特に、1996年に発売された「ポケモンカードゲーム」や「遊戯王オフィシャルカードゲーム」は、子供から大人まで幅広い層に人気を博し、TCG市場を拡大させた。
また、この時期には「デュエル・マスターズ」や「ヴァンガード」といった新しいタイトルも次々と登場した。
既存の有名IPとの組み合わせによって様々なTCGが開発され、グッズとしての側面も持つようになる。
2000年代以降
2000年代に入ると、TCGはデジタル化の波にも乗り、オンラインでプレイできるバージョン(DCG)が登場した。
特に「ハースストーン(Hearthstone)」や「シャドウバース(Shadowverse)」などのデジタルTCGは、物理的なカードを必要としない新しいプレイスタイルを提供し、さらに多くのプレイヤーを引きつけている。
ゲームプレイ
TCGの基本的な流れは、カードを引く、カードをプレイする、相手と対戦する、のサイクルで進行する。各ゲームには独自のルールがあり、戦略やデッキ構築の自由度が高いのが特徴となる。
デッキ構築
プレイヤーは通常、ゲームのルールに従って自分のデッキ(カードの束)を構築する。デッキには特定の枚数のカードが含まれ、戦略に応じてカードを選択する。デッキ構築の自由度が高く、プレイヤーの個性が反映される。また、大型大会などで優勝したデッキはコピーされることも多い(コピーデッキ)
対戦
対戦は通常1対1で行われますが、マジック:ザ・ギャザリングの統率者戦のように複数人でプレイできる形式も存在する。プレイヤーは順番にカードをプレイし、相手のライフポイントやリソースを削ることを目指す。対戦の流れや勝利条件はゲームごとに異なる。
コレクションと取引、トレード
TCGの特徴の一つとして、カードの収集と交換がある。カードには1枚ごとにレアリティが設定されており、特にレアなカードは高価値となり、セカンダリーマーケットで取引される。プレイヤーはトレードや購入を通じてコレクションを充実させる。
一方で、昨今のトレーディングカードゲームのショップはトラブル防止や売上減少の観点からトレードを禁止している店舗も多く、国内では頻繁なトレードが行われなくなって久しい。
日本国内の主なトレーディングカードゲーム
ヴァイスシュヴァルツ
ポケモンカードゲーム
遊☆戯☆王オフィシャルカードゲーム
WIXOSS
ワンピースカードゲーム
国外発の主なカードゲーム
似たようなキーフレーズ
同じカテゴリーのキーフレーズ