「楽しいから始まる学び」をコンセプトに、Webメディア、YouTube、テレビなど多岐にわたるプラットフォームで活躍する知的エンタメ集団・QuizKnock。
クイズをテーマにしたWebメディアとして出発したQuizKnockは、2026年10月2日に活動10周年を迎える。
「QuizKnock10周年プロジェクト」のキービジュアル
Web上での情報発信/収集のメインストリームが、テキストから動画へと移り変わりつつある現代。生成AIの台頭により、社会のファスト化がさらに加速するのと並行して、偽・誤情報の氾濫もより深刻になっている。
こういった情報環境の変化を、この10年間インターネット上で“知”の発信を続けてきたQuizKnockは、どのように捉えているのか。
「QuizKnock10周年プロジェクト」の記者発表会で、伊沢拓司さん、ふくらPさん、河村拓哉さん、須貝駿貴さん、山本祥彰さん、鶴崎修功さん、東問さん、東言さんら、QuizKnockの動画出演メンバーたちに話を聞いた。
取材・編集:都築陵佑 文・写真:タナカハルカ
目次
Webメディア・QuizKnockが実現した、動画ではできない体験
──QuizKnockは「身の回りのモノ・コトをクイズで理解する」をコンセプトとしたWebメディアとしてスタートしました。あれから9年、情報発信の中心はテキストから動画へと移り変わりつつあります。この現状をどのように見ていますか?
伊沢拓司 俺らがQuizKnockを立ち上げた9年前は、Webメディアブームだったというか。先輩方がいっぱいいらっしゃったんですけど。
鶴崎修功 そうでしたね。「わかりませんでした。いかがでしたか」みたいな、いわゆるキュレーションサイト的な記事がたくさん出ていた時期でしたね(※)。
※2016年、DeNAが運営する「WELQ」「MERY」をはじめとしたキュレーションサイトで、不確かな情報の掲載や他サイトからの盗用が発覚し社会問題となった
伊沢拓司 そういうのはメディアとは呼ばないんだけどね!?
鶴崎修功 (笑)。当時、QuizKnockを立ち上げた背景には、そういった情報の氾濫やフェイクニュースへの問題意識もあったんですよね。
──2020年にKAI-YOU Premiumで取材した際には、WebメディアとしてのQuizKnockは当時「情報を待つ人から情報を探す人に」というテーマを掲げていたことについてもうかがいました。
伊沢拓司 今は動画メディアが主流になりましたが、QuizKnockのWeb記事の良さは失われていないと思っています。
ユーザーが記事に掲載されたクイズを解いて、クリックして回答をしたら成功が返ってくるという能動的な体験は、動画ではなかなか実現できません。
WebメディアとしてのQuizKnockのシステムは、10年目を迎えるにあたっても、強みがあるのかなと考えています。とはいえ、主流が動画になってきたのは事実ですよね。
伊沢拓司さんと鶴崎修功さん
須貝駿貴 僕ら自身は、情報を得るには、読む方が早いとは思っています。(他のメンバーを見て)みんなも読みものがたくさんあると嬉しいよね?
東言 テキストの方がタイパ(=タイムパフォーマンス。時間対効果)いいですよね。
須貝駿貴 そう。生成AIの登場でコンテンツを大量生産できるようになった今、Web上で文字情報ももっと増えてほしいと個人的には思っています。
伊沢拓司 動画と違ってテキストだと、検索から遡りやすいしね。
須貝駿貴 読むのが苦手な人は動画を見て、そうでない人はテキストを読んで、というようにどっちも増えて欲しいですね。
鶴崎修功 それでいうと、Webメディアは広告汚染と言われて数年が経ちますが、「読みにくいんだけどこのページ!?」みたいなサイトもすごく増えましたよね。
伊沢拓司 動画も今、広告がすごいですからね。
WebメディアとしてのQuizKnockも、サイト上に出す広告は協賛企業さんとコラボしたものを出すスタイルに変えました。そこは、Webメディアも動画も試行錯誤のあった10年なのかなと思います。
受動的か能動的か──河村拓哉が語る、YouTubeとWeb記事の違い
──みなさんはWebメディア・QuizKnockのライターとしても活動されていますが、WebメディアとYouTube、それぞれの媒体でコンテンツを制作する際に意識していることの違いはありますか?
ふくらP Web上の記事は、読者が自分の好きなスピードや順番で読むことを前提にしていて。対して、動画は基本的に、視聴者全員が同じ速度で、頭から順番に見ていくものだと考えています。最近は倍速視聴とかもありますけど。
なので動画は、情報の順番とか表示時間とかは結構気にしてつくっています。
河村拓哉 受け手が“視聴者”なのか“読者”なのか、という違いもあると思っていて。
動画は再生すれば自動で進んでくれるので、受動的にでも見ることができますが、文字は自分で「読もう」としないと中々頭に入ってきません。
そうしたメディアの特性を活かしつつも、自分が視聴者/読者だったら何を見たいか/読みたいかを考えてつくり分けています。
河村拓哉さん
──2022年にQuizKnockに加入した東問さん・東言さんは、QuizKnockの一ファンだった期間も長いかと思います。お二人から見て、QuizKnockのコンテンツは、WebメディアとYouTubeそれぞれでどのように映っていますでしょうか?
東言 作り手になったときも、「QuizKnockのこういう企画が(一ファンだった時代に)見ていて面白かったな」という体験が、コンテンツ制作のベースになっているかなと思います。
東問 まあでも、実は僕ら、記事はまだ書いたことがないんです。僕らが入った頃には、YouTubeの視聴者の方がWebメディアの読者よりも圧倒的に多くて。
東言 まだ僕ら、株式会社baton(=QuizKnockの運営会社)に正社員として入社してから半年の新入社員(※)なんですよ(笑)。
※東問さん、東言さんは大学生時代、アルバイトととしてQuizKnockの動画に出演していた。
ふくらP (笑)。
東言 これから仕事を覚えていく段階なので、今後WebメディアのQuizKnockで記事を書く機会も出てくると思います。その時は勉強しながらやっていきたいなと思いますね。
東問 もしかしたら「QuizKnock10周年プロジェクト」の中で、何かやることもあったりするかもしれないです。

この記事どう思う?
関連リンク

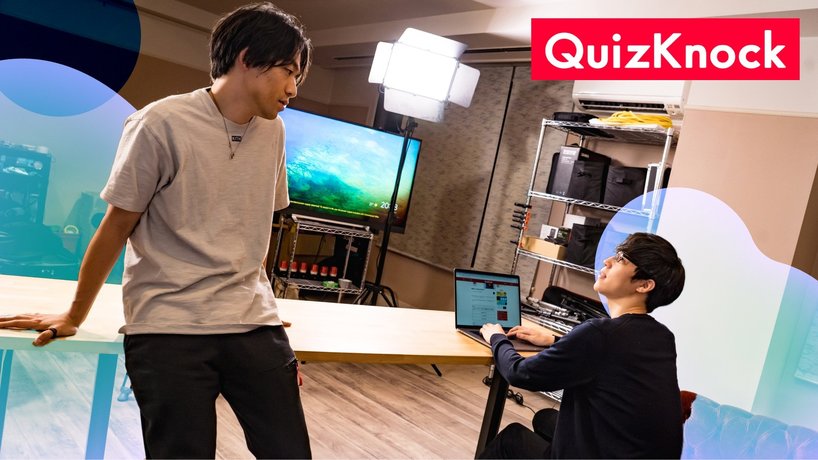


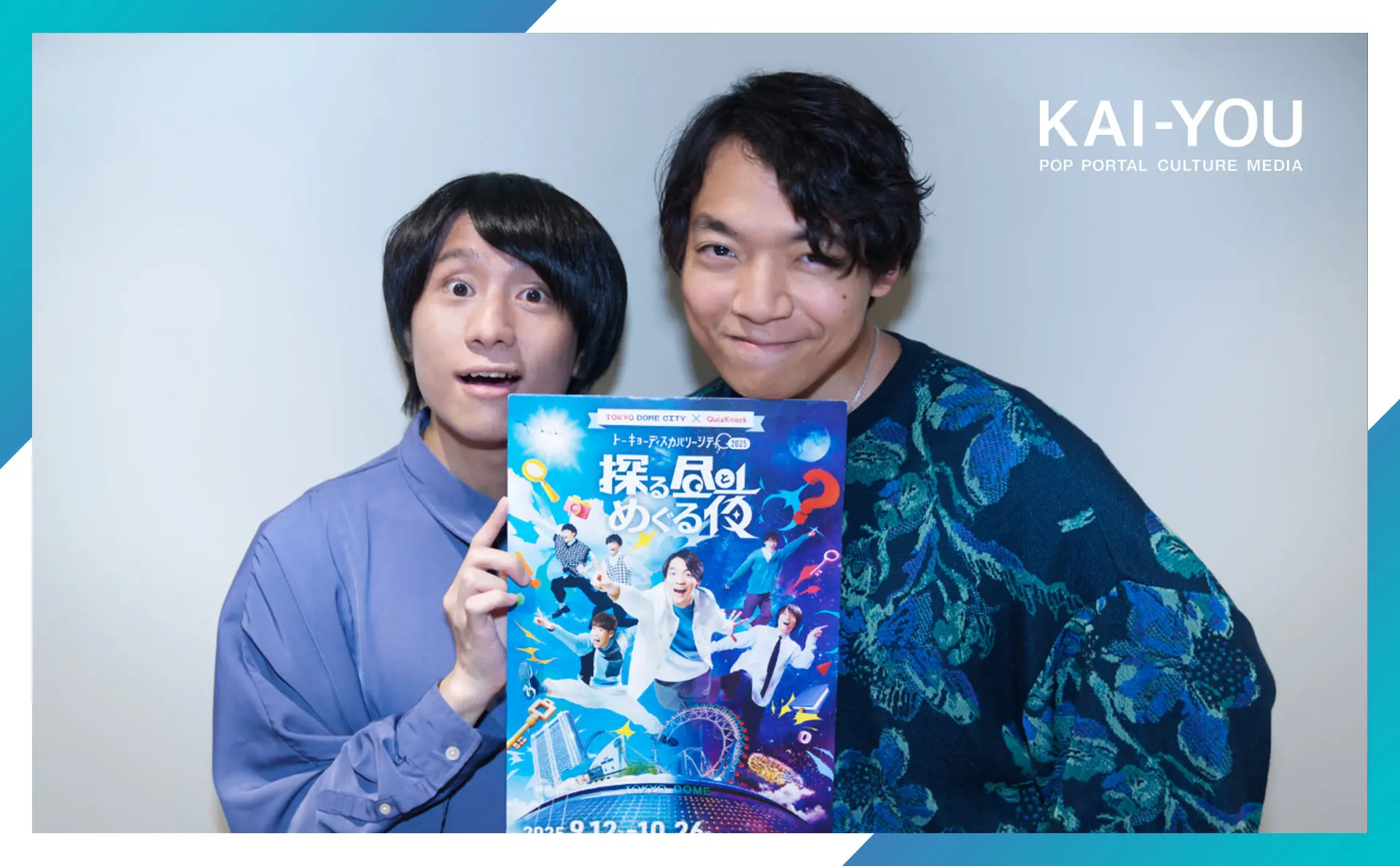

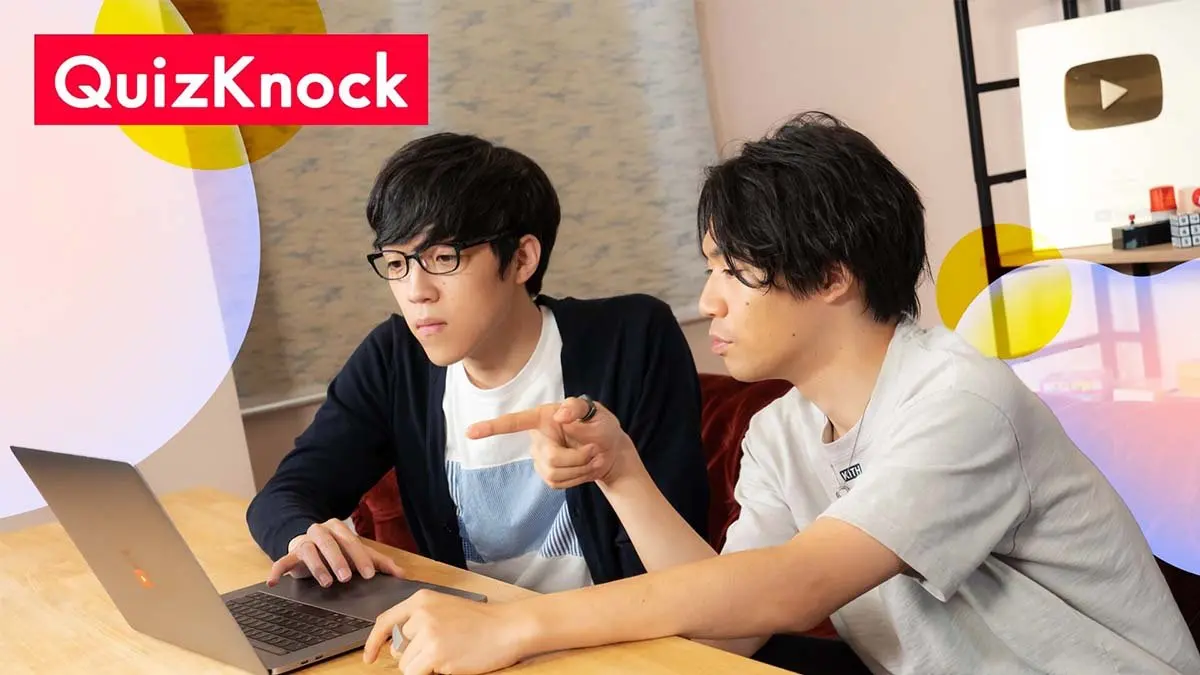


0件のコメント