知的エンタメ集団・QuizKnockがプロデュースした、東京ドームシティ全域を舞台にした大型イベント「トーキョーディスカバリーシティ!2025 探る昼とめぐる夜」が、9月12日(金)~10月26日(日)まで開催される。
本イベントは、前回のべ4万人超を動員した大好評イベント「トーキョーディスカバリーシティ!」シリーズの第3弾。
東京ドームシティ アトラクションズを舞台にした遊園地謎解きゲーム「いたずらおばけと最後のシャッターチャンス」や、QuizKnockメンバーのトークと豆知識が聞ける「QuizKnockのおせっかいラジオ〜シティ回遊ボイスラリー〜」などが展開。
その他にも、訪れる人々が東京ドームシティの魅力に触れられる、多彩なコンテンツが用意されている。
「トーキョーディスカバリーシティ!2025 探る昼とめぐる夜」の看板
今回KAI-YOUは、QuizKnockの伊沢拓司さんと山本祥彰さんの二人のクイズ王に取材を敢行。本イベントの見所について聞いたところ、昨今の謎解き人気や考察ブームにまで話が広がった。
取材・編集:都築陵佑 文・写真:タナカハルカ
目次
QuizKnockプロデュース「トーキョーディスカバリーシティ!」のコンセプトは“発見”
──まず、今回QuizKnockが「トーキョーディスカバリーシティ!」をプロデュースするにあたっての、コンセプトやこだわりのポイントについて教えてください。
取材に応える山本祥彰さん(左)と伊沢拓司さん(右)。山本祥彰さんはQuizKnock発の謎解き制作チーム・NazoLockのメンバーでもある
伊沢拓司 「トーキョーディスカバリーシティ!」は、“発見”を大事なキーワードとしてつくられています。東京ドームシティに来たことがある人でも別の見方ができたり、初めて来る人は「こういう楽しさがあるんだ!」と発見ができたり。
あと、知的コンテンツに触れる中で“自己を発見する”という体験を含めて、ディスカバリーなのかな、と。もう3年もやらせていただいてますね。
──私たちも今回、イベントを先行体験させてもらいましたが、各施設を巡る中で「東京ドームシティって、こんな場所もあるんだ!」という発見がありました。
伊沢拓司 本当にいろんなものがあるんですよ。
東京ドーム、LaQua、遊園地(東京ドームシティ アトラクションズ)、それぞれが別々の施設だと捉えられがちですが、一緒に楽しんだって面白い。「こんなところにこれがあったんだ。じゃあ今度行ってみようかな」と思える場所がたくさんある。
この懐の深さこそが東京ドームシティの魅力だと思いますし、イベントをプロデュースする我々としても学びを仕掛けやすくもありますね。
「QuizKnockのおせっかいラジオ〜シティ回遊ボイスラリー〜」を楽しむインタビュアー
山本祥彰 東京ドームシティ自体が、元々色んな面白さがちりばめられている場所なんですよね。
その面白さを起点にして、我々が学びや発見だったり、ひらめく喜びだったりを付け加えることによって、非常に良いコンテンツになるんです。
クイズ王・伊沢拓司、謎解きへの羨望を露わに
──今回の「トーキョーディスカバリーシティ!」では、QuizKnockの軸であるクイズではなく、謎解きゲームがメインコンテンツのひとつに据えられています。知識や視点を問うクイズと、発想力やひらめきを求められる謎解きでは、異なる部分があるのではないでしょうか。
山本祥彰 クイズと謎解きの大きな違いとして、参加障壁の違いがあるかなと思っていて。クイズって、知識がないと楽しめないと考えてしまう人や、「勉強」のイメージを嫌ってちょっと遠ざけちゃう人がいると思うんです。
それに比べて、謎解きは準備がいらない。与えられている情報だけで解くことができる。クイズと比べて参加のハードルがちょっと低く、より多くの人をターゲットにできるんです。
イベントに参加してもらえれば、我々は自信を持って皆さんに楽しさを届けられると自負しています。だからこそ、そのハードルを下げるために、クイズではなく謎解きを選んでいるところはありますね。
「QuizKnockのおせっかいラジオ 〜シティ回遊ボイスラリー〜」「いたずらおばけと最後のシャッターチャンス」のキット
伊沢拓司 もうひとつのメインコンテンツであるシティ回遊ボイスラリーの方は、逆に“ド知識”なんですけど(笑)。
とはいえやはり、謎解きは知的なコンテンツすべての入り口であり、会話のきっかけとしても機能している感じがするんですよね。「アマチュアクイズ」としてのクイズ文化に属する私からすると、それはめちゃくちゃ凄いことだなと。
とにかくみんな謎解きイベントに遊びに行っているし、僕自身もすごい誘われてます。
そこで誰かと一緒に謎解きをしていると、まっすぐ謎を解くために努力するとか、頭を使うとかが、すごく肯定されるじゃないですか。結果的にそれで自信もつくと思うので、すごく素敵なカルチャーだなと思いますね。
山本祥彰 謎解きは、基本的には誰しもが努力すれば必ずゴールに辿りつけるように設計されていて。努力する価値がある前提でつくられている。考える意味がある。努力が肯定される喜びみたいなものを味わいやすくて、 僕はそこにすごく魅力を感じています。
また、この謎解きで得られた成功体験が、他の学びとか勉強とかにも繋がるかなと思っています。僕自身、小さい頃に謎解きやひらめきクイズを通して得た喜びや成功体験が人生のベースにあるんです。
謎解きゲームではLINEを使用。熟練者にも新しい発見をもたらしつつ、初心者に「次も来たい」「頭を使うの楽しい」と思ってもらえることを第一に設計したと山本祥彰さんは語る
山本祥彰 逆に、謎解きのコミュニティを見ていると「全然謎解きできない/苦手なんですけど、謎解き大好きなんですよね」みたいな人も結構いるんです。
自分では解けないけど、答えを知った時の喜びが忘れられなくて謎解きに挑戦している。そういうところって、謎解きならではなのかなって思いますね。
伊沢拓司 クイズよりハードルが低くてうらやま! 僕らのクイズ業界ももっと敷居を下げたい。

この記事どう思う?
関連リンク





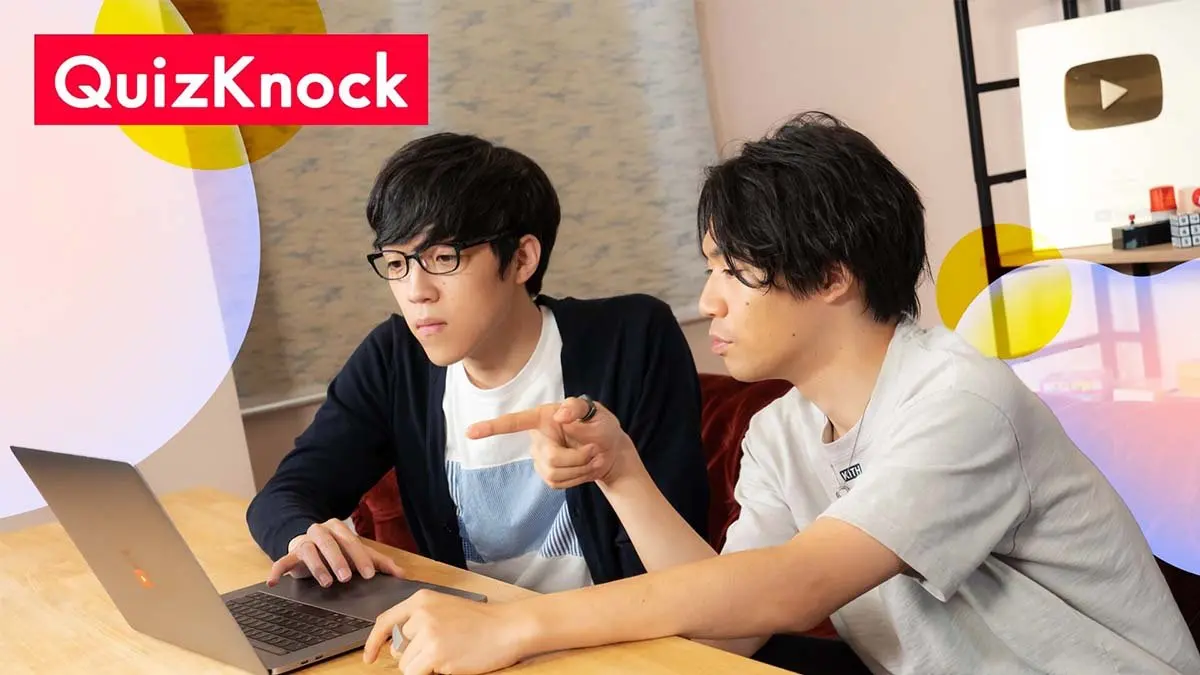

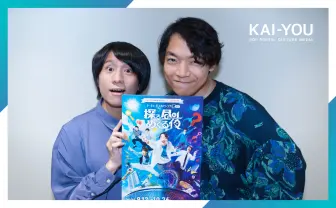
0件のコメント