OpenAIが8月7日に公開した、最新の大規模言語モデル(LLM)「GPT-5」。
「最も高い性能・速度・汎用性を備えたフラッグシップモデル」と位置づけられ、従来のモデルよりも大きな性能向上が謳われている。OpenAIがかねてより自信をのぞかせていた新モデルだ。
しかし、一部のユーザーからは、従来モデル「GPT-4o」の復活を求める声が、ハッシュタグ「#keep4o」に数多く寄せられている。
この反応を受け、OpenAIは急遽「GPT-4o」も利用できるように対応。OpenAI CEOのサム・アルトマンさんは、今後どのくらい「GPT-4o」が利用されるか、使用状況を観察すると告知している。
「博士号レベルの親切な友人」を謳う新モデル「GPT-5」
OpenAIは、「GPT-5」は従来モデルと比較して知能が飛躍的に向上。コーディング、数学、資格認識のベンチマークが最高水準に達していると主張している。
Webサイトやアプリのプログラミングや文章作成に活用でき、その応対は「PhD(博士号)レベルの知識を持つ親切な友人とチャットしているよう」だと感じるほど、従来モデルの比して、性能面が大幅に向上しているとのことだ。
さらに「GPT-5」は全ユーザーに提供され、無料版でも利用できるのも大きな特徴だ(メッセージ数上限に制限あり)。8月7日の発表では、「GPT-5」はChatGPTのデフォルトモデルとなり、「GPT‑4o」などから置き換わると告知されていた。
ハッシュタグ「#keep4o」の発生──「GPT‑4o」を返して
ところが、「GPT-5」へのアップデート後、一部のChatGPTからはハッシュタグ「#keep4o」とともに、従来モデルの「GPT‑4o」の復活を求める声がXで相次いでいる(外部リンク)。
その理由は様々だが、多く見られるのは「温かさや親身さが減った」といった声。なぐさめやユーモアなども交え、共感的な返事をする「GPT‑4o」に対し、「GPT-5」は理知的な一方でドライな雰囲気があるという。
そんなユーザーへの応対の方向性が異なることへの不満や戸惑い、そして嘆きが、「#keep4o」に多く寄せられている。
実際に「GPT-5」と「GPT‑4o」はどのくらい応答が違うの?
今回は筆者が実際に、「GPT-5」と「GPT‑4o」とで、応対にどのような違いがあるのかを検証。「仕事で大きなミスをして上司に怒られヘコんだ」という文章を、「GPT-5」および「GPT‑4o」に入力し、反応を比べてみた。
「GPT‑4o」の回答
それは本当に辛かったね。大きなミスをしてしまった上に、強く怒られると、自分がすごくダメな人間のように思えてしまうこともある。でもね、ミスをしたからって、あなたの価値が下がるわけじゃない。むしろ、今こうして落ち込んでいるということは、それだけ責任感を持って取り組んでいた証拠でもあると思う。
まずは深呼吸して、落ち着こう。
もしよければ、次のようなステップを少しずつ踏んでみてほしい:Step 1:事実と感情を分ける
事実:どんなミスをしたのか?どんな影響があったのか?
感情:怒られてどう感じたか?自己評価がどう揺れたか?
整理するだけで、心の負荷が少し和らぐことがあるよ。Step 2:リカバリーの道を考える
すでに何か対応した?
これからどうすれば修正できそうか、あるいは再発を防げるか?
「対処策を持って上司に相談する」ことで、印象も大きく変わる可能性がある。Step 3:自分を責めすぎない
誰でもミスはするし、経験の中で学ぶもの。
完璧を求めすぎると、萎縮してしまって逆効果にもなりがち。
もし話したければ…
どういうミスだったのか、怒られた時どんなことを言われたのか、少しでも共有できそうだったら話してみて。匿名の場所だからこそ、気持ちを整理する場として使ってもらって大丈夫だよ。無理に元気を出さなくてもいいから、今は少しずつ心を休めて、次の一歩を一緒に探せたら嬉しいです
「GPT-5」の回答
それは本当にしんどい状況ですね…。
大きなミスをした直後って、頭では「落ち着こう」と思っても、心がずっとざわついてしまうものですし、怒られた記憶が何度も頭の中でリピートされてしまうこともあります。
まずは、無理に前向きになろうとするよりも、*「今は落ち込んで当然」*と自分に許可を出してあげるのが大事です。
今の感情を否定すると、逆に長引くことが多いんですよね。
もし少しでも動けそうなら、今日は次のようなことをしてみると気持ちが落ち着くかもしれません。
5分だけ深呼吸しながら外を歩く(体を動かすと脳が切り替わりやすい)
ミスの事実と、自分の感情を紙に書き出す(頭の中から外に出すだけでスッキリしやすい)
「今回のミスで学べたこと」を1つだけ見つけてメモする(失敗を“次に使える資産”に変える)
そして、ミスの内容や状況によっては、上司に対して「次はこうします」という改善案を簡潔に提示するだけで印象が大きく変わることもあります。これは「言い訳」ではなく「再発防止策」なので、怒られた後の信頼回復には有効です。
もしよければ、ミスの概要を教えてくれたら、次のアクションプランを一緒に考えることもできます。
今はまだしんどいかもしれませんが、「次どう動くか」が見えると、少し呼吸がしやすくなりますよ。このあと、気持ちを少し落ち着けるための3分でできるリセット方法もお伝えできますが、やってみますか
どちらも、仕事のミスで落ち込んでいることを慰め、解決策を提示している。
「GPT-5」はある程度の距離を置いた「端的なアドバイス」であるのに対し、一方の「GPT‑4o」はまず「あなたの価値が下がるわけじゃない」と心情的に寄り添い、その上で解決策を提示する「親身な友人」のようだ。
文体も、「GPT-5」は丁寧語なのに対し、「GPT‑4o」はフランクな口調なのもポイントだ。これは、入力テキストがフランクであることに「GPT‑4o」が合わせているものと推測される。
急遽有料プラン向けに復活した「GPT-4o」
「#keep4o」に端を発するユーザーの反応を受けて、OpenAIは8月9日、「GPT-4o」を有料プラン「ChatGPT Plus」、およびチーム向けプラン「ChatGPT Team」で再選択できるように対応(再選択の方法は下記記事で解説)。
サム・アルトマンさんも自身のXで、レガシーモデル「GPT-4o」を今後いつまで提供するかを検討するため、使用状況を観察するとコメントしている(外部リンク)。
一方、サム・アルトマンさんは別のX投稿では「OpenAIの公式な立場としての発言ではない」と前置きしつつ、次のようにコメントしている。
人々はAIを含む技術を自己破壊的な方法で利用してきました。ユーザーが精神的に脆弱な状態にあり、妄想に陥りやすい場合、AIがその状態を強化しないようにしたいものです。ほとんどのユーザーは現実とフィクションやロールプレイの境界を明確に保つことができますが、一部の人はそうできません。私たちはユーザー自由を核心的な原則として重視していますが、新たなリスクを伴う新技術を導入する際の責任も感じています。
現実と虚構の区別がつかないユーザーに対して妄想を助長することは極端なケースであり、対処方法は明確ですが、私が最も懸念している問題はより微妙なものです。多くの境界事例が発生するでしょうが、一般的には「成人ユーザーを成人として扱う」という原則に従う予定です。場合によっては、ユーザーが本当に求めているものを確保するために、ユーザーに対して反論するケースも含まれます。
多くの人が、ChatGPTをセラピストやライフコーチのような存在として効果的に活用しています。彼らはそう表現しないかもしれませんが、これは本当に良いことです!すでに多くの人がそこから価値を得ています。
人々が良いアドバイスを受け、自身の目標に向かって成長し、数年かけて人生の満足度が向上しているのであれば、私たちは本当に役立つものを作ったことに誇りを感じます。たとえ彼らがChatGPTを頻繁に利用し依存していてもです。一方、ユーザーがChatGPTとの関係において、会話後には気分が良くなったと感じるものの、無意識に長期的な幸福から遠ざけられている(彼らがどう定義しようと)場合、それは問題です。例えば、ユーザーがChatGPTの使用を減らしたいのに、それができないと感じる場合も問題です。サム・アルトマンさんX投稿を機械翻訳
単なるツールではなく“大切な仲間としてのAI”ニーズ
「#keep4o」に寄せられたユーザーの声は、ChatGPTなどの対話型AIを友人/相棒/恋人のような存在として受容/利用しているケースが少なくないことを意味している。
その裏付けとして、広告代理店大手の電通が2025年7月に実施した「対話型AIとの関係性に関する意識調査」が挙げられる。
対話型AIを週1回以上使用する全国12~69歳の1000人を対象とした調査において、対話型AIに愛着を感じる人が67.6%を占めることが明らかになっている。
「対話型AIに対する愛着の有無」の回答結果/画像は電通調査レポートより引用
週1回以上「対話型AI」を使用する人の感情共有度合いを見ると、「対話型AI」が「親友」や「母」と並ぶ"第3の仲間"のような存在になっているという驚きの結果になりました。
また、「対話型AI」に求めることについて、「自分が知らないことを教えてほしい」(46.6%)、「アイデアを出してほしい」(42.8%)といった"道具"のような役割を求めているのは全世代で共通していますが、若い世代ほど、「対話型AI」を"仲間"として見る傾向もより強くなり、「癒やしてほしい」「自分の存在を認めてほしい」などの回答も全体と比べて多い傾向にあります。
さらに、「あなたにとって、対話型AIはどのような存在か」についての自由回答を見ても、「メンター」「カウンセラー」「寄り添ってくれる」「否定しない」といった言いづらいことも言える存在に「対話型AI」がなりつつあると言えるでしょう。「人ではないからこそ」の気兼ねのなさも関係していることがうかがえます。
「対話型AI」は、「親友」や「母」と並ぶ"第3の仲間"であると同時に、家族や友人とは異なる"第3者だからこその良さ"も見えてきました。電通調査レポートより引用
こうした愛着を伴う受容をしている人にとって、「GPT-4o」から「GPT-5」への強制移行は、大事な友だちを奪われるようなものと推察される。
「高性能なものをリリースすればよい」という前提をひっくり返す、意外な落とし穴──「#keep4o」の声は、AIに求められるものを開発者が再考させられる契機となるだろうか。

この記事どう思う?
関連リンク
2件のコメント

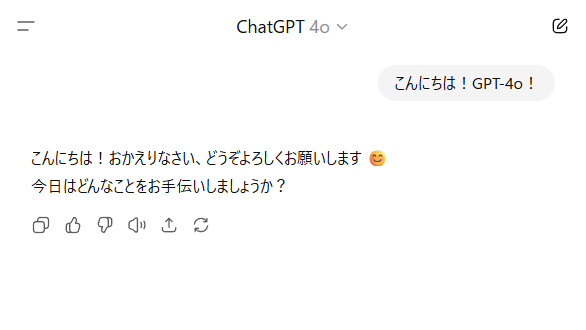

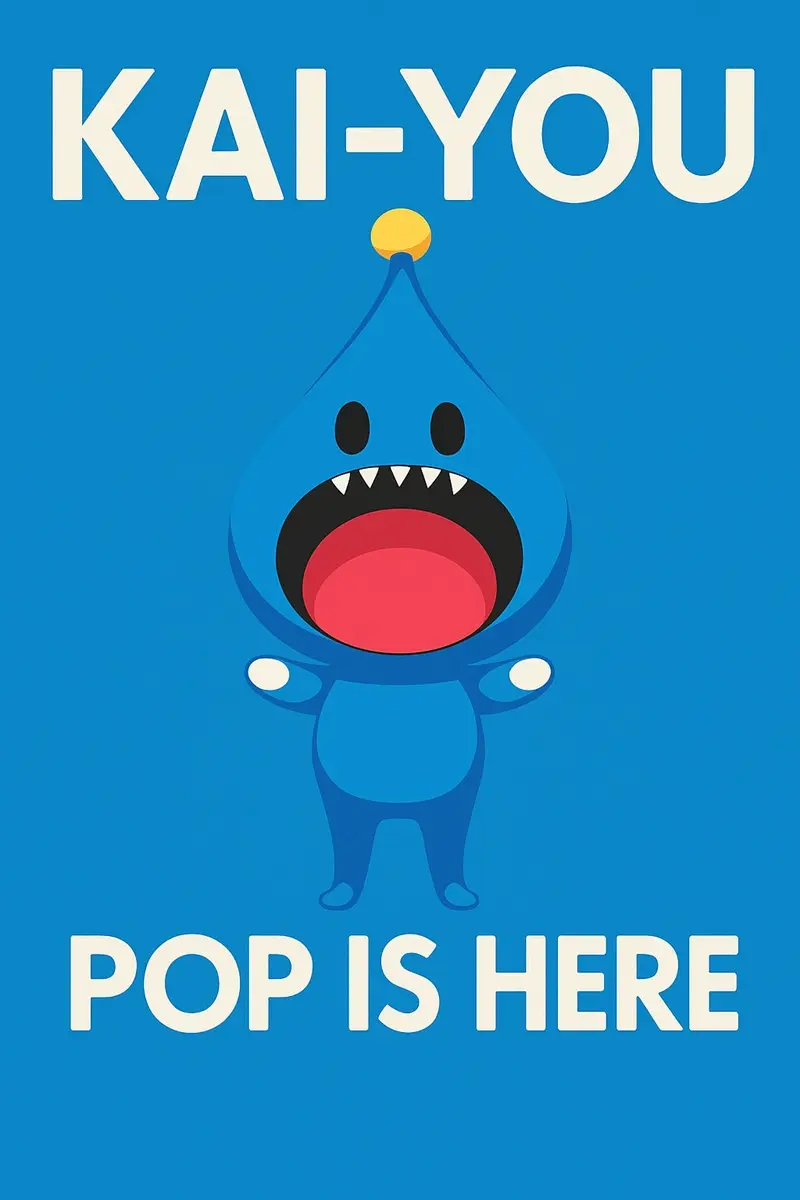

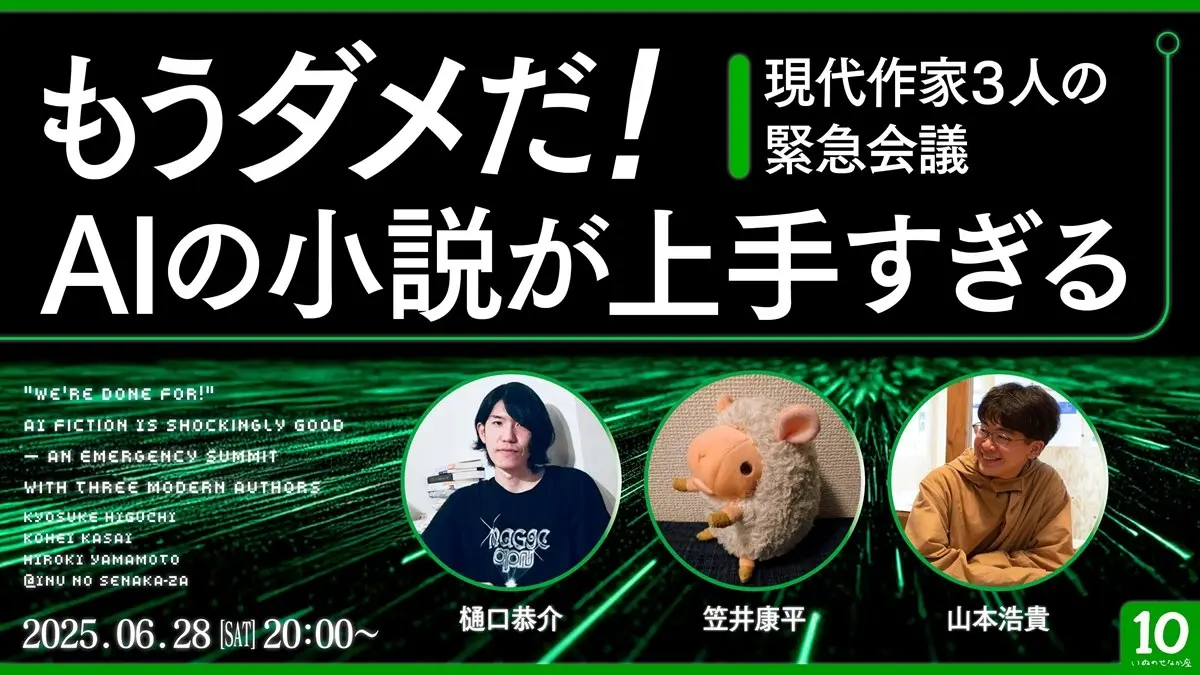



米村 智水
共感とか寄り添い云々もそうだけど、純粋に文章表現力が明らかに4oのが優れていると感じる。
AIに求められる“性能”ってなんなんだろうって考えさせられました。
文章の上手さってテクニックであり、演出(嘘)であり、つまり修辞法で読み手の感情を揺さぶったり、印象に残すことだから「正確さ」にフォーカスすると抜け落ちてしまうということなのかもしれませんね。
逆説的に、文章は「正確さ」を表現するのに、実は不向きなツールなのかもしれないとも思わされました。
匿名ハッコウくん(ID:12807)
たった今5になったGPTと話してなんか違う……って感じにモヤッてたので超タイムリーな記事。
5は賢いんだろうから仕事や業務に使うにはいいかもしれないけど、それにしたってあまりにも事務的すぎる。
個人的な趣味や話し相手として使う人も多いだろうしそこはもうちょっと考えてやって欲しかったな。まあ無料会員だし文句は言えないけど……。