東京国際工科専門職大学工科学部デジタルエンタテインメント学科講師の小野憲史さんが、チーム対戦ゲームにおける「怒り感情」を分析した発表資料を国内最大級の研究者情報データベース・researchmapに投稿した。
本発表資料によれば、5000件を超えるWebアンケートをもとにした調査により、「自分の怒りは味方に悪影響を与えると自覚している一方で、味方の怒りは自分に影響しないと考える」という認知の非対称性が確認されたという。
筆頭著者である髙橋樹生さんと、最終著者/責任著者の小野憲史さんは、本発表資料の中で、この傾向がプレイヤーの孤立化やチームの崩壊につながる可能性を指摘している。
FPSゲーマーは味方の怒りから受ける影響を小さく見積もりがち
発表資料『FPSチーム対戦ゲームにおける怒り感情がプレイヤー間に与える影響の構造分析』(著:高橋樹生・小野憲史)は、『Apex Legends』『VALORANT』などのチームで対戦するFPSにおける「怒り感情の自覚」と「他者への影響」をテーマにした研究。
小野憲史さんのXの投稿によれば、学生の卒業論文をもとに修正を加え、9月12日に開催された「日本デジタルゲーム学会」2025年夏季研究発表大会で発表されたものだという(外部リンク)。
調査は2024年8月から10月にかけて行われ、有効回答数は4918件にのぼった。プレイヤーが自認する怒り感情と、その影響範囲(自分→味方、味方→自分など)を統計的に比較している。
その結果、毎日プレイする層ほど自らの怒りを自覚している一方で、味方の怒り感情から受ける影響を小さく見積もる傾向が示されたという。
味方の怒りによって萎縮・集中などさまざまな反応が生じる一方、「自分は影響されない」と考える認知の偏りが見られたと分析している。
誤った自己責任意識がチーム崩壊やプレイヤー離脱の遠因に
資料では、こうした結果をもとに「FPSチーム対戦ゲームのコアユーザー間で誤った自己責任意識やストレスの内在化が進み、チーム崩壊やプレイヤー離脱の遠因となる危険性がある」との考察が示されている。
コアゲーマーは、味方プレイヤーの怒り感情が自分に与える影響を低く見積もりであると分析。
互いの善意が伝わらず、孤立を深めてしまうなどの事態が考えられるとしている。
今後は「社会的な喜び」などのポジティブ感情も含めた調査を
高橋樹生さんと小野憲史さんは、こうした状況を防ぐ手立てとして、プレイヤー教育とゲームデザインの両面からのアプローチを提案。
アンガーマネジメントの導入や、「自分だけが迷惑をかけている」認知を緩和するためのUI、などでチーム内の認知の非対称性を是正できる可能性があると説明した。
なお小野憲史さんは自身のXで「こちらの原稿は発表資料であり、論文ではありません。今後は今回の調査で得られた知見をもとに、さらに調査研究を進めていく所存です」とコメント。
また、今回の研究は怒り感情に焦点を当てたものであり、今後は「社会的な喜び」などのポジティブ感情も含めた調査を予定しているという。

この記事どう思う?
関連リンク




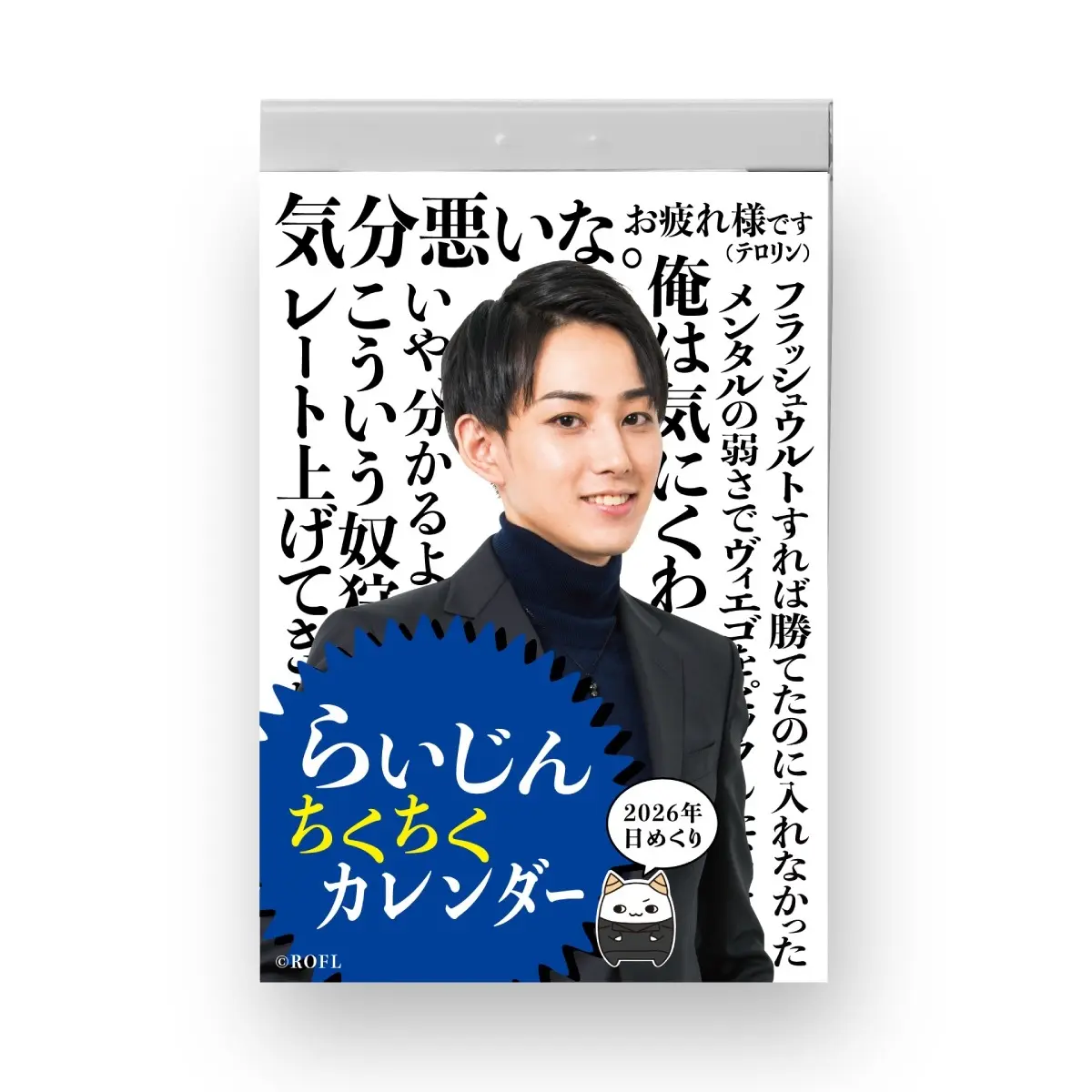


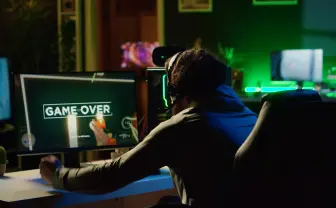
0件のコメント