4月1日、文化庁が「著作権契約書作成支援システム」をリニューアルし公開しました。
このシステムは、質問に回答していくことで、簡単かつ手軽に著作権契約書の雛形・テンプレートが作成できるというもの。日本語のみならず、英語の契約書(※)にも対応しています。
この記事では、この「著作権契約書作成支援システム」の使い方を解説・紹介しています。
※日本法に準拠。海外各国の法・慣習を念頭においた雛形・テンプレートではない。
実際の業務でも用いられることが多い著作権の譲渡に関する契約書などには対応されていません。
本システム構築に関する報告書では、「権利者が不用意に著作権を失わないように注意する必要があるため」などと理由を説明しています(外部リンク)。
このようなケースに対しては、参考資料として文化庁は「契約書マニュアル」を公開しています(外部リンク)。
なお、今回は「動画に他者の楽曲を使用したい」場合を想定して進めています。
今回は後者を選択。
今回は、「楽曲及び楽曲を伴う歌詞」を選択。
今回は、「既存の原稿(エッセイ、詩、小説など)やイラスト、写真、自作の楽曲・映画、舞踏(ダンス)・無言劇などの利用許諾」を選択。
なお、この「著作権契約書作成支援システム」はあくまでも雛形・テンプレートであり、文化庁は「実際に利用する場合は(中略)直しして使ってください」と呼びかけています。
「著作物」を巡る状況やその扱われ方は多様化の一途をたどっています。一般人も著作物に触れる機会が増え、扱うことが当たり前となりました。
しかしその一方で「著作権」の大切さや法律的な理解はあまり進んでいません。著作権などに関する契約を口頭で済ましてしまい、個人間でもトラブルに発展することがあります。
そこで文化庁は、平成18年(2006年)より公開している本システムの見直しを実施。「文書による契約を推進」するため、時代に合わせて再構築したということです。
このシステムは、質問に回答していくことで、簡単かつ手軽に著作権契約書の雛形・テンプレートが作成できるというもの。日本語のみならず、英語の契約書(※)にも対応しています。
この記事では、この「著作権契約書作成支援システム」の使い方を解説・紹介しています。
※日本法に準拠。海外各国の法・慣習を念頭においた雛形・テンプレートではない。
一般人同士の契約を想定 著作権譲渡契約には未対応
この「著作権契約書作成支援システム」は、対企業ではなく個人同士の契約を想定しており、著作権の利用許諾に関する契約書の雛形・テンプレートが作成できます。実際の業務でも用いられることが多い著作権の譲渡に関する契約書などには対応されていません。
本システム構築に関する報告書では、「権利者が不用意に著作権を失わないように注意する必要があるため」などと理由を説明しています(外部リンク)。
このようなケースに対しては、参考資料として文化庁は「契約書マニュアル」を公開しています(外部リンク)。
回答だけで簡単・手軽に雛形・テンプレート作成
「著作権契約書作成支援システム」/以下、画像はスクリーンショット
なお、今回は「動画に他者の楽曲を使用したい」場合を想定して進めています。
契約書作成のための契約書選択
今回は後者を選択。
今回は、「楽曲及び楽曲を伴う歌詞」を選択。
今回は、「既存の原稿(エッセイ、詩、小説など)やイラスト、写真、自作の楽曲・映画、舞踏(ダンス)・無言劇などの利用許諾」を選択。
契約書の作成
なお、この「著作権契約書作成支援システム」はあくまでも雛形・テンプレートであり、文化庁は「実際に利用する場合は(中略)直しして使ってください」と呼びかけています。
文化庁「文書による契約を推進」
スマートフォン・パソコンが普及・発展した現代。SNSなどインターネット上のプラットフォームにおける著作物の制作や二次利用が増加。「著作物」を巡る状況やその扱われ方は多様化の一途をたどっています。一般人も著作物に触れる機会が増え、扱うことが当たり前となりました。
しかしその一方で「著作権」の大切さや法律的な理解はあまり進んでいません。著作権などに関する契約を口頭で済ましてしまい、個人間でもトラブルに発展することがあります。
そこで文化庁は、平成18年(2006年)より公開している本システムの見直しを実施。「文書による契約を推進」するため、時代に合わせて再構築したということです。
もっと知りたい!超情報社会における著作権

この記事どう思う?
関連リンク



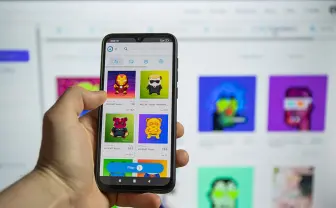



0件のコメント