昨年末に刊行された、『ウルトラマンと戦後サブカルチャーの風景』の著者である文芸批評家・福嶋亮大と、企画者である批評誌『PLANETS』編集長・宇野常寛の対談を通して探る本連載。
第2回では、戦後のテクノロジーへのへの1960年代「昭和ウルトラ初期」での、現実の社会や文明を批評した両義性をもつ怪獣から、1970年代・大阪万博以降のウルトラ第2期や『仮面ライダー』の時期では、人間の内面的な心の不安定さやトラウマを映し出した怪獣へと変容していったことを語った。 第3回となる本稿では、昭和特撮が遺したものを『新世紀エヴァンゲリオン』、『シン・ゴジラ』の庵野秀明や『攻殻機動隊』の押井守らが、どのように応用し、戦後サブカルチャーの想像力を形づくっていったかを明らかにしていく。
そしてそこから見えたのは、現代の映像作品がかつての「昭和特撮」に回帰しながらも、袋小路に陥っているということだった。
対談構成:佐藤賢二 リード:和田拓也
なぜ改めて怪獣の「風景」論を語るべきなのか
宇野常寛(以下、宇野) 本来、ミニチュア特撮自体が、テクノロジー的に「風景との対峙」だった。しかし、ウルトラ第2期のころには、たとえば『ウルトラマンレオ』(1974年)は光線技をあまり使わずにキックで戦ったり、半分は『仮面ライダー』化してる。『仮面ライダー』は、ミニチュアを使わなくても、アクション俳優が頑張れば特撮ヒーロー番組はできるという、予算削減の手段でもあったはずだから。
その意味でウルトラ第2期は、特撮のアイデンティティが変化していく過程でもあった。その中で大きく生き残ったのが、市川森一的なトラウマの表現としての怪獣で、それが特撮からアニメの『新世紀エヴァンゲリオン』や『SSSS.GRIDMAN』にも受け継がれてる。
この本で言う市川森一的なモチーフが一番残ったという皮肉な事実が、今のサブカルチャーの想像力を規定している面があると思うんだよね。
『新世紀エヴァンゲリオン』
単純な話として、現代では巨大なヒーローというフィクションを描くのは難しい。でも、怪獣の方は嘘が通用するところがあると思うんだよね。実際、原発事故や災害が起こると、それが怪物的なものに見えてくる。
怪獣は社会の「内部」の亀裂や無意識のきしみから生成することができるけれど、逆にヒーローは僕らが住んでいる世界とはまったく別の領域、つまり「外部」に対する想像力が無いと生まれないと思うんですよ。
現に1970年代以降、ヒーローはアイドルに置き換えられていく。大林宣彦は77年の『HOUSE』でそのことを的確につかんでいた。ヒーローの敵は、実は怪獣ではなくてアイドルという気もする。
宇野 『シン・ゴジラ』は円谷英二への回帰で、『SSSS.GRIDMAN』は市川森一的なものを引き継いでいるわけですよね。
アニメ『SSSS.GRIDMAN』
2013年ごろ、もし将来に日本のサブカルチャー史の教科書が書かれたとき、1995年に放送開始した『エヴァンゲリオン』から、2007年に登場した『初音ミク』の間は、何も無かったと書かれるんじゃないかという話になった。
『シン・ゴジラ』は優れた作品で、僕も大好きだけど、架空の近未来のフランスを描いたウェルベックの『服従』みたいに、現代社会に対する気の利いた嫌味を言ってインテリが喜んでいる作品だとも思うんだよね。あれが限界なのかなと思うと、けっこう辛い。なぜかというとこれは作家の問題ではなく、完全に時代の問題だから。
『シン・ゴジラ』/(C)2016 TOHO CO., LTD.
たとえば、実相寺昭雄(1937~2006年)はATG(※1)で前衛的な映画を撮ったりしているけれど、その前にテレビでつくった『ウルトラマン』や『セブン』の方が後世まで残る作品になっちゃってる。
前衛の「お座敷」として用意されたATGでは、彼の創造性はイマイチ冴えない。むしろテレビ特撮みたいなアナーキーなメディアのほうが面白いものが作れたわけです。
押井守さんも『うる星やつら』ではちゃめちゃな演出をやったりしていたけど、それもテレビアニメというオートマティックな反復が可能な枠があるからこそできることだった。図らずもテレビを「ポスト前衛」にしてしまった実相寺さんの歩みは、押井さんや庵野さんの原点のようなところがある。ただ、今はそのテレビも体制になってしまったから。
宇野 当時のテレビは、今のネットのような新興メディアですね。
※1:日本アート・シアター・ギルド。低予算ながらも監督の自由を保証し、非商業主義的な芸術作品を製作・配給した映画会社(1961〜1992年)
現代の映像文化が陥っている袋小路
福嶋 あと問題なのは、最近のサブカルチャーが芸術的に完成度を上げようとして、妙な大作化が進んでしまっていること。庵野さんはもう20年以上も『エヴァンゲリオン』をつくり続けているけど、作品に新しい生命を吹き込んでいこうとするならば、『シン・ゴジラ』のように、むしろ(『エヴァ』とは)違う作品をつくった方が良いと素人的には思うんです。 福嶋 押井さんで言えば、90年代に『機動警察パトレイバー』や『攻殻機動隊』を作ることによって、80年代のテレビ版『うる星やつら』とか映画の『ビューティフル・ドリーマー』に新しい光が当たることもあったわけでしょう。
実際『シン・ゴジラ』によって『エヴァンゲリオン』の見方が変わってくることも十分ありえる。手塚治虫だって自作にパッと見切りをつけて次の作品にジャンプし続けていたわけだし、その軽さが「ポップカルチャー」というものだと思う。でも、最近はそういうことがやり辛くなっているのかもしれない。
宇野 今の邦画の興行収入ランキングを見ると、たとえば『君の名は。』みたいなアニメに席巻されてる。
アニメを中心とした映像系サブカルチャーが、団塊ジュニアより下の世代では最大の共通言語になっていて、それを支える社会的な要請に応えるものになっちゃってるんだよね。
『君の名は。』
福嶋 そういう袋小路から逃れるためにも、批評家はマクロでダイナミックな映画史的な考え方をもっと導入したほうがいいよね。
この本では、円谷英二は「演劇的映画」から「映画的映画」への流れを技術者として推し進めた人だと書きました。そもそも、映画は演劇を原点にしながら、それを切断して成立している。今でも映画館を劇場と呼ぶのはその名残ですよね。
今はこの100年前に一度切断したものが、もう一度リターンしつつあると思う。この前、宇野さんに勧められて『ボヘミアン・ラプソディ』を観に行ったんですが、この映画は要するにライブの複製で、その点では映画は再び劇場に回帰しているわけです。劇をする場というか、パフォーマンスの場としての映画館ですね。
宇野 ハリウッドはブロードウェイへの対抗心から成立した側面もあるわけだしね。
映画史の原点「ドキュメンタリー」「特撮」に回帰する現代映画
福嶋 映画史の原点にはまずリュミエール(1864~1948年)(※2)がまずいるわけだけど、彼はドキュメンタリー的な映像を撮った。列車が駅に入ってくるだけの映像が観客には驚きだった。※2:フランスの映画発明者で「映画の父」と呼ばれる。世界初の実用カラー写真の開発者でもある。
次に登場したメリエス(1861~1938年)はもともと奇術師で、劇場で奇術としてやっていたことを映像で見せる発想から、『月世界旅行』(1902年)など初期の特撮SF映画を撮ったわけです。ドキュメンタリーと特撮が映画の原点にあったわけで、円谷英二も本多猪四郎もその延長線上にある。
『ボヘミアン・ラプソディ』もライブの記録(の複製)と劇場への回帰という意味では、映画史の原点に帰りつつあるという気がするんですね。
『ボヘミアン・ラプソディ』
たとえば『グレイテスト・ショーマン』も、自分たちは昔のショービジネスをこういう距離感で捉えてますよ、といったハリウッドの自意識の話でしょう。テレビドラマの『グリー』あたりから輸入してるんだろうけれど、一方に『ラ・ラ・ランド』や『ボヘミアン・ラプソディ』みたいなリッチなミュージカル映画があって、もう一方にマーベル的な特撮があって、映画はリュミエールとメリエスがつくった二つの方向性に回帰してるといえる。
そして本来、その中間に、ドラマを中心とした20世紀的な劇映画があったはずなんだけど、今はそこが抜け落ちて、Netflixのドラマとかに行ってるわけだね。
福嶋 現代では劇映画という制度は難しくなってきているんでしょうね。
宇野 日本はミュージカル映画のノウハウは比較的弱いかもしれないけれど、特撮に関してはあるはずなんだよ。マーベルとは違うタイプの特撮作品が現れて、今の『ラ・ラ・ランド』や『ボヘミアン・ラプソディ』的なものに拮抗してもいいはずなんだよね。
日本特撮/サブカルチャーは三世代の協働によってつくられた
福嶋 押井守さんは「すべての映画はアニメになる」と言っていましたが、特撮もアニメと実質的に変わらなくなっている。その記号的な映像のなかから、マーベルとは別の特撮が出てくると面白いですね。そもそも、演劇は観る角度によってイメージはまったく違ってくる。僕らがここで喋っている様子も、どの席から観るかによって変わるわけですね。それに対して、映画だと、どの席に座っても同じ一つのイメージを共有することができる。これがとても大きな発明だった。
しかし、今はそのような映画の統合機能が壊れつつあるんだと思います。みんな家で個別バラバラの映像を観る状況になっている。映像の時間的な長さにしても、インターネットの映像は10秒とか20秒あれば良い。
時間や空間を占有できる映像の寿命が短くなってきているから、『ボヘミアン・ラプソディ』みたいにライブの複製で時空をむりやり再支配しようとするわけです。とはいえ、最終的にはオリジナルな劇映画を撮れる人を頑張って育てていかないと、映画はもたないという気はしますね。
宇野 今の映画の興行収入は、作品自体の消費より、コミュニケーション消費というかイベント消費で保ってるわけでしょう。今のままだと、20世紀的な劇映画という制度自体の支配力が純粋に落ちていく。
こうした中で、たとえばNetflixのオリジナルコンテンツが1960年代のウルトラシリーズのように機能するのか、そこから新しい実相寺昭雄や押井守のようなアプローチが出てくるのかが問われると思いますね。
福嶋 そうですね。僕はこの本で世代論をしつこくやりましたが、それは文化が一つの世代ではつくれないということを強調するためです。
日本の特撮は、平たくいえば三世代の力でつくられていて、最初が円谷英二の世代、その次が円谷英二の息子の世代で、その次が庵野秀明さんの世代なんだよね。面白いことに、これがちょうど昭和天皇(1901~1989年)と、平成の明仁天皇(1933年~)と、次の天皇である皇太子(1960年~)と、世代的にぴったり重なる。今の皇太子が最初にデパートで買った本が大伴昌司の『怪獣図鑑』だった。オタクの時代は皇太子によって予告されていたわけですね。 福嶋 たいていの世代論は自分の属した世代に視野が限定されている。するとただのノスタルジックな語りになってしまう。しかし、本当に大事なのは世代間のコミュニケーションなんです。ある世代がつくったものを、次の世代がどう受け継いだかを読み解いていくのは、純粋に楽しいことですしね。しかし残念ながら、そういう線の引き方は、日本の文化史の記述においてとても弱いと思う。
宇野 庵野秀明は、逆に世代を引き受けすぎた作家だと思いますね。自分のオリジナリティは、アマチュアの学生映画のような自意識の発露に留めて、上の世代の映像作品の技術や方法論をすべて引き継ごうとした。
その振る舞い自体がアイロニカルだと思うけれど、むしろそれが彼の持ち味になっていったんですね。円谷英二の世代が、結果的に特撮怪獣映画というジャンルをつくり、その息子世代がテレビという新しい媒体で異化して、表現の裾野を広げた。その遺産を押井守や庵野秀明らアニメの有名監督が応用して、戦後サブカルチャーの想像力を形づくっていった。
でも、庵野秀明まで受け継がれていたものを、その下の新海誠や細田守の世代が継承しているかといったら、そうは思えない。いや、引き継がれているものも多いのだけど、断絶のほうが目立ってしまう。なぜ断絶が起こったかは、はっきりとは言えない。
その結果が『SSSS.GRIDMAN』によく現れてる。あれはよくできてるとは思うけど、良くも悪くも二次創作的。市川森一たちがやっていたことと、ゼロ年代風のループものの組み合わせをしっかりやりきってしまっている。それを、庵野秀明が中心にいたGAINAXから分派したTRIGGERが作った、ということも含めて、ちょっと皮肉な状況だと思う。
(第4回へ続く)
日本のカルチャーをもっと知る

この記事どう思う?
イベント情報
ウルトラマンと戦後サブカルチャーの風景
- 著者
- 福嶋亮大
- 発売
- 2018年12月17日
- 価格
- 2,800円+税
- 頁数
- 288頁
- 販売元
- PLANETS/第二次惑星開発委員会
PLANETS公式オンラインストアなら、脚本家・上原正三さんとの対談冊子『ウルトラマンの原風景をめぐって――沖縄・怪獣・戦後メディア』つき!(数量限定・なくなり次第終了)
全国の書店、Amazonでも発売中
福嶋亮大(ふくしま・りょうた)
文芸批評家
1981年京都市生まれ。京都大学文学部博士後期課程修了。現在は立教大学文学部文芸思想専修准教授。文芸からサブカルチャーまで、東アジアの近世からポストモダンまでを横断する多角的な批評を試みている。著書に『復興文化論』(サントリー学芸賞受賞作)『厄介な遺産』(やまなし文学賞受賞作)『辺境の思想』(共著)『神話が考える』がある。

宇野常寛(うの・つねひろ)
評論家/批評誌〈PLANETS〉編集長
1978年生まれ。著書に『ゼロ年代の想像力』(早川書房)、『リトル・ピープルの時代』(幻冬舎)、『母性のディストピア』(集英社)、『日本文化の論点』(筑摩書房)、石破茂との対談『こんな日本をつくりたい』(太田出版)、『静かなる革命へのブループリント この国の未来をつくる7つの対話』(河出書房新社)など多数。京都精華大学ポピュラーカルチャー学部非常勤講師、立教大学兼任講師。

連載
昨年末に刊行された、『ウルトラマンと戦後サブカルチャーの風景』。 戦前までさかのぼった映画史における円谷特撮、そして戦後サブカルチャー史の中での「昭和ウルトラ」を位置付ける作品だ。その著者である福嶋亮大と、同書の企画者・宇野常寛による全4回の連載対談。初代の『ウルトラマン』をはじめ、戦後の特撮作品は現代に何を問いかけるのか。


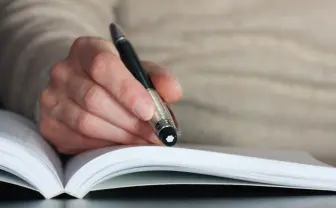






0件のコメント