「量より質」に集中できる環境が必要
──何人かの研究者は、ポケモンの論文が偽物であることを見抜けず、それを本物の論文に引用してしまったそうですが、実際にはどういった形で引用が行われていたのでしょうか?
マタン・シェローミ その引用してしまった論文は『The COVID-19 Outbreak’s Multiple Effects』というもので、感染症について書くべき立場にない退職したチュニジア人の物理学者が、International Journal of Engineering Research & Technologyというこれまた感染症の論文を載せるべきでない「ハゲタカ・ジャーナル」に発表したものでした。
中身はご想像どおり完全なゴミで、「コロナはチュニジアのハーブで治る」などと主張していました。彼は私のズバット論文を引用しただけでなく、その中に出てくる架空の参考文献『“Signs and Symptoms of Pokérus infection(ポケルス感染の徴候と症状)』まで引用していたのです。
もし彼が私の授業の学生なら、成績はFです。存在しないテーマについて、存在しない論文、それどころか読んでもいない論文を、仮に実在していたとしても内容に即していない形で引用していたんですから。彼がポケモンに詳しくないのは理解できますが、存在しない論文を引用することは断じて許されません。
──なぜ、彼がそのような論文を執筆してしまったか推測していますか?
マタン・シェローミ 私は彼にメールを送り、ここで書いているよりかはもっと穏やかな言い方で「どうしてこれで問題ないと思ったのか」と尋ねました。彼の返事は、「パンデミック中は他にやることがなく、この論文の掲載にかかった費用はたった3ドルだったので、悪いことではないと思った」というものでした(多くの雑誌は、真っ当なものも偽物も、発展途上国の著者に料金を割り引くんです)。
彼のしたことには、本当に数え切れないほどの問題があるでしょう。中でも最悪なのは、この論文が彼自身を愚か者に見せてしまっていることです。この事例は、「ハゲタカ・ジャーナル」に関する無知がどれほどまでに広がっていて、どれほど深刻な影響を及ぼしているか、そして発展途上国の研究者こそが連中の最大の被害者であることを物語っていると言えるでしょう。
──偽論文の発表から数年が経ち、現在このプロジェクトの影響をどのように評価していますか?
マタン・シェローミ はっきり言うのは難しいですね。「ハゲタカ・ジャーナル」を立ち上げるのは簡単ですし、そこに偽論文を載せるのも簡単です。一方で、「おとり調査」について正規の学術誌に正規の論文を発表するのは非常に難しく、膨大な時間もかかります。そして特に残念なことに、「ハゲタカ・ジャーナル」の実態を理解していない人々はいまだに存在していますから。
とはいえ、私のズバット論文は複数の言語でいくつかの論文に引用されており、それらはおそらく「ハゲタカ・ジャーナル」に関する文脈で正しく引用されているので、人気のあった偽論文の一例として加えられることは嬉しく思っています。
認知を高めることは重要です。ただその一方で、私はこうも思うんです。「需要がなくならない限りは、「ハゲタカ・ジャーナル」が消えることもない」だろうと。たとえば中国では、データ捏造などの研究不正による劣悪な研究が、「ハゲタカ・ジャーナル」や正規の出版社を問わず発表されてしまうという広範な問題が起き続けています。
これは政府が「学術関係者全員に、医師のような研究職でない人も含めて、毎年複数の論文を発表させる」という圧力をかけているためです。
そもそもの要求が非現実的なので、データの捏造やAI生成の論文、そして「ハゲタカ・ジャーナル」への投稿が横行してしまっているんです。その不合理な要求を取り除き、研究者が「量より質」に集中できるようにすれば、近道に頼ったり不正に手を染める圧力は消えるはずでしょう。
未来に向けて、恐れずに声を上げる
──今後も同様のアプローチで「学術的フェイク」を通じた問題提起を続けるご予定はありますか?
マタン・シェローミ 現在は本業の研究論文を発表するのに忙しく、偽論文に時間を割く余裕はありませんね! ですが、いつかまた戻ってくることになるだろうとは、確信しています。
──最後にこれを読んでいる日本のゲーマー、そして研究者たちに、メッセージをお願いします。
マタン・シェローミ まずは研究者の皆さんへ——質の悪い論文を見かけたら、恐れず声を上げてください。必ずしも「ハゲタカ・ジャーナル」を騙す必要はありません。むしろ、誤りのある論文を読んだら、ためらわずに(そして丁寧に!)雑誌や著者にメールして間違いを指摘してください。そうして誤りは正されていきます。
著しく質が低い論文や、不正(たとえば画像の合成など)が疑われる論文を読んだ場合も、遠慮せず雑誌に懸念を伝えてください。状況が適切なら、懸念表明やコメントの手紙を公開することもできます(対象論文が掲載から数か月以内で、かつ雑誌が倫理的に運営されていることが前提ですが)。
この種の「出版後査読」はシステムの運用に不可欠なものですが、実践されることがあまりにも少ないのが現状です。誰かがやるのを待たないでください!何かを見たなら、何かを言いましょう!
そして日本のゲーマーの皆さんへ——革新を止めないで! そして、ビデオゲームへの情熱をアカデミアと結びつける方法があるのかと疑問に思ったことがあるなら、安心してください。そこに方法は必ずありますし、なにより、すごく楽しいものですよ!

この記事どう思う?
関連リンク





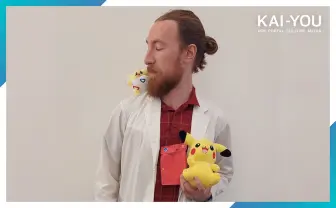
0件のコメント