全ての論文は「批判的」に読む必要がある
──ポケモンをテーマに論文を書いたことは、「ハゲタカ・ジャーナル」を告発するためだったんですよね。最初から彼らを“騙せる”という意識はあったのでしょうか?
マタン・シェローミ 詐欺師を騙すことは「騙し」になるでしょうか? もし彼らが掲載内容に興味を持っていないなら、偽論文を載せることが彼らの名誉を傷つけることになるでしょうか? 当然、そんな訳はありませんよ。
だって彼らは金さえ手に入るんだったら何も気にしないんだから!(もし無償で掲載してしまうのなら、それは流石に彼ら自身の問題でしょう)。「ハゲタカ・ジャーナル」どもに、慈悲は不要です!
彼らは主に発展途上国の弱い立場にある研究者を欺き、搾取する、犯罪的な組織です。こうした雑誌やその運営者たちは、自分たちが悪事を働いていることを分かってるんです。おとり調査で彼らを刺すことは誰も傷つけず、問題への認知を高めます。読者が一度でも「おとり」を見抜けば、見た目がどれほどそれらしくても、論文を盲目的に信じることはなくなるでしょう。
それこそ、最近もズバット論文に騙されてしまった人のブログ記事を読みましたが、その人も「もう二度と同じ過ちを繰り返さない」と言ってましたから(外部リンク)。
さらに言えば、私は実のところ彼らを騙してすらいないんです。何故なら私の論文には、文字どおりそれが”偽物”だと書いてあるからです! たとえばズバット論文では「この論文を掲載する雑誌は査読を実施していないはずであり、ゆえにハゲタカ・ジャーナルと言えるだろう」と文中で明言しています。
もし査読者が実在していて、この論文に目を通していたのなら、いくつも混ぜ込んでおいた数々の巨大な”フラッグ”に気付かないはずがないんですよ。逆に言えば、この論文が掲載されているということは、それらの雑誌に掲載されている論文は誰一人として読んでないってことです。「これを掲載するような雑誌はハゲタカ・ジャーナルですよ!」ってわざわざ主張しているにもかかわらずね。
騙す相手がそもそもいないんです。すべてが自動化され、ボットによって動かされている。ぜーんぶ、偽物です。私がしたことは、犯罪的な事業の実態を誰の目にも明らかにするために、低品質の原稿を投稿しただけ。もし彼らがそれを掲載することを選んだのなら、それは彼らの責任でしょう?
──現在アカデミックの場が抱える「ハゲタカ・ジャーナル」の問題について、どこに問題点を感じているかを教えてください。
マタン・シェローミ 「ハゲタカ・ジャーナル」の存在を最初にどう知ったのかははっきり覚えていませんが、私はいつの頃からか科学・研究・出版倫理というテーマに非常に深く踏み込むようになっていました。実際、このテーマについては実在の学術誌に本物の論文も書いています(外部リンク)。
私たちは「科学は真実の源であり、その真実は査読制度によって誠実さが保たれた学術論文という形で届けられる」と考えがちです。しかし残念ながら、現実はそうではありません。
「ハゲタカ・ジャーナル」は、意味不明で妄想的なゴミのような論文が出版される経路の一つにすぎません。査読付きのジャーナルでさえ、ときに警戒をゆるめることがあります。
──悪質な論文に問題を感じるようになったきっかけの論文などはありますか。
マタン・シェローミ 例えば著名な科学雑誌の一つ『Proteomics』は、かつて「ミトコンドリアには魂がある」と主張する論文を掲載したことがあります。私はその論文が査読を経ているとは一瞬たりとも信じていません。タイトルを見ただけで、宗教的なナンセンスを科学っぽくおおったものだと警告されるべきだったと思います。それでも、どういうわけかそれが通ってしまったんですよ。
もちろん、優れた査読であっても誤りがすり抜けることはあるでしょう。私はこれまで、掲載済み論文の誤りを指摘する書簡を何度も学術雑誌に送ってきました。誤りが軽微であれば、著者は感謝して素早く訂正を出します。
ですが、粗悪さや不正行為の可能性を示唆する深刻な誤りとなると、著者は防御的になり、ときには出版社側も同様の態度をとることがあります。これは本当に容認できることではないんです。撤回については明確なルールが決められているはずなのに、彼らはそれでもしばしば言い訳を並べます。しかも、これは「まっとうな」ジャーナルの場合でさえ、ですよ。「ハゲタカ・ジャーナル」の連中なんてそもそもそんなことまったく気にかけすらしませんから。
おそらく「科学論文すべてを鵜呑みにすべきではない」ことの最大の例は、1998年に『The Lancet』に掲載された、ワクチンが自閉症を引き起こすと主張したアンドリュー・ウェイクフィールドらの論文でしょうか。あれはまったくのデタラメでした。
刑事捜査の結果、著者らが申告していない金銭的利益相反を抱え、データを捏造し、その過程で子どもに対して非倫理的で残酷な実験を行っていたことが明らかになったんです。編集部は当初から研究が偽物らしいと疑っており、査読者もデタラメだと指摘していましたが、それでも編集部は話題性と金になると分かっていて、それを掲載したんです。
そして、実際に注目と金は集まり、同時に現在まで人命を奪い続けているある種の反ワクチン運動の火付け役にもなりました。
『The Lancet』は当時も、そして今もなお、世界で最も信頼される医学誌(かもしれない)存在です。科学界がほぼ即座に不正と認めたにもかかわらず、完全撤回までに十二年を要したこの一本の論文で、彼らの手はどれほどの血に濡れたことか。
もし『The Lancet』ですら信頼できない存在なのだとしたら、我々は一体誰を信頼すべきなのでしょうか?
答えはこうです。「誰も信頼してはしけない、少なくとも無条件では」。全ての論文は批判的に読み、常に著者に利益相反がないかを考え、同じテーマの他の研究と結果を比較し、それがハゲタカ・ジャーナルではないことを必ず確かめてください。
──このような「ハゲタカ・ジャーナル」の問題はアカデミックの場で広く知られる問題なのでしょうか。
マタン・シェローミ 今では多くの国がこの問題を認識しはじめており、ようやく「ハゲタカ・ジャーナル」での発表を研究業績として数えないようになってきました。台湾では、私の所属する大学でもそれをテニュア(終身在職権)の審査に考慮しませんし、政府も助成金申請には認めません。これは当然のことでしょう。
しかし残念ながら、インド、中国、バングラデシュ、パキスタンなどの発展途上国ではまだ問題意識が薄く、研究者が時間とお金を浪費して価値のない雑誌に発表を続けているのが実情です。もしその土地の学術の場で「質より量」が重視されているのなら、「ハゲタカ・ジャーナル」は存続し、研究者はだまされ続けてしまうんです。
面白いことに、多くの「ハゲタカ・ジャーナル」は半自動的に運用されているので、実は掲載料を払わなくても自動的に論文を掲載してしまいます。もちろん何度もお金を要求してきますが、無視すればいいんです(実際そうすべきでしょう)。
結局、彼らは偽物の雑誌だってことです。すべてが自動化されていて、私のポケモン論文もすべて無償で掲載されますから。

この記事どう思う?
関連リンク





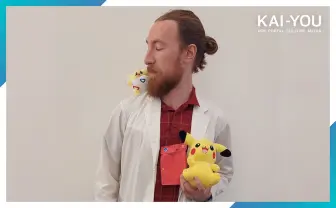
0件のコメント