フェイクニュースや陰謀論などの誤情報が社会を揺さぶる現代。
そうした現象を心理学や社会学の観点から整理した入門書『現代誤情報学入門』が、10月2日に日本評論社から刊行された。
人々が誤情報を信じてしまう認知バイアスや、陰謀論が拡散するメカニズムを解説しながら、対策の手がかりを提示している。
誤情報研究をリードする学者たちによる一冊『現代誤情報学入門』
原著は、ケンブリッジ大学の研究者として「誤情報の心理学」や「フェイクニュース対策」に取り組むジョン・ルーゼンビークさんとサンダー・ヴァン・ダー・リンダンさんによるもの。
翻訳は、研究者として本分野に関わってきた名古屋大学環境医学研究所助教の加納安彦さんが担当した。
コロナ禍やロシアのウクライナ侵攻、加速する誤情報の研究
コロナ禍において誤情報の拡散(インフォデミック)が世界を席巻したことは記憶に新しい。この状況を受け、近年では欧米を中心に誤情報の研究が加速している。
本書ではこの分野の第一人者が、科学の視点で誤情報を体系的に分析し、インターネットやSNSにおける実態や位置付けを取り上げる。どうすれば騙されないか、「社会」と「個人」の2つのレベルに分けて紹介する。
さらに、ロシアのウクライナ侵攻における情報戦など、現代的な事例も紹介。政策・教育・メディア実務に携わる読者にも示唆を与える構成となっている。
誤情報をめぐる議論、国内ではどうつながるか
誤情報/偽情報をめぐる研究は欧米で先行しているが、日本ではまだ体系的な入門書が少ない。
現代の情報環境について論じた書籍では、2024年に刊行された津田正太郎さんによる書籍『ネットはなぜいつも揉めているのか』などがある。
本書の刊行により、SNS時代のリテラシー教育やメディア政策に関する議論の土台を広げることが期待される。

この記事どう思う?
関連リンク

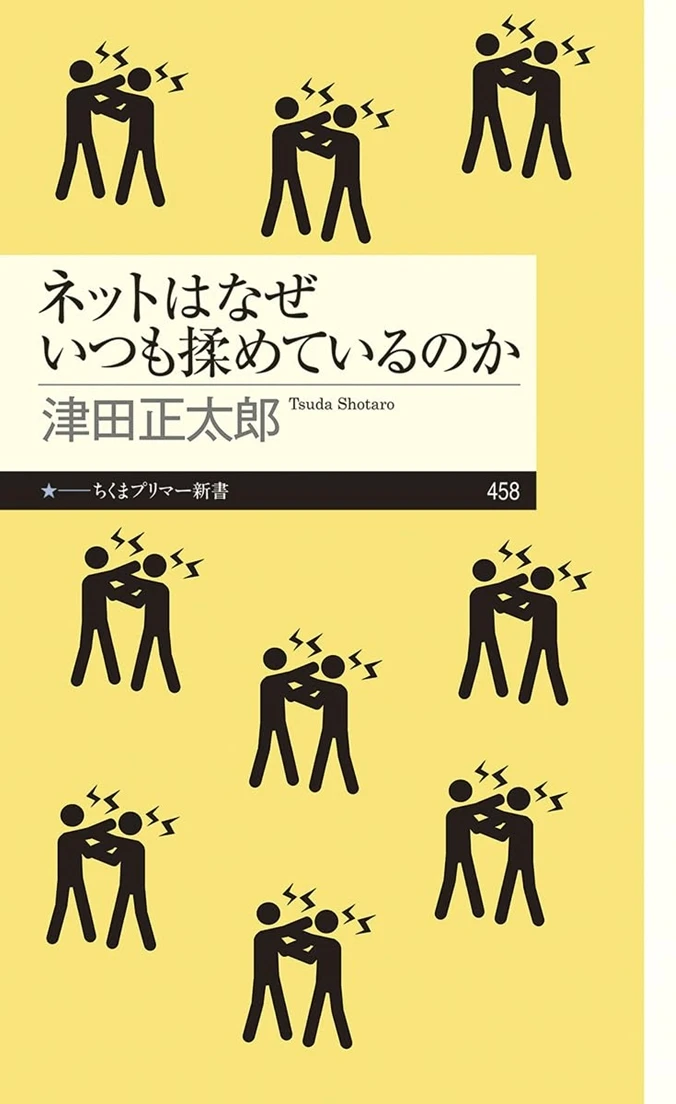

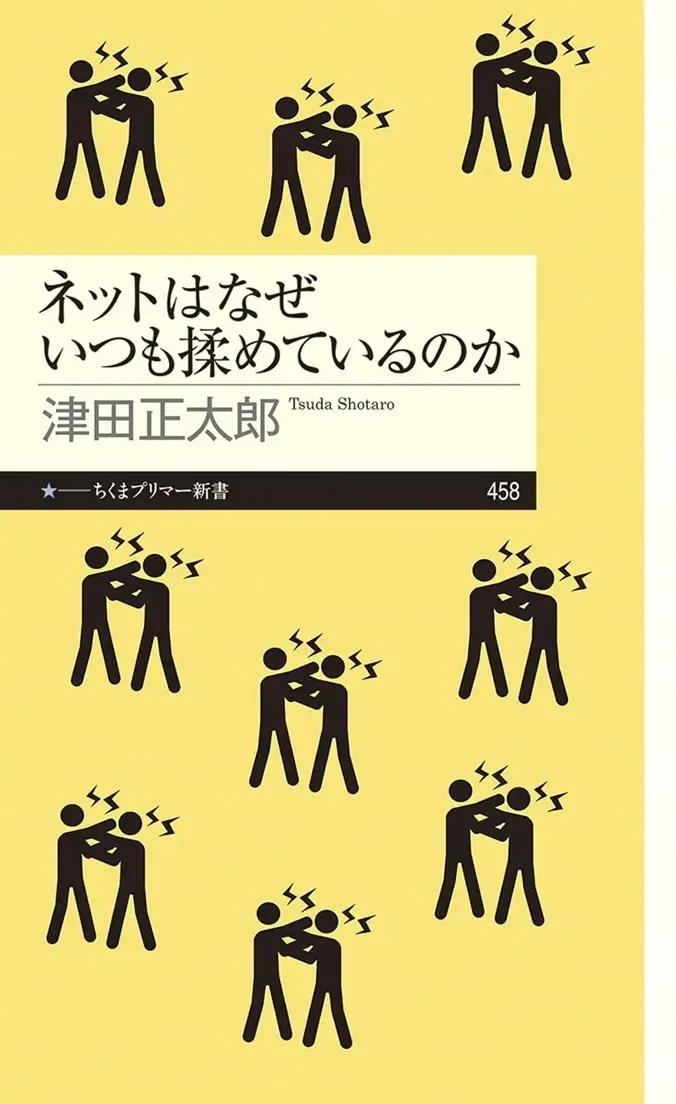
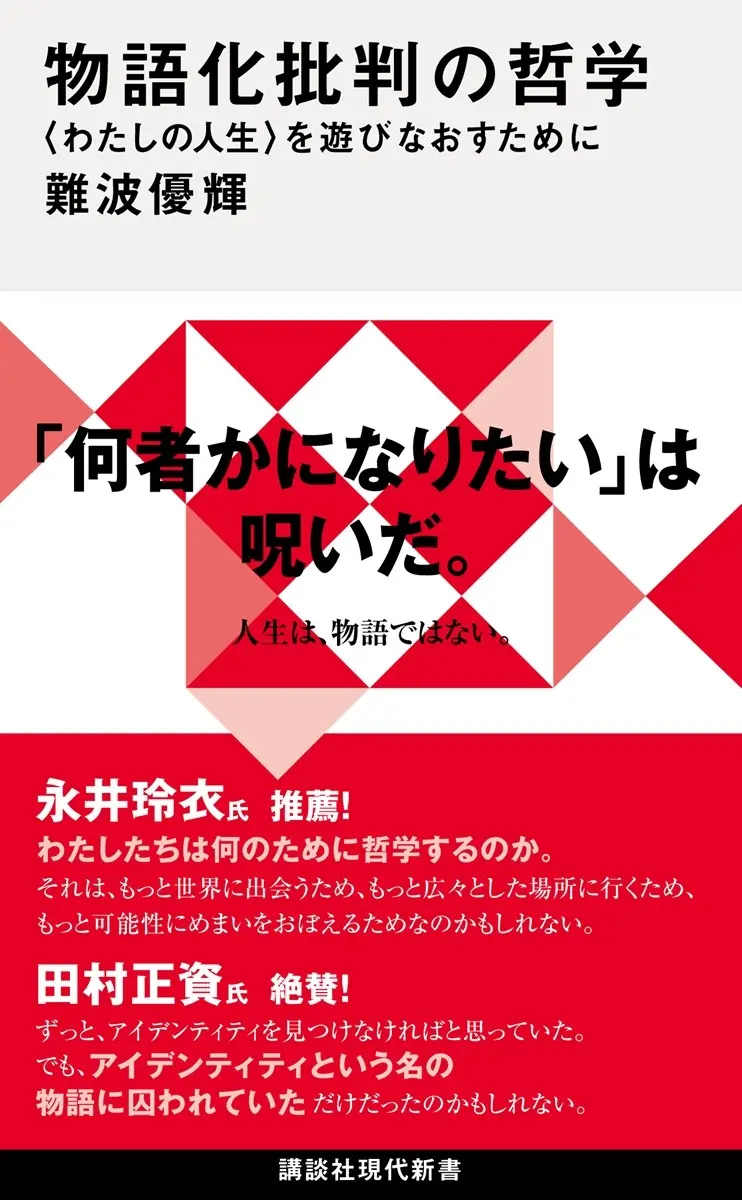
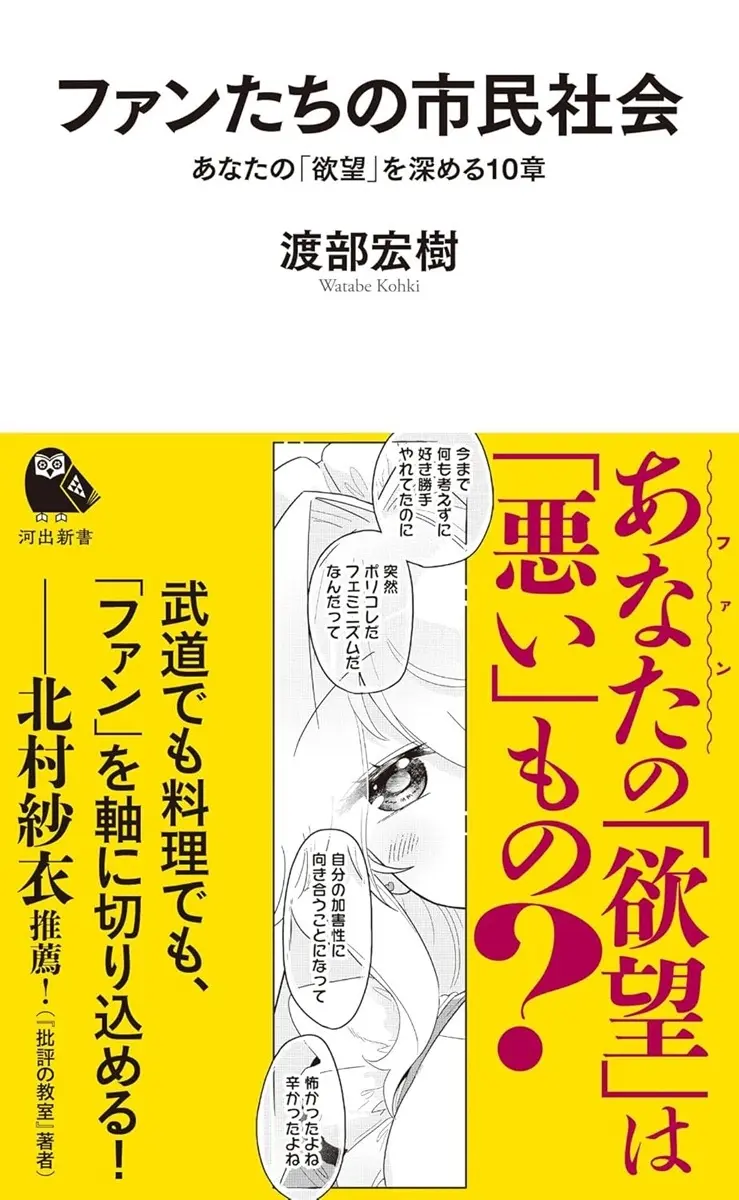
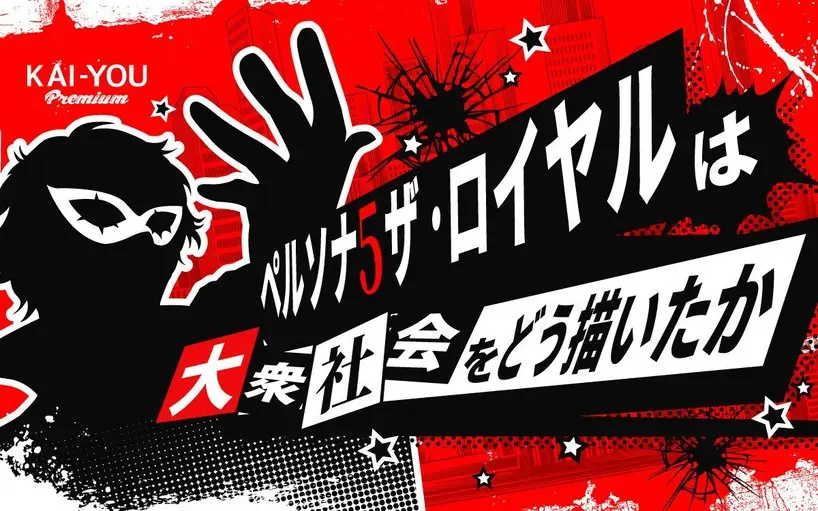

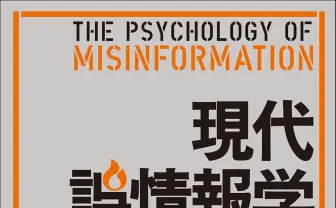
0件のコメント