日本経済新聞社が主催する短編小説の文学賞、第12回星新一賞(一般部門)で、最終選考の10作品まで残った「アルゴリズムの檻」が、作者の青野圭司さんのnoteで全文公開された(外部リンク)。
「アルゴリズムの檻」は、青野圭司さんが執筆の「ほぼ全てをAIに任せた」と明かしている作品。
星新一賞の一般部門に集まった1250作品の中で、最後まで選考に残った小説の大部分を、AIが書いていたことの衝撃は大きい。
あらすじ、登場人物もAIが考案した小説「アルゴリズムの檻」
「アルゴリズムの檻」は、2145年の東京を舞台にした短編小説。
人間の意思決定プロセスがすべて予測できるものだと判明し、人間の行動パターンを読む未来予測機械「ラプラス」が人々の生活に欠かせなくなった世界を描いている。
主人公は「ラプラス」の開発者の一人でありながら、その存在を受け入れられなかった元AI研究者の佐藤明。どこにいても「ラプラス」がついて回る生活から逃げるように、仮想世界「ノスタルジア」に入り浸る佐藤だが、ある日「ラプラス」の欠点に気づくことになる。
青野圭司さんは「アルゴリズムの檻」について、AIが書いた全文の一部を手直して完成させたとnoteに綴っている。
制作の8割はAIで行い「私の手が入ったのはせいぜい2割程度と言っていいでしょう」とのこと。作品のあらすじと登場人物もすべてAIが考えたという。
noteで公開されている作品を一読すれば、草案となった全文をAIが執筆したとは思えない完成度に驚くはずだ。
青野圭司さんは今後、AI小説の書き方をnoteで発表していくと告知しており、さっそく「星新一賞最終選考作品のプロンプト公開。AIでの小説執筆の2つのポイント」と題した有料記事を公開している(外部リンク)。
第12回「星新一賞」では優秀賞作品もAIを活用
星新一賞は、日本経済新聞社が理系的な発想力を問う短編小説を公募/表彰する文学賞。短編小説の一ジャンル「ショートショート」を広めた人物で、SF作家の星新一さんの名を冠している。
人間以外(人工知能など)の応募作品も受け付けているのが特徴だ。
第12回は、最終審査を菅浩江さん(SF作家)、大澤博隆さん(慶應義塾大学准教授/SFセンター所長)、北村みなみさん(イラストレーター/漫画作家)、尾形哲也さん(早稲田大学理工学術院教授)、土井隆雄さん(宇宙飛行士/京都大学特定教授)、矢野寿彦さん(日本経済新聞社 編集委員兼論説委員)が担当。
最終審査前の中間審査を鏡明さん(SF作家/評論家)、牧眞司さん(SF研究家/文芸評論家)、三村美衣さん(書評家)、橋本輝幸さん(書評家)が担当した。
結果は2月21日に公表。一般部門(対象制限なし)のグランプリは吉野玄冬さんの「ユウェンテルナ」、ジュニア部門(対象は中学生以下)のグランプリは小林宗太さんの「将来ドック」に決定した。受賞した9作品は日経新聞のWeb版で公開されている。
なお、一般部門の優秀賞(アマダ賞)を受賞した「最後の画家」はAIを活用した作品だ。作者の形霧燈さんはXで、「辞書的・検索的・相談的な用途」で、ChatGPTとClaudeを活用したと明かしている。

この記事どう思う?
関連リンク
1件のコメント

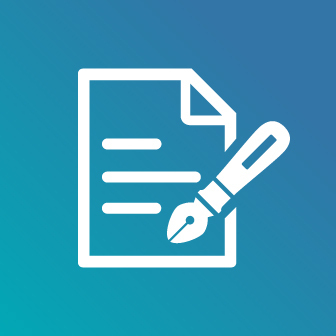

匿名ハッコウくん(ID:12045)
改めて、AIの凄さを知った。