前回までは宮崎駿、富野由悠季、押井守という戦後日本におけるアニメーションの巨匠たちの作品を振り返り、彼らが「母性」とどのように対峙したかを考えることによって、今後の現代社会のヒントを探ってきた。
最終回では、2016年に日本映画史にその名を刻みつけた作品『君の名は。』と『シン・ゴジラ』の差異から、今後の10年における「魅力的な主体像」の可能性を提示する。また、宇野常寛自身が今後どのような仕事を行なっていくかについても後半部で語られている。
刊行されている『母性のディストピア』(外部リンク)を片手に、是非とも最後まで読んでほしい。
取材/インタビューテキスト:碇本学 文:米村智水
『君の名は。』と『シン・ゴジラ』で描かれたもの
──『母性のディストピア』第6部になると「アトムの命題」に対する「ゴジラの命題」が出てきます。『君の名は。』を公開初日に観にいったら宇野さんに会って、観終わった後に作品について聞かせていただきましたね。宇野 なんだかんだといって、川村元気は怪物だよね。要するに、あれは震災を遠い地方で起こった過去の出来事だということにして、安全に泣けるラブストーリーの背景にしたってことでしょう? つまり、東北に対する後ろめたさで国民の心が一つになる、という仕掛け。「〜ではない」という否定性だったら今の日本は一つになれる。さすがだよね。川村元気は言葉の最良の意味で「悪いやつ」だと思った。
──ヒロインを救うために主人公が動く、ということでセカイ系に位置する作品だといえます。 宇野 うん、かつてのセカイ系のノウハウをうまく応用している。ただ、新海誠を『ほしのこえ』(外部リンク)から追い続けた人間としては、あのキモさが限りなくゼロに近づいていて、「口噛み酒」以外は新海誠の変態性が全部失われてしまっていることに物足りなさがあった。やっぱりさ、新海誠作品ってキモさがポイントじゃない? まったく共感できないし、たぶんそれが共感されないことを本人もわかっているんだけど、つい出てしまう自己憐憫と結びついたフェティッシュがね、もうどうしようもなくキモくてさ。そこが新海誠の個性だと思うのね。
僕が一番好きなのは『言の葉の庭』(外部リンク)なんだけど、足フェチの高校生が女教師に童貞を喰われるとかさ、安っぽいポルノみたいな話なんだけど、それを無理やりリリカルに美しく描いちゃうわけでしょ。雨の新宿御苑を背景に美しく描いてさ。あのグロテスクなものを無理やり美しいものとして描いているイタさが彼の味だと思うんだけどね。良くも悪くもさ。
──フェティッシュについての作品ですね。
宇野 しかし、『君の名は。』の中には新海誠のフェティッシュがほぼ削ぎ落とされている。
──宇野さんが好きな部分を全部抜いていくと大ヒットメーカーになってしまうと。
宇野 だからこそヒットしたのは当然間違いないよ。川村元気は同世代で一番優れていると僕は本当に思っている。結局誰も川村元気に勝てなかったのが2010年代。もちろん、勝ち負けの世界ではないけれど、この現実から目を逸らした話には意味はないと思う。
──そのコインの裏表にあるのが『シン・ゴジラ』ですよね。
宇野 僕は『シン・ゴジラ』の方が好きかな。理由は色々あるけれど、要するにあれは「なに言ってるんだよ、震災は終わってないだろ」という異議申し立てでしょ。 ──向き合うしかねえだろうみたいな。
宇野 この先俺たちはずっとこの震災=ゴジラと向き合っていくしかないんだよ、ふざけんな、という気持ちがある。
──みんな言葉には出してないけど、このくらいの年代ってみんなそういうことを感じたと思うんです。
宇野 かなり直接的だからさ。あれを観て、ゴジラ=震災や原発だってわからないやつはただのバカでしょ。ただ、非常にドメスティックな作品だから外国に行ってもわからないんだと思うんだよね。日本の政治が30年も停滞しているってことを知らないとあの脚本のアイロニーって伝わらないでしょ。
──ヘリに乗った内閣の政治家はみんな死んでしまって、意思決定する世代が下がるというのも皮肉でしかない。
宇野 ゴジラが自民党の幹部を全部ぶっ殺してくれたら構造改革できたのに……という話だよね。
──すごく日本的ですね。石原さとみが演じたカヨコ・アン・パタースンのキャラクターの問題も書かれていましたが?
宇野 あれは宮台真司さんの『シン・ゴジラ』批判を使って、後半の最後の吉本隆明に繋げるために引かせてもらったんだよ。僕は宮台さんと違って『シン・ゴジラ』はむしろドラマの希薄さがポイントだと思う。カヨコ・アン・パタースンという母化したアメリカが日本を救済する話だと宮台さんは読んでいるんだけど、僕はその物語が前面化せずに、逆に政治家同士のイチャイチャなボーイズラブ的なものが前面化していると思う。
──それを多くの人が楽しんでいましたね。
宇野 同じ現象を右から見るか左から見るかで、理解そのものは実はそれほど差はないと思うけどね。そして僕と宮台さんの視点の違いから論を展開して、現実に帰還するために吉本隆明論を挟んでいる。この本は最初に「もう現実のことなんか語ってられるか、俺は今からアニメという豊かな虚構の世界に完全に逃避する」っていう宣言からはじまる。しかし、最後にもう一回現実に帰る構造になっている。そのために吉本隆明論を挟んで現代社会論に回帰していく。要するに蝶番だね。
──そして、その先に『汎イメージ論』がある。最後の方には市場とゲームの話、共同幻想についてありました。
宇野 もう、この辺りから『汎イメージ論』(外部リンク)のプロローグに入ってるんだよね。
──『小説トリッパー』で連載されている『汎イメージ論』を読み返したんですが、たしかにほぼ同じですよね。
宇野 うん、文章は変わっているけど言っている内容がほぼ同じなのは同時期に書いていたから。『母性のディストピア』で戦後アニメーションの考察として書いたものを現代社会論に置き換えると『汎イメージ論』になっていく。
──『母性のディストピア』を読むとスムーズに『汎イメージ論』に移行できますし、興味を持ってもらえそうです。そして最後の方にも『ガンダムW』の話が出てきます。
宇野 国家というものは家族の延長戦にあるもの。時間的な永続が非常に大きな役割を果たしている。逆に市場というものは友愛的な広がりを持っているもので、空間的な広がりがないと成立しない。いま、世界と個人、公と私を結ぶものは「政治と文学」から「市場とゲーム」へと変わろうとしている。その中の新しい主体像を考えるときに何か、同じ対幻想でも核家族的なものではなく、兄弟姉妹なものを基盤にするほうがいいのではないかということを、吉本を批判的に読むことで展開しているんだよ。
それは言ってしまうと父になれなかったアムロとシャアからヒイロ・ユイへの転換なんだよね。やはり現時点では残念ながらヒイロとデュオはイチャついているだけ、つまり自分の問題を解決しているだけで、政治性というか、世界の問題にまったくコミットできていない。その現実というものが『新世紀エヴァンゲリオン』は文学しかないし、『シン・ゴジラ』は政治しかないという結果で、アイロニカルに表れている。
政治と文学は断絶するしかない。しかし市場とゲームは再統合されていく。この時代の主体像はアムロやシンジではなく、ヒイロ・ユイ的なものにならざるを得ない。しかしそのイメージはまだまだ未熟だ、という問題提起なんだよね。
「オタク」の失われた可能性と理想形
──最後の方で『シン・ゴジラ』のスクラップ&ビルドについて書かれていて、そして現実を変えるしかない、と言われています。今、現実を変えるしかないという話をするために虚構の話をしているわけですよね。宇野 一周戻って現実に帰ってくる。そのヒイロ・ユイ的な主体のアップデートとしての、かつてのオタクたちが持っていたポテンシャルの再評価を訴えて、終わるわけ。
──だから、行って帰ってくる構図なんですよね。
宇野 そう。一度虚構の世界に行って現実の世界に戻ってくる。過去の話をして現代の世界に帰ってくる。
──その構造があるからわかりやすく読みやすいのかもしれませんね。そして普段から宇野さんが言われているような「きちんと現実を見ろ」っていうのが伝わってきます。
宇野 日本という国は端的に、バブル以降からアップデートに失敗していてグローバル化と情報化に対応できていない。それに対応するためにスクラップ&ビルドというものの必要性とそこに適応した新しい主体、戦後日本的で矮小な父とは違った主体というものの確立ということについて考えて最後は終わっている。
──そこに昔の「オタク」的なものの力の話も出てきています。
宇野 「オタク」の失われた可能性。言ってしまえば当時の来るべき情報化社会に備えた新しい知識人のビジョンだよね。世界をイデオロギーや物語として捉えるのではなくて、情報の束として捉える。世界を物語としてではなくゲームとして捉えていく。
──『シン・ゴジラ』に出てくるキャラクターたちはそう描かれていました。
宇野 あれって僕は世代が近いからよくわかるんだけど、失われたオタクの可能性なわけなんだよ。
──宇野さんぐらいの世代ですね、確かに。
宇野 四半世紀前のオタクの理想像。もちろんそれは理想に過ぎなくて、実際には『シン・ゴジラ』でもアイロニーとして描かれていると思う。実際問題、オタクはネトウヨの温床の一つになってしまっている。映画で描かれたような成熟は訪れなかったわけ。
僕は小泉純一郎があと五年総理大臣をやっていて、堀江貴文が潰されなければ日本は変わっていたと本気で思っている。もちろん、お世辞にもそれで全部解決するなんて思わないよ。でも今よりはだいぶマシだったと思う。平成は本来そうあるべきだったし、平成という改革プロジェクトは成功すべきだったと思っている。左翼は激怒するだろうけど、僕はそう思っている。もちろん、あれをまたもう一回やってもうまくいかない。批判的な修正というものが行われた上でやらないと意味がないと思っている。この失われた2、30年を5、10年で挽回するしかない。
──しかし、東京オリンピックが良い方向に行くとは思えないですね。
宇野 その時に考えられる主体像というのが、実現しなかった理想形のオタク像なんだよね。比喩的にニュータイプという言葉が出てくるけど、それはもしかしたら、カリフォルニアン・イデオロギーに対しての日本からのポジティブな批判になるかもしれない。カリフォルニアン・イデオロギー自体は僕は不可避だと思うんだけど、かつて日本が日本車やアニメーションのような当時のアメリカナイズに対する肯定的な批判としての二次創作を通じて独自の価値を生んだように、魅力的な主体像を出せたらいいなと思っている。
基本的に西海岸の人たちの言っていることって非常に批判力が高いと思うんだけど、彼らはやはりどこかで技術楽観主義なんだよね。僕は工学知の優位自体は不可避だと思う。それは認めながらも、ポジティブに批判的でありたいと考えている。批判的技術主義でいくしかないと思うんだよ。かつての「オタク」たちの知性に、その萌芽を僕は見ているんだよね。
そもそも技術主義という考え方は諸刃の剣で、片方はイデオロギーに対して無垢で、免疫がない。
──取り込まれやすいということですか?
宇野 堀越二郎問題だよね。つまり技術オタクで、イデオロギーに対して無垢であるがゆえに零戦を作って軍国主義に加担してしまう。同じことが円谷英二にも言える。今で言うオタクの技術主義者である円谷は戦意高揚映画(『ハワイ・マレー沖海戦』)もつくればある意味での反戦映画(『ゴジラ』)もつくる。
しかし逆に言うと技術主義はイデオロギーに対しての免疫にもなり得る。それが円谷英二の息子、円谷一世代のスタッフであり、そこに集った若い脚本家たち。その結果、昭和の初期『ウルトラ』シリーズは左右のイデオロギーでは回収できない、まさにグロテスクな「怪獣」的なものになっている。
これからの僕たちは後者、つまり批判的技術主義でやっていくしかない。カリフォルニアン・イデオロギーが支配的になっていくのは明らかであって、だとすると僕たちがカリフォルニアン・イデオロギーの時代をより良く生きるための主体形成として、かつてのオタク的なものが抱えていた批判的技術主義の視点がポジティブに機能すればいいなと思ってる。かつてのオタクの理想≒ニュータイプというものがね。
──シリコンバレーから、というところで詳しく書かれていますね。
宇野 まあ、『汎イメージ論』の序章だよね。
『母性のディストピア』もう一つのエンディング
──僕は普段からわりと歩く方なのですが、『Pokémon GO』をやったことがなくて。宇野さんは『Ingress』をはじめたけど、散歩のやり方がわかるようになったから辞めたと言われていましたね。宇野 ジョン・ハンケの狙いは人を外に連れ出すのが目的だって前から言ってるからさ、碇本くんみたいに最初から外に出てる人にはいらないんだよ(笑)。
『Ingress』公式サイトより
宇野 いや、もともとジョン・ハンケは世界を情報化すればそれだけで充分だと思ってると思う。Googleマップを作った人だからね。Googleが世界を検索可能にすれば人々は単に街を歩くだけで自然の圧倒的な情報量や歴史の文脈に触れて成熟していく、というジョン・ハンケの考えがあって。その敷居を下げるためにゲーミフィケーションをかましてたのが『Ingress』なんだ。でも『Ingress』は都市部のアーリーアダプターしかやらなかったから、そこで考えついたのが『Pokémon GO』だった。
ジョン・ハンケというか、Googleは発想自体が環境管理的だから世界の環境さえ整えば、大半の人間はダメなまんまなんだけど、とりあえず底上げはされるし、優れた才能を持った人間が開花する確率も上げることができるという考えになる。
『Pokémon GO』がゲームとして面白くないって言ってるやつは基本バカだと思ってる。だってゲームが面白くないからこそ、世界を誰かと歩くことのほうが主体になり得るわけでしょう? それがハンケの狙いなんだよ。
──『汎イメージ論』にはチームラボの猪子寿之さんの話が出てきます。最後までの見通しはあるんですか?
宇野 うん、書きながら試行錯誤してるけど。ジョン・ハンケとは違う形で吉本隆明と猪子寿之という日本的な市場とゲームの関係性を書いてみたいんだよね。
宇野 いや、してない。これがはじめて。猪子さんの話に引っ掛けるとアナザーエンディングがあるんだよ。
──アナザーエンディングとは?
宇野 『母性のディストピア』の元になった集英社の「政治と文学の再設定」というWeb連載と、終章の「結びにかえて」の部分が一番違う。
──そうなんですか、本当に最後の部分ですよね?
宇野 「結びにかえて」は『汎イメージ論』のプロローグみたいになっているんだけど元々の連載では違っていて、書いているメッセージはそんなに変わらないんだけど、話題が違うんだよね。「映像の世紀」も「サブカルチャーの時代」も終わる。モニターの中の他人の物語を消費するのも終わって、自分の物語をスマホから発信する時代に既になっている。
だから終わったものを延命するよりも過ぎ去りし時代に培われた思想やノウハウを新しい時代に応用することの方が大事なんだってことを書いていて。その例として最後に、猪子寿之や落合陽一が出てきて、編集者の僕の仕事を紹介して終わるという構成だったわけ。
──そうなんですね、実際に『魔法の世紀』は「PLANETS」から出版されてますからね。
宇野 世界は虚構ではなく現実の方が優位な時代になっていて、ただその現実にかつての虚構が優位だった時代のノウハウを入れることによって現実が変わっていくというビジョンを示して終わる。読んでもらった人たちからは手前味噌だって言われたんだけど、僕はかなり気に入ってた。
虚構の中で培われたもので現実を変えようとする人たちがいっぱいいるんだという話をしていて、『カーデザインは未来を描く』の根津孝太さんだったり、「光学迷彩」の稲見昌彦さんや落合陽一の研究や猪子さんの活動について書いていて。でもあまりにも身内褒めに見えるし、宣伝みたいに見られるからやめたほうがいいって。
宇野 うん、今の吉本隆明論を媒介にして『汎イメージ論』のプロローグになっていくという終わり方になった。でも、連載版の終わり方も気に入ってたから、未だにどっちのエンディングが良かったのかわからない。
──そのアナザーエンディングをWebにアップしたら読みたいって人けっこういると思いますよ。ここに書かれている「境界がない」世界を作っていく人たちが猪子さんだったりするんですもんね。
宇野 単行本版のエンディングは理論に寄せたんだよね。最後に理論的な結論を書いて終わるよりも本当は編集者としてこういう仕事をしているという実例を書いて終わるほうが美しいと思ったんだよね。最後まで迷った部分なのだけど、おかげで『汎イメージ論』のプロローグとしてきちんと整理しながら書けたので、その後すぐに書いた『汎イメージ論』の第一回目はすごく気に入っている。
『PLANETS vol.10』そしてこれからの宇野常寛
宇野 次は『汎イメージ論』をこれから一年ぐらいかけて仕上げるつもり。単行本にするのはあと一年半ぐらいかかるかもしれないけどね。『汎イメージ論』を書きながら『PLANETS』の本誌とか作ったり、好きなことをしようかなと思っている。──『PLANETS」の次の本誌のイメージとかってあるんですか?
宇野 『PLANETS vol.10』は「2010年代の想像力」特集がいまのところ最有力。『ゼロ年代の想像力』から10年になるから、それもいいかなって。久しぶりに昔の『PLANETS」みたいなことをやろうかなと思ってる。 宇野 もう一つの候補が「戦争」特集。押井守の章で、ラジオと映画が20世紀前半の世界大戦の総力戦を生んだ全体主義の温床となった、20世紀後半の冷戦の時代ではテレビによって国民統合が行われていたけど衛星放送が現れて東側が崩壊していった、21世紀はインターネットとテロが結びついているって話をしたでしょう?
その延長線で「メディアと戦争」というテーマでやるというのを考えている。両方やりたいから、そのどちらかが先になるか後になるかは決まっていないけどね。あとひそかに『観光しない京都』という本を作りたいと考えています。
──宇野さんが京都に住んでいたことがあって、今も好きだから?
宇野 僕は京都に7年間住んでいたし、もう5年間ぐらい京都の大学に春学期は隔週で出張しているんだよね。京都ってさ、世界でも有数の観光地だから行くとどうしても観光してしまう。でも、京都って観光しなくてもけっこう楽しいんだよね。1ヘクタールあたりにおける文化度や歴史的文脈がかなり高いわけでしょ。
──集中してしまってますもんね。
宇野 すごく特殊な街なんだよ。人口の1割が学生だったり、昼間人口は観光客が多すぎて外国からも人が来るから、ものすごくハイブリッドになっている。
──戦争中に被害を受けていないのも大きいですね。
宇野 そうそう。そのせいで飲食店の展開も独特だったりする。東京の方が量はもちろん多いんだけど、京都の方が日本でも文化的な密度が濃いんだよね。そこでダラダラ過ごす。普通に朝起きてジョギングして、ご飯を食べて仕事して本読んで映画を観て寝る、みたいな。
ただ暮らすように京都で何日か過ごす、というのをこの数年やっていて、それが気持ちよくてね。これは何人かの共著で書こうと思っていて、写真メインのフォトッブックのような形にしようと考えている。何人かの書き手による「観光しない京都」の過ごし方の提案本になる予定なので、もう批評でもなんでもない。
──生活するっていう実質的ことをメインにするんですね。
宇野 うん、でもそれって伝えたいことは『汎イメージ論』と僕の中ではあまり変わらないんだけど、それを批評的な言語で切断的に「〜ではない」と語るのではなく「〜である」というイメージで提示するということを一回してみたくて。
しばらくの間、すごく嫌だったけど世の中のためにと思ってやったワイドショーの仕事とか、みんなバカにするかもしれないけど僕としてはがんばったつもりなんだよ。だから自分の人生の時間の使い方としてむこう1、2年間は好きなことをやりたいなと思っていて、前から試してみたいと思っていたことを思いっきりやってみたい。
──では、2020年ぐらいまでの間は宇野さんは自由にやっていくということですね。それは前から決めていたんですか?
宇野 良いタイミングだからね。このタイミングで『スッキリ!!』をクビになって、この10年間宿題だった『母性のディストピア』を出版できたということはなにか宿命のようなものを感じるわけ。
──余暇というか、そういう時間を過ごすことによって次に行くという感じでしょうか。
宇野 そうですね。今までやろうと思ったり挑戦しようと思っていたことがなかなか環境とかタイミングが合わずにできなかったことをやるタイミングなのかなって思ってるんだよね。
──しかし、京都の本っていうのは。しかも観光でもないんだっていう。
宇野 明後日の方向から攻めてくるでしょ。なんかさ、いかにも宇野がやりそうなことをやるのは面白くないし、僕が京都の本を出すなんて誰も思ってないだろうし。
──「PLANETS」vol.10の「2010年代の想像力」か「戦争特集」にまったく違う京都という日常があるのは宇野さんらしいのかもしれないですが楽しみです。
宇野 京都が好きなんだよ。単純に。時間はあまりかけたくないんだけど、僕が一生懸命働ければできる本なので。
──結局休めないんですね。
ほんと2015年ぐらいから意図的に自分のメンテナンスというか自分の頭をほぐして、視野を広げるためにも遊ぼうと思ってたんだけど、遊びすぎても自分はしっくりこないという気持ちがあった。少し仕事モードに戻そうと思っている。
──今後、会社のPLANETSもどんどん広げていく予定ですか?
宇野 そんなことはないけど、あと一回りとか二回りは大きくしたい。自分のやりたいことが充分やれる大きさやレベルに。つまり僕にとって会社は目的ではなく手段だからね。
しばらくは『汎イメージ論』と京都本かな。でも、『スッキリ!!』で僕を知ってくれた読者のために入門編みたいな社会論や文化論が一冊あってもいいかなと思ってる。
──新書だったり、軽めの本があってもいいですね。
宇野 ある出版社から中高生向けの本を書いてみないかと誘われていて、僕としては新しい挑戦なんだけど、なかなか構想が固まらなくてね。僕も来年40歳だし、若い子たちに向けてメッセージを送るような仕事もやってみてもいいと思うんだよね。
──人はそういう風になっていくんですね。
宇野 まあ、それは仕方ないことだよ。相対的にそういう位置に行っちゃおうとしてるんだなって。
──『10年代の想像力』よりも京都本の方が今読みたいです。
宇野 そうでしょ。そっち方が先に出るかもしれない。僕がさ、石破茂さんとの本をいきなり出したりAKBの本を出したらみんな驚いたと思うんだよね。最近そういう驚きがあまりない気がするわけ。
──そうですね、宇野さんはこれまでの仕事をアップデートしているという感じがします。
宇野 そういうフットワークの軽い宇野を取り戻そうと思ってね。そのための環境を整えるための数年間だったと思っています。
宇野常寛『母性のディストピア』連続インタビューを振り返る

この記事どう思う?
関連リンク
宇野
評論家
1978年生まれ。評論家。批評誌〈PLANETS〉編集長。著書に『ゼロ年代の想像力』(早川書房)、『リトル・ピープルの時代』(幻冬舎)、『日本文化の論点』(筑摩書房)、石破茂との対談『こんな日本をつくりたい』(太田出版)、『静かなる革命へのブループリント この国の未来をつくる7つの対話』(河出書房新社)など多数。企画・編集参加に「思想地図 vol.4」(NHK出版)、「朝日ジャーナル 日本破壊計画」(朝日新聞出版)など。京都精華大学ポピュラーカルチャー学部非常勤講師、立教大学兼任講師。

碇本
ライター
『水道橋博士のメルマ旬報』にて「碇のむきだし」、『週刊ポスト』にて「予告編妄想かわら版」連載中。

連載
評論家・宇野常寛の6年ぶりの単著『母性のディストピア』は、宮崎駿、富野由悠季、押井守という3人のアニメーション作家に焦点を当てている。 彼らはどのようにして「母性」と対峙したのか、その精神性は社会にどのような影響を与えたのか。 「政治と文学」から「市場とゲーム」へと価値観が移り変わっていく社会を示唆した本作をさらに深く読み解くための、超ロングインタビュー。





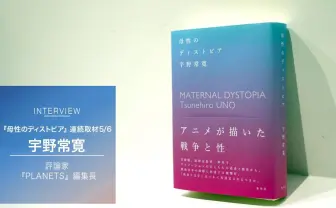

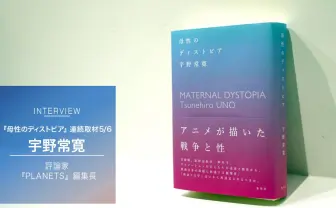





0件のコメント