第3回目となる今回は、いよいよ『母性のディストピア』本論でもメインモチーフとなる3人のアニメーション監督・宮崎駿、押井守、富野由悠季の3人へと細かく言及していく。
それぞれがアニメや映画という領域だけでなく、様々な表現や創作の分野に影響を与えた、日本を代表するクリエイターとも評価される3人だが、意外にも彼らに対する本格的な批評・論文は多くない。
今回は宮崎駿と富野由悠季の差異、そしてそれぞれがどのように「母性のディストピア」と対峙していったのかを作品論から解き明かしていく。
取材/インタビューテキスト:碇本学 文:米村智水
帰っていかないトトロの可能性
──今回取り上げている3人の作家について聞いていきたいのですが、先ほど話にあがった宮崎駿さんだと、宇野さんが一番好きな作品は何になるんでしょうか?宇野 『天空の城ラピュタ』は子供の頃の方が苦手で、今は一周りしてむしろ好きなんだよね。あれって表面的には典型的なボーイミーツガールの成長譚であるのだけど、同時にそういったものを断念している物語だよね。パズーは冒険を経て、シータを得ることでむしろ父の夢を継いで空を飛ぶことを諦めてしまったわけだからね。あとはもう、一生シータのスカートの中に隠れながら、飛んだつもりになって生きるしかないよ。あれって本にも書いたけれど戦後中流における矮小な父性そのものだからね。
だからあれ、ハッピーエンドのはずなのにあんなにもラストが物悲しいんだよ。一周りして『天空の城ラピュタ』も好きだし、でも実は一番好き、というかすごいと思うのは『となりのトトロ』だよね。 ──『となりのトトロ』のどこがすごいと思われますか?
宇野 『となりのトトロ』もそうだし原型の『パンダコパンダ』(外部リンク)もそうなんだけど、子供たちと妖怪が別れないでしょう? そこがいいと思うんだよ。普通こういうものは通過儀礼として描かれるわけだ。要するに子供の頃にしか見えない異界についての物語だよね。そういう異界を見る力を人は成熟すると失っていく。『この世界の片隅に』の主人公のすずちゃんは妖怪を見る力を性的な成熟を得る代わりに忘れてしまって日本的な母性になっていくよね。 ──『母性のディストピア』の最終章でも『この世界の片隅に』に触れられていましたね。
宇野 すずちゃんは異界を覗くという力を母性に置き換えることによって失う。この母性によって、彼女は結末で原爆孤児を自分の家族に受け入れて拡大家族を作っていく。それは戦後という偽りの時代の美徳で、一件すごく寛容でリベラルに見えるのだけど、実際は違うんだ、そんなものは自分のスカートの中と外を峻別して、収まりきらないものは排除して、外に出ていこうとする家族を縛り付ける排除と抑圧の支配するディストピアだっていうのがかつて押井守が高橋留美子批判をした『うる星やつら2 ビューティフル・ドリーマー』。まさに「母性のディストピア」そのものでだよ。 だから『この世界の片隅に』は『うる星やつら2 ビューティフル・ドリーマー』と『機動警察パトレイバー2 the Movie』のプロローグなんだよね。だから僕は第6部ですずちゃんが母になることなく異質なものと接するにはどうすればよかったのか、という話を展開している。要するに「母」になることなく、他者を子供ではなく他者のまま受け入れるにはどうしたらいいのかってこと。日常の中で妖怪を見る力を維持したまま成熟というか、社会を作っていくための想像力というのはあり得なかったのか、ということを論じている。
──異質なものが見えるという点で『となりのトトロ』と『世界の片隅に』が通じているわけですね。
宇野 そう、『となりのトトロ』はその意味ではあのままトロロが帰ってしまうと、サツキとメイはすずちゃんみたいな日本的な母になっていくしかない。矮小なマチズモと結託しながら家庭の内側と外側を峻別し空気を読まない人間を抹殺して石像にしていくしかないと思う。でも、あそこでトトロ帰らないじゃない。僕はトトロとサツキとメイがずっと一緒にいるってことが大事だと思うのね。
もちろん、宮﨑駿はそんなことは考えていない。実際に彼はその後、こうした戦後日本的「母性」への依存を強めていくからね。単にこのときは姉妹とトトロとの別れを描きたくなかったんだと思う。正しく、子供向けの作品としてあるためにね。でも、そのせいで結果的に射程の長い作品になっていると思う。
それって実は高橋留美子が56巻かけて描いた『犬夜叉』における、かごめのエンディングと近いものでもある。ずっとトロロという非日常、日常の中の非日常、日常の中の異界と常に共にあるということは何か日本的な母になることなく、日常という自分の世界に他者を織り込んでいくことができる。
──見方の方法として。
宇野 他者のまま調和していく、向き合っていくことが現代的なハイブリッドなコミュニティのビジョンとして見えるんだよね。結局、昭和の大家族的な家族の拡張性を取るか、トトロがサツキとメイのそばにずっと居続ける拡張性のどちらの方が魅力的かという話で、僕は後者だと思っている。この二つは近いんだけどそれは決定的に違っていて『この世界の片隅に』では、物語前半に座敷わらしとして登場した他者が最終的には子供に同質化されている。
僕はもうちょっと他者性というものが存在したままユルユル付き合っていくほうがいいと思っているし、日本的な想像力が持っていたポテンシャルはそういうところにあると思う。『となりのトトロ』ってあの終わらないところ、あの後トトロってお母さんたちが帰ってきても一緒にどんぐりとかを見てるわけなんだよ。あのビジョンの方が僕にとって魅力的なんだよね。ところが宮崎駿はそちらの方には行かずに『千と千尋の神隠し』は『となりのトトロ』の事実上セルフリメイクなんだけど、「行きて帰りし」の通過儀礼の物語になってしまっている。
──物語構造論をそのままやっているんですね。
宇野 それをやってしまった結果、日本的な想像力が持っていた日常の中に裂け目があって、生活の中で妖怪的な異質なものと共存するというビジョンを失ってしまった。トンネルの向こうの世界と現実の世界がきっぱり分かれてしまっている。でも、それが混在しているのが本来の日本的想像力なんだと僕は思う。
──宮崎駿が『となりのトトロ』でやろうとした可能性を引き継いでいる人っていないんですかね。
宇野 むしろそれをやってるのは明らかに『Pokémon GO』を作ったジョン・ハンケ。それは表面的なレベルかもしれないけど、Googleというのはスマートフォンを使って日常をハックしようとしているわけだよね。日常生活の中から自然に歴史とか自然といった世界の物語に自分の物語を接続していく。そこには日常の中に出現する日本的な妖怪が必要だったわけね、現時点ではあまり機能していないけど。
──確かにあれは非日常が日常と同化してますね。『Pokémon GO』が出てくるより先に僕たちはそういう風景をずっと見てきていたんですね。
宮崎駿の作家としての欺瞞
──『母性のディストピア』では、『もののけ姫』制作時の「言い訳」について書かれています。ジブリは基本的にずっと「言い訳」している集団ですし、実際に戦争を描くことも回避していたりします。宇野 いや、むしろ宮崎駿という作家は描けないんだと思う。まさに『風立ちぬ』の主人公の堀越二郎だよね。『風立ちぬ』で自分の自画像を堀越二郎に重ねて描いたわけなんだけど、決して自分は飛行機に乗ることはできないんだっていうある種の矮小な父性としての自意識が宮崎駿の魅力でもあり限界でもある。 ──しかも、その声を弟子筋である庵野秀明さんにやらせるっていう。わかりやすいのもどうかと思ったんですが。
宇野 あれはあれでいいんじゃない。そんなに評価している作品じゃないけど宮崎駿ぐらいになったらその創作姿勢というか自己解説そのものが作品になるということ。
──作家性のすごさということですか?
宇野 いや、宮崎駿ぐらいのクラスだったらあれが許されるし、いろいろ文句を言っているけど楽しめた作品ではあるよ。たださ、『母性のディストピア』にも書いたけどあの作品は大きな嘘をついている。「母性のディストピア」の安住というのは基本的には停滞と滅びしか生まない、かつての日本のような集団自決しか最終的には生まないってことを宮崎駿はわかってるんだよ。未来に何も残すことがないことも実はわかっていて、それを告白しているのにも関わらず二郎に対して妻の菜穂子に「生きて」と言わせたその罪は大きいと思う。
──それは国民的作家だからつかないといけない嘘だったんでしょうか?
宇野 国民的作家だからついた嘘というより、彼の自意識がつかせた嘘なんじゃないかな。自分の物語として語った瞬間に嘘をついてしまったという問題。あれを子供たちの物語にしたら正直なことを言えるわけだよ。実際に『崖の上のポニョ』ではかなり正直に言ってしまっているわけだし。このままこの国は何も残さずに戦後の思い出とともにゆるゆる終わっていく、みんな死んでいくんだけどそれでいいじゃないかっていうメッセージでもあるんだよね。でも、それを自分の物語にしたら言えなかった。だから本音ではこの国はこのまま「母性のディストピア」にまどろんだまま、戦後の思い出に浸ったままゆっくりと幸福に死んでいくのが一番良いんだと思ってるのに、自分に対してだけは「生きて」っていうのはどうなのよと僕は思うわけ。
──まあ、下の世代だったらそう言いますね。しかし、それを下の世代に言わせているのもすごいなと思います。
宇野 でも、それは彼の願望でしょ。
──最後の時にあのセリフに変えたっていう話がありますよね?
宇野 本当は「二郎さんこっちに来て」だったんだよ。そのままだったらはすごく正直だと思ったんだけど、あの改変でガラッと変わってしまった。僕は宮崎駿の作家としての欺瞞を感じたね、正直。あの一言がなかったらここまで批判しなかったと思う。
──その批判はすごく印象的でした。また、宮崎駿の作品は「少女の庇護」がないと男は飛べないということが書かれていて宮崎駿という作家性がよくわかりました。宮崎駿のモチーフとして「飛べる」か「飛べない」かということが重要だということは昔から認識されていましたか?
宇野 自分でもいつ頃からそう思いはじめていたのかわからないんだけど、この集英社版というのは「政治と文学の再設定」という断続的に9〜10年ぐらい続いていた連載の原稿が母体になっている。その後半が『母性のディストピア』になっているのだけど、宮崎駿論だけは初期の方で『コクリコ坂から』や『崖の上のポニョ』について書いている章がベースになっているので執筆したのは震災の前後だと思う。だからかなり早い時期に考えていたんだよ。
今回出版されたのは2017年だけど宮崎駿論とかは震災の前後とかに書いたものがベースになっているし、富野由悠季論の一部や押井守論もずっと温めてきたもので、昔『新潮』でやっていた同名の連載やイベントで話したものとか、大学の講義で使った資料とか、そういったものがベースになっている。最後の「結びにかえて」に出てくる「中間のもの」としてのインターネットというアイデアも、『リトル・ピープルの時代』とか『PLANETS vol.8』から取ってきてるので、ここに出ているアイデアはわりと何年も前から考えていたものだよね。
──それらを一つものとして繋いでいきながら一冊にまとめて書いていくのに時間がかかったということですね。『コクリコ坂から』や『崖の上のポニョ』を観ていないのですがグランマンマーレや母性という「海」がキーワードのものに包まれていくという話ですよね?
宇野 そうね、『コクリコ坂から』が長く書いてあって、宮崎駿の息子の宮崎吾郎が監督していて、本人は脚本しか書いてないけど『コクリコ坂から』はけっこう面白いというか、そこまで優れた作品ではないけど重要だと思っている。この作品は宮崎駿作品の中で一番男性性が後退している作品なわけね。
──登場人物が女性ばかりだと書かれていましたね。
宇野 その中で男性はただ種付けのためだけに定期的に丘に上がってくる存在みたいなものになっている。もし宮崎駿が「母性のディストピア」により肯定性を見出すとしたら、そういった女系社会の連鎖みたいなところに見出していたことは間違いがない。
『コクリコ坂から』はそういうところが何かグロテスクで「母性のディストピア」の先に宮崎駿が見出している肯定性のつもりではあったと思う。要するに、強い女性たち、グランマンマーレがグランマンマーレを生んでいくという系譜だよね。ただその強さというのは、結局闘争する男のためにおにぎりを作ってお掃除してくれるような母性でもあるわけだ。 宇野 別に女性だけの社会で完結することはしない。これはどういうことかっていうと、宮崎駿は『コクリコ坂から』まで来ると自分たちを安全に飛んだふりさせてくれる女性たちが世の中を回していってくれるのが一番良い、とどこかで考えているというのがよく出ている作品なんだよね。でもそういう母性に依存して、スカートの中を大空と錯覚しながら飛んだつもりになる生き方って、彼が嫌悪する資本主義のシステムに乗っかって何も考えずに生きる愚民大衆とどこが違うのか僕にはわからない。
宮崎駿と富野由悠季の差異
──もはや主体にはなりたくないという。母性の中でずっと飛んでいたいみたいなことなんですね。富野由悠季論のところでも出てきましたが『Vガンダム』でも主人公を巡って女性たちが戦うという話がありましたが、ほとんど同じようなものなんでしょうか?宇野 いや、それは宮崎駿と富野由悠季の違いというか。宮崎駿っていうのは自分を安心して飛ばせてくれる母性に対して圧倒的に賛美する。彼が賛美するものは自分たち男の子たちが安心して父になったつもりにさせてくれるような非常に良妻賢母的な喜んで犠牲になってくれる女性なんだよね。
富野由悠季はそこに圧倒的に惹かれながらも同時にそれを嫌悪しているところがあって、アムロもシャアも結局ララァに取り込まれて死んでしまう。『ハウルの動く城』だとソフィーがいるからこそハウルは飛べたっていう話になるのだけど、むしろ富野由悠季だとララァのせいでアムロとシャアは死んでしまうという話になる。
──アイロニカルな母性の重力の海に巻き込まれていくということですね。
宇野 富野由悠季自体はその母性に抗う術を見出せなかった。でも、その肥大した母性と矮小な父性との結託の欺瞞を徹底的に告発するカテジナ・ルースという女性を登場させてくることになる。 ──男には頼らないってことですか?
宇野 いや、実は頼ってる。だからあくまで卑しい存在として描かれることになる。「母性のディストピア」構造の欺瞞を告発する存在ではあるけれど、それは彼女自身が「母」であることを引き受けられない卑しい存在だから、とされる。なのでカテジナはむしろ作中に登場するショボい男のひとりと付き合うことになる。
ここに当時の富野由悠季の乗り上げた暗礁がある。「母」的なもののグロテスクな肥大には敏感なのだけど、同時にそれに途方もなく惹かれてもいる。なんてたって妊娠中の女性はその聖なる力で敵のニュータイプ能力すら無効化しちゃうくらいだからね。
──そして「母性のディストピア」に巻き込まれていくしかなくなる。
宇野 ロボットアニメなんて強くてカッコいい身体を得ることによって正義を実行して少女を得て父になるという男の子の成熟願望の塊だよ。問題はそれが機械の、偽物の身体であるってことなわけでさ。そのロボットアニメのヒロインが「男の子のロマンスになんで私が付き合わないといけないの」みたいなことを平気で言う。やはりカテジナというヒロインを描くことのできた富野由悠季はすさまじい。だからキスも同居もしてくれる『エヴァンゲリオン』のアスカとか、カテジナに比べたらかわいいもんだよね。
もう『エヴァンゲリオン』も一回りしてすごい好きになった作品なんだけど、極端なことを言うとアスカとかカテジナと比べてしまうとマジでヌルいよね。ただ富野由悠季はこのとき「母」になれない、ならないカテジナを卑しい存在として描き、「母」を体現するシャクティを聖なる存在として描いた。このとき既に富野由悠季自身は「母性のディストピア」に敗北していたんだよ。
『イデオン』『∀ガンダム』の先にあったもの
──では続いて富野さんの話を聞かせてもらいたいのですが、『海のトリトン』は最後に絶望しかなく、最初の頃から富野さんが子供向けのアニメーションでそれをあえてやっていたお話があります。『無敵超人ザンボット3』などもそういう作品でしたよね。宇野 あの頃の富野由悠季がやっていたことは要するに善悪の逆転なのだっていう評価が多いと思うんだよね。でも、今回僕は少し違う観点から考えていて、それはアニメにおける「リアリティ」とはなんなのかということ。要するに富野由悠季は『海のトリトン』や『無敵超人ザンボット3』で、子供向けのアニメで子供騙しの世界の記号的リアリズムが、いきなり現実のリアリズムとぶつかって崩壊するということをやったわけ。
富野由悠季は自然主義的なリアリズムと記号的リアリズムを宮崎駿のようにスムーズに往復させるのではなくぶつけるんだよね。そうすると記号的リアリズムの方が崩壊していく。崩壊することによって「アトムの命題(※)」というものを引き受けているんだよね。記号的リアリズムの方が崩壊することによって現実との接続というものが行われる。
※大塚英志が提唱した漫画論であり、著作。アトムのような「人の心を持っていても、人工(記号)の身体を持つがゆえに成長できない」という成長の不可能性を持ったキャラクターはいかにして成長し得るか、というテーマを指す。記号的/漫画的なリアリズムに通底する、戦後日本のフィクション全般における命題でもある。
──夢を見させるためではなく、現実と出会わせるためのものとして?
宇野 そこまで言うと単純化させすぎなんだけど、『海のトリトン』も『ザンボット3』もそうなんだけど主人公の少年というのが記号的リアリズムの中にいる限り「アトムの命題」的にいうとさ……
──成長することができないっていう問題が出てきてしまいますね。
宇野 そう。作品の中に矛盾を孕むということによって自然主義的なリアリズムと記号的リアリズムは普通だと同居できないんだけど、宮崎駿という作家はそれを無理やり同居させることによる破綻を魅力として提示してしまう。
富野由悠季が初期に取っていた手法だと、それを同居させることなく記号的リアリズムの世界にいきなり自然主義的なリアリズムを導入して破壊しちゃう。だいたいそれを最終回にやるので視聴者は愕然とするんだけど、その破綻によって見ている人間の成熟をもたらすという世界なんだよね。
──対して少年兵であるガンダムの物語は現実を描くというよりも虚構の世界を描きました。
宇野 『海のトリトン』『ザンボット3』と『機動戦士ガンダム』はかなり違っていると思っていて、前者の二つは記号的リアリズムの世界にいきなり自然主義的なリアリズムが侵入してきて、いろんなお約束だとか前提条件をぶっ壊して番組自体が崩壊していくんだけど、その事故性によって批判力を持ったんだよね。それに対して『ガンダム』というのはそうではなくて高畑勲的なリアリズムで完全に舞台設定をファンタジーにして虚構空間を作り上げるとそこに一個の現実を作れてしまう。
──偽史的な想像力ですね。
宇野 まさにそれで、完全な仮想現実を作り上げたのが『ガンダム』なわけね。しかし結果的に彼が作劇上の理由で導入したニュータイプという概念がそれを内側から壊していってしまう。ニュータイプというのは非常に現代的な概念で当時のオカルトブームや海の向こうのヒッピーカルチャーやニューエイジの影響を非常に受けている。要するにニュータイプというのは富野なりの60年代から70年代にかけての、同時代のユースカルチャーへの応答なんだよ。つまりここだけ「現実」が侵入してきてしまっている。
トリトンや神勝平は最終回で現実にぶち当たってしまうわけだけど、アムロにそれがないのは宇宙世紀という完全なる虚構の世界に生きていたから。でも後半に富野由悠季が苦し紛れに入れたニュータイプという設定によって『ガンダム』の世界に現実が侵入してしまうわけね。その結果、富野由悠季がニュータイプに引きずられてしまう。そうして生みの親によって宇宙世紀はどんどん破壊されていったのがその後の『ガンダム』シリーズなんだよ。
──そして『∀ガンダム』になって「黒歴史」というものを取り入れていくことになります。僕が唯一きちんと見たのが『∀ガンダム』なんです。
宇野 『∀ガンダム』いいよね。 ──はい、『母性のディストピア』にも書かれていますが、主人公のロラン・セアックはユニセックスな存在ですし、登場する∀ガンダム自体がシステムであり、今までだと父から与えられた仮の大人の身体というガンダムではないということに僕は全然違和感がなかったんです。
宇野 僕も『∀ガンダム』はすごいポテンシャルを秘めた作品だったと思う。本の中でも最重要な可能性の一つとして位置付けている。
──『伝説巨人イデオン』と『∀ガンダム』についてそう書かれています。
宇野 やっぱり富野由悠季って拡張身体としての日本のロボットアニメというジャンルを育てた人間なんだよね。特にモビルスーツという意匠によって幼児の成長願望の表れだった操縦する巨大なアニメロボットを、どちらかというと思春期の揺らぎや自意識の象徴として再定義したということにおいて富野由悠季は決定的な役割を果たしている。そして。それを自分で解体してもいる。
それがまさにシステムとしてのロボット。つまり「イデオン」であり「∀ガンダム」でもある。システムとしてのロボットとユニセックスな主人公というここからまったく新しいロボットアニメがはじまっていったはずなんだけどね。やっぱり『∀ガンダム』は設定が完璧、コンセプト完璧で素晴らしすぎてものすごいポテンシャルを感じる。ただ展開がそこまで面白くないよ、というのが正直ある。
なんで展開がつまらないかというと、敵の設定がうまくいっていないからだよね。ギム・ギンガナムってまあ、「黒歴史」というシステムの上で戯れていることが楽しくなっている人で、ネトウヨみたいなものだよ。要するにシステム自体への批判力を失っている矮小な存在だよね。ギム・ギンガナムがラスボスだと単にシステムに踊らされている可哀想な人をなだめるという話になってしまっていて、まあ、「そりゃそうだよね」という感じにしかならない。実はそれが『Gのレコンギスタ』まで続いている。だから敵を設定できないという問題がある。
──敵のいない世界というか。
宇野 「敵のいない世界」をちゃんと引き受けたわけでもないでしょう? 僕が富野由悠季論の最後で書いたのはまさにその問題で、「イデオン」というシステムを乗り越えられない人間の、自ら生み出したシステムに翻弄される人類の業という問題だよね。そこに向きあわないとダメなんだと思う。
ロランというユニセクシャルな存在が、あるいは月の女王ディアナやキエル・ハイムという母の呪縛から逃れている新しいヒロインたちがその「∀ガンダム」や「黒歴史」というシステムにいかに対峙していくかということを描くべきだったのに、そこが追求されずにシステムに踊らされる可哀想な人をどうかしようという話になってしまったのが非常に残念だった。
──『∀ガンダム』はガンダムなのに世界名作劇場みたいな感じでやっていると言われて興味を持って見たんですよね。
宇野 やっぱりあれいいよね。でも、富野さんがうまく転がせきれなかった部分もある。
──自分の作ったものを信じきれていない?
宇野 そうではなくて、富野由悠季の何が一番すごいかっていうと想像力や着想だと思う。例えばニュータイプとかさ、最初は当時のオカルトブームの要素を入れようと思っただけなんだろうけど凡庸な作家だったらテレキネスだとかテレポーテーションをやるよね。でも実際は、空間を超えて相手の存在を認識するということをやっている。
──今の情報化社会みたいですね。
宇野 はっきり言ってしまえば現在のインターネットだよ。そういう超能力のビジョンを出したことがすごいと思うし、まさにインターネットを予見しているみたいでしょ。さらにすごいことには『Ζガンダム』以降、空間を超えて人の意識と意識が直接繋がってしまうと人はろくなことにならないってことまで描いてしまっていた。まさに『伝説巨人イデオン』や『Ζガンダム』はそういう話なんだよ。一言で言えば、空間を超えて意思と意思が直接つながるようになると人類は滅ぶという話。今の情報社会に対して、ものすごく説得力があるわけ。
──人々が繋がってしまうとただ怒りや負の感情が拡散されてしまってさらに壁ができてしまって、トランプ大統領も生まれてくるのは必然だと。
宇野 でしょ。富野由悠季という作家は、予言性ともいうか天才的な着想が圧倒的に優れていると思う。そして自分の天才的な想像力にもはや監督としての、集団制作のリーダーとしての自分自身がついていけずに作品が壊れてしまうというか、展開や物語が破綻するということをずっと繰り返している。
『∀ガンダム』もそうだと思うんだよね。「黒歴史」という圧倒的なアイデアとユニセクシャルな主人公──「イデオン」のアップデートしてのシステムとしてのガンダムというすべてが素晴らしいアイデアなんだけど、本人がそのアイデアについていけずに物語を作れていない。
──天才でしかないという。
宇野 富野由悠季は自分のアイデアや想像力に自分がついていけず破綻しているというのが理解できる作家で、『∀ガンダム』はその代表格だよね。
──ニュータイプや黒歴史という単語ももはや一般化してますからね。
宇野 「スタンバってる」という表現も実はブライト艦長が使い出したという説もあるしね(笑)。大学の授業で何度か富野由悠季についてやったことがあるんだけど、黒歴史ってガンダム用語なんだよって教えたらみんな愕然とするもんね。
──ええ、今の大学生が物心がついた頃には「黒歴史」という言葉が普通に使われていたんですもんね。
宇野 でも富野由悠季が作ったんだということを誰もわかっていない。
──『∀ガンダム』を見ていたら世の中でも普通に使われるようになったんだなって感じでしたけど、一般の人だったら例えばGACKTがMALICE MIZER時代のことを黒歴史だと語ったのをYahoo!ニュースで記事になったことから一般的に広まっていった感じかもしれないです。ガンダムからというイメージはないかもしれないですね。
宇野 ないね。だから何が言いたいかというと富野由悠季は着想が一番すごい作家だということなんだよね。
──『∀ガンダム』で敵をどう描くかという問題が『ガンダム Gのレコンギスタ』まで続いていくことにもなる。最後の部分で宇野さんが書かれていますが富野さんには新作を作って欲しいとありますが、それはやはり『伝説巨人イデオン』の最新版のアップデートということですよね?
宇野 『ガンダム Gのレコンギスタ』のオフィシャルブックの時に富野さんと長時間対談させてもらったんだけど、あの時に戦後ロボットアニメはもう終わっているんだという話をずっと二人でしていた。つまり富野由悠季は自分で作ったものを自分で終わらせてしまっている作家なんだよ。
『逆襲のシャア』も『Vガンダム』も少年性の表現としてのロボットアニメという限界というのも基本的には露呈してしまっている。『エヴァンゲリオン』でシンジくんがエヴァに乗りたくないって言うのは基本的には『逆襲のシャア』や『Vガンダム』があるせいだよ。だから富野由悠季は少年性の表現ではない新しいロボットアニメを──かと言ってアメリカ的な人工知能みたいなものではないまったく違うロボットアニメを作るしかない。
その手がかりや着想はすでに『イデオン』の段階で出しているわけだよね。『イデオン』と『∀ガンダム』の系譜で富野由悠季はもう一本作るしかないと僕は思っていて、本人にも何度も伝えている。そういう作品を作ってケリをつけて欲しいなと僕は思っています。
宇野常寛『母性のディストピア』連続インタビュー

この記事どう思う?
宇野
評論家
1978年生まれ。評論家。批評誌〈PLANETS〉編集長。著書に『ゼロ年代の想像力』(早川書房)、『リトル・ピープルの時代』(幻冬舎)、『日本文化の論点』(筑摩書房)、石破茂との対談『こんな日本をつくりたい』(太田出版)、『静かなる革命へのブループリント この国の未来をつくる7つの対話』(河出書房新社)など多数。企画・編集参加に「思想地図 vol.4」(NHK出版)、「朝日ジャーナル 日本破壊計画」(朝日新聞出版)など。京都精華大学ポピュラーカルチャー学部非常勤講師、立教大学兼任講師。

碇本
ライター
『水道橋博士のメルマ旬報』にて「碇のむきだし」、『週刊ポスト』にて「予告編妄想かわら版」連載中。

連載
評論家・宇野常寛の6年ぶりの単著『母性のディストピア』は、宮崎駿、富野由悠季、押井守という3人のアニメーション作家に焦点を当てている。 彼らはどのようにして「母性」と対峙したのか、その精神性は社会にどのような影響を与えたのか。 「政治と文学」から「市場とゲーム」へと価値観が移り変わっていく社会を示唆した本作をさらに深く読み解くための、超ロングインタビュー。
2件のコメント





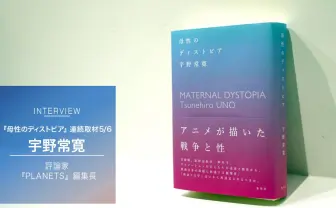




匿名ハッコウくん(ID:2881)
河合隼雄「母系社会 日本の病理」
この著者の生きた時代ブームになっていたろ。わかってて名を出さないか?
「鬼子母神」という単語から、「日本特有」過保護の成人社会的引き籠りまで言及できるが、この人物は『それっぽいモノ』が出来て満足なんだろう。
「雰囲気」イケメン、意識高い『系』。
実態もない。クリエイターの事積への落書きで中身の無いマンガ文を書いてキモチヨくなってる倭人特有のいつもの【エセ】人文ヤローだな。倭人のネット衆愚に対し、「北米特有の『反"知識層"主義』」を中身も見ずに平気で言葉の響きに酔いしれて当てはめそうだ。
カタカナ語厨、リアル中二病患者相応に。
何様だ?w 中身もない分際でデカいツラをしたいならご自分のお考えな『完璧な』脚本でも製品でも出してみるといい。
大塚英志氏はその方面でも取り組んでたな。
こんな半端極まる役に立たん妄想メモで、よく小林秀雄氏と同じ名義を名乗れるな。
飯を喰うには苦労しなさそうだ。咎めるほどの民度もここにはないもんで。いいシタリ顔だ。(笑)
匿名ハッコウくん(ID:2695)
なんだ?こいつ??
自分に酔っている。