しかし現在では、テレビやラジオといったマスメディアで政治や国際問題について語る機会も多く、そのパブリックイメージとして「コメンテーター」という立場で彼を知る人も多いだろう。だが、宇野常寛の出発点は自身が主宰をつとめる批評ユニット・第二次惑星開発委員会であり、編集長をつとめる批評誌『PLANETS』であり、確かな知性と熱量に裏打ちされた「批評」であることは間違いない。
そんな宇野常寛が、宮崎駿、富野由悠季、押井守といった日本アニメーションの巨匠たちを大きく取り上げた評論『母性のディストピア』(集英社)を、10月26日に刊行した。
宇野常寛『母性のディストピア』(集英社)
取材/インタビューテキスト:碇本学 文:米村智水
父性と母性の間にある「中間のもの」
──目を引く装丁の新刊『母性のディストピア』ですが、表紙の装丁デザインは上の部分が水色から下の部分に向かって紫に近いピンクにグラデーションしていくものになっていて、本書の内容と非常にリンクしていると思うのですが、これは宇野さんからの装丁デザインの指定などあったのでしょうか?宇野 『母性のディストピア』の装丁は『PLANETS』でもデザインをしてくれているデザイナーの池田明季哉くんです。9案ぐらい出してもらったのだけど、その中で彼が最初に出してきてくれたA案でこれが一番のド本命だと出してきてくれたのが今回の表紙です。僕もこれが良いと思った。なぜかというと、一番この本のコンセプトを表現していると思ったから。
デビュー作『ゼロ年代の想像力』(外部リンク)は真っ白なところにタイトルが入っていて、真っ白なキャンパスにサブカル批評の新しい地表を切り開くんだという気負いの表現だったんですよね。 2冊目『リトル・ピープルの時代』(外部リンク)は、鈴木成一さんが自己解説しているけれど哀愁を帯びた仮面ライダーを本と読者の間に置く、というコンセプト。あれは「なぜ仮面ライダーなのか」という部分がキモだからね。 ──たしかに『リトル・ピープルの時代』は表紙の仮面ライダーがものすごくインパクトがありました。
宇野 でしょ。今回の『母性のディストピア』は、最後に「結びに代えて」と題したエッセイが入っている。ここだけ意図的に視点も文体も変えているのだけど、このエッセイは実は「中間のもの」についての話なんです。つまり政治と文学、公と私、世界と個人がきっぱりと切断されていて、それをどう接続していくかというのが近代的な成熟の問題だけど、この二項とは同時に虚構と現実、あの世とこの世のことでもある。
日本はそもそもそれらの二つというものの境界線が曖昧であって虚実の皮膜が曖昧になっていて近代化がうまくいってない。その曖昧さというものを母権的なものとして日本の表現者たちや作家たちは表現してきた。だからそのイメージみたいなものを池田くんなりに表現したと僕は考えていて、一発で気に入った。いろんな人に見せて意見を聞いたらほとんどの人間が他のB案の方を支持したんだよね。
──そのB案というのは具体的にどういうデザインだったんでしょうか?
宇野 B案というのは、これは僕の考えた案で『ヱヴァンゲリヲン新劇場版』の赤い海の元になっているウクライナのアゾフ海という所があるんだけど、庵野秀明はその赤い海に日本のアニメーションが培ってきた母性のディストピア的なイメージを見ていたと思っていて、それを使うとわかりやすくていいんじゃないかと思って提案した。しかし、そのものズバリすぎて安易な寓意かなと思ったけどみんなに意見を聞いたら圧倒的にそれが支持されたわけ。でもそのB案は僕の指定とラフ通りに上がってきた感じだったので面白みを感じなかった。
──宇野さんの想像力の範囲内だったという。
宇野 そう。でも、デザイナーの池田くんの発想のほうが面白いと思ったわけ。で、どこか抽象化されているA案の方がいいと思ってこちらにしました。
──僕は富野さんの章に書かれている父になれないアムロとシャアという二つの可能性についての部分を思い出して、表紙のグラデーションが地球と宇宙の狭間の大気圏のように見えました。青と赤というのも父性と母性の間にある「中間のもの」という今回書かれている重要な部分と重なるのでピッタリだと思いました。
新刊『母性のディストピア』は現在『小説トリッパー』で連載されている『汎イメージ論 中間のものたちと秩序なきピースのゆくえ』(外部リンク)にも繋がっていますよね。
宇野 そう、まさにこの本の「結びにかえて」でエピローグ的に書いている「中間のもの」についてというエッセイは『汎イメージ論』の一回目のプロトタイプです。『母性のディストピア』とは戦後アニメーションや戦後のオタク文化の想像力の根底にある母権的な包摂のことであって、その包摂は排除と表裏一体なわけです。この母権的な排除の論理と日本社会性とオタク文化というものを繋いで論じるというアイデアは『ゼロ年代の想像力』の頃からありました。
──では、初期の頃にはすでにイメージされてたんですね。
宇野 『ゼロ年代の想像力』には「肥大する母性のディストピア(空転するマチズモと高橋留美子の「重力」)」という章があります。それとこの本の原型となった『新潮』版の連載のものを僕がアップデートしているものがあって、そこに『PLANETS vol.8』(外部リンク)ぐらいから提案していた市民社会や地域共同体という中間のものを解体すると言われているグローバリゼーションとその背景にある情報化というものをむしろ「中間のもの」の再構成として捉え直すということをしようと思っていた。
たとえば『PLANETS vol.8』では、こんな議論を展開している。20世紀という「映像の世紀」というのは映画という意識高い市民を想定した能動的なメディアと、テレビという受動的な愚民を対象とするメディアを並走させることで成り立っていた。同じことが民主主義にも言えて、上院と下院、熟議とポピュリズムでバランスをとる、ってことをやっていた。だからこそその中間的な存在としてのインターネットのような新しいメディアを活用しよう、というアイデアを展開していたわけです。こうしたメディア論的な議論と僕が従来抱えていた「母性のディストピア」という問題意識を接続させるということを今回やっています。
それが今回の本で、だから最後はその「中間のもの」が具体的にどういう形をとりうるのかということを僕なりに考察しているんですよ。続く『汎イメージ論』(外部リンク)はその延長線上の議論をしていて、日本でジョン・ハンケの仕事に匹敵するような、中間的なものの再編成のような可能性が出てくるのかというのが『汎イメージ論』で書こうとしていることで、それが本作とそのまま繋がっています。
変化しないテレビ、変貌したネット 絶望と怒りが書かせた『母性のディストピア』
──はい、この『汎イメージ論』の前史でもあり、これに至るために書かないといけなかった戦後論として書かれています。どちらにも吉本隆明が出てくることも印象的です。今回たまたまですが、選挙後に発売になりました。選挙後に宇野さんはリベラルもどきの人から絡まれたりしてましたが。宇野 あれ、悲しくなるよね。ツイッターでも書いたけど僕は小選挙区は立憲民主党に入れてるくらいだし、留保はつけているけど枝野代表にもエールを送っている。
──はい、枝野さんに期待しているとは書かれてました。
宇野常寛さん
まず前提としてこの立民党ブームを昔の左翼の再興の契機にしたくて仕方がない、というのがあって、少しでもその路線に批判的な僕はまず潰しておきたい、ってことなんだろうね。僕は立民党は中道路線にするほうがいいと思うのだけど、そんな意見を述べる事自体がもう、一部の支持者たちには許せないみたいで……。0か1か、敵か味方かでしか思考できない。僕はリベラルな人たちって、ああ、こうやって自分たちから味方を減らしていったんだろうな、としか思わなかった。
──ツイッターが顕著ですが、条件反射的に書けばいいみたいな人がたくさんいて、やはりインターネットはテレビ的なものでしかなくなってしまいました。
宇野 そう、インターネットは第二のテレビになり、誰もがテレビのコメンテーターになった。20年前のインターネットは、テレビワイドショーやバラエティに顕著なマジョリティによる「いじめ」エンターテインメントの力学が機能しない、自由な場所だった。けれど、それがブログ論壇が形成されたころからおかしくなっていって、いまではすっかりテレビワイドショーの補完装置になっている。週に1度、生贄を選んでみんなでそいつに石を投げて「スッキリ」する場になっている。
だから僕は2年半前に、自分がテレビに出て、この陰湿な世界の中心から「こんなことは間違っている」と指摘してやろうと思ったんだよ。最終的には政治的な発言でクビになったけどね。
──正しい態度だと思いました。
宇野 そう言ってもらえると嬉しいんだけどね。ただ、状況は確実に悪化していると思う。『PLANETS』vol.8を編集していた頃にはまだインターネットの未来が信じられていてさ、「アラブの春」の結果がここまでひどいことになるとは見えていなかったからね。
──そうですね。
宇野 日本のインターネットやツイッターの言論空間もいまほどグダグダになっていなくて、ニコニコ動画もいい意味でいまより存在感を放って、インターネットを中心に新しい民意が生まれて、そこから新しい政治が生まれてくるという機運がまだあった。
さっき僕は市民と動物みたいな二項対立ではなく、その間を繋ぐ中間のものをインターネットが作らないといけないし、再編成しないといけないという話をしたと思うんだけれど、時代は下からの全体主義じゃないけど、どんどん逆の方に行ってしまいインターネットが第二のテレビになってしまった。インターネットは本当にテレビ的な卑しさを補完するだけの装置というものになっていて、それをどうにしかしたいと乗り込んだ自分自身がテレビでこの2年間消耗してしまった。
だから、はっきり言ってしまえば怒りだよね、絶望というかそういうものが書かせた本ではあるんだよね。
収録されなかった高橋留美子論の行方
──今回書籍になった形では押井守論の所に高橋留美子さんの話も入っていますが、『新潮』連載時の時には高橋留美子を論じた章がたしかありましたよね?宇野 それは単純にかなり物理的な理由が大きくて、ここに高橋留美子論を入れたらいつ出るんだっていうことになっちゃうでしょ。今の時点で40万文字あるんだけど高橋留美子論を入れたらそれだけで一冊分ぐらい、10万文字以上増えてしまう。
──700ページ超えになるぐらいになってしまいますね。
宇野 うん。きっとあと1年以上かかる。僕は高橋留美子についてまとまった評論を書いた数少ない人間だけど、ただそれを一冊にまとめるのはまた別の機会にチャレンジしようと思っています。今回は後的な家長崩れの、矮小的な父の自意識の問題に集中した方がいいかなと思って男性作家で統一しました。
──それで押井さんが高橋さんを批判しているというポジションでその章の中に入れたのでしょうか?
宇野 実際問題、この本のタイトルになっている「母性のディストピア』とはいうメカニズムは宮崎駿、富野由悠季、押井守と言った戦後のアニメ作家だけじゃなくても明治、大正の文学者まで遡れば近代的な市民、「父」になれないという自意識を抱えた男性の依存先として母のような妻、母として機能する妻としての女性性みたいなものというのが昔から必要とされてきた。
彼らの自分たちはほんとうの「父」になれない、だからお母さんのスカートの中でだけ「父」になった気分を味わいたい、という欲望と、そんな男たちを「自分の胎内から出て行かないで」と所有する、そうすることで自分の箱庭を守りたいという「母」的な欲望との結託がこの本で僕が主張している『母性のディストピア』で、それを最も体現しているのは当然、その高橋留美子なんだよね。そのことをもっと深掘りしないと本当は『母性のディストピア』は完結しないんだけど、それはそれで高橋留美子に関しては扱うと全然違う問題系を大量に扱わないといけなくなって時間的にも分量的にも入りきらなくなってしまうので別の本にした方がいいなと判断して切り離した。
本当は『新潮』の連載の時に書いていた『犬夜叉』論をアップデートして展開したかったんだけどね。あれは一言で言うと高橋留美子なりに新境地に行こうとしていた作品だったと思う。普通に考えたらやはり母性を体現する存在の桔梗がヒロインで犬夜叉という少年性を抱えた存在の物語だよね。
桔梗に見る、高橋留美子の本音とは?
──たしか犬夜叉って年を取らない存在でしたよね。宇野 そう、山口勝平以外声を当てられないような少年性のカタマリのような存在だよね。そんな犬夜叉とヒロインのかごめが二人がパートナーになって、最終的には夫婦になっていく。
これ、以前の高橋留美子なら桔梗がヒロインだったと思う。ラムちゃんや音無響子のような髪が長くて、嫉妬深いヒロインの直系は桔梗なんだよ。歳を取らないヒロインの桔梗と、永遠の少年・犬夜叉が永遠に先延ばしされる奈落との「いつか行われる最終決戦」に向かって楽しく旅を続ける、そんな作品になっていたと思う。
でも、実際に描かれた『犬夜叉』は違う。かごめという、普通に進級して歳を取るヒロインが、戦国時代というけどまあ、事実上はファンタジーの世界にワープして桔梗の代わりに犬夜叉とパートナーになる。高橋留美子は自分がこれまで描いてきた世界の限界というものをよくわかっていて、だから桔梗を殺してかごめをヒロインにした。このかごめというのは、まあ、言ってみれば読者の分身だよね。
これまでの高橋留美子作品のヒロインとはだいぶ違っていて、彼女が描いてきた「終わりなき日常」のファンタジーを必要とする現代人の象徴でしょう? だから高校に通いながらときどき戦国時代で冒険する。まるでディズニーランドに行くようにね。要するにちょっとメタフィクションぽくなっている。
戦国時代というのは漫画の世界でありフィクションの虚構の世界であって、高橋留美子が描いてきたような時間の止まったユートピアだよね。その虚構と現実の世界を自由に往復するような現代的な主体がかごめだった。『犬夜叉』って一言で言うと、高橋留美子の長い反論なんだよ。押井守に告発されたように、自分の描いてきた世界は時間の止まったユートピアの絵空事で、そこを維持するためには数々の欺瞞というか暴力性、排除の論理が働いている動んだけど、そういったものがあるからこそ人間は生きられるだっていうメタフィクショナルな意識によって『犬夜叉』ってできていると思うんだよね。
──高橋留美子さんがずっと漫画でやってきたことの結晶みたいな作品が『犬夜叉』だったんですね。
宇野 ただ、『犬夜叉』の問題というのは高橋留美子がそういったメタフィクショナルな意識を前面化することにためらいがあったこと。桔梗が序盤でとっとと死んで犬夜叉とかごめが新しい関係性をどう築いていくかということと奈落という抽象的な悪の打倒と結びついていくのが本来の構造のはずだけど、単行本が56巻あって桔梗が死ぬのは47巻でしょ? 高橋留美子は自分の過去の世界との決別できないんだよね。
桔梗を殺せないという問題が高橋留美子の本音、「母性のディストピア」で何が悪いんだという本音を表していると思う。人間というのは別に社会化しなくてもいいんだ、と。老いから目をそらしてこの私たちの肥大した母性と矮小な父性の結託で完成するんだったら、そこでパブリックなものが失われていっても、その裏で犠牲になる人がいたとしても私たちは幸福なんだからいいじゃないか、という。だってそれが私にとって必要な美しいファンタジーなんだからということをどこかで思っている。ただやっぱり『犬夜叉』ってそのファンタジーの世界に居直るんじゃなくてどこか現実に接続したいという、何か今を生きる『少年サンデー』を読んでいるティーンエイジャーにとっての虚構の役割みたいなところに踏み込んで自分の作品を位置付け直すということをやりたかったんだと思うんだけどね。
──ヒロインのかごめは何度も現実世界に帰りますよね。
宇野 そう、カジュアルに行ったり来たりするでしょ。でも、最後は犬夜叉と結婚して戦国時代に行っちゃって向こうがメインになってあまり現実世界には帰ってこない。それくらいの距離感に落ちついている。
──やはり胎内からは出ていって欲しくないんですね。
宇野 虚構を通過儀礼に大人になっていくのではなくて、虚構と付き合いながらだらだら生きていくという現代的な主体だよね。非日常=仮想現実的ではなく、日常=拡張現実としての虚構。この終わりは最初から決まっていて描きたかったんだと思うのね。ただそこに辿り着くまでに単行本で56巻かかってしまう。高橋留美子の本音としてはは虚構と現実を往復してるんじゃなくて「母性のディストピア」、彼女にとってはユートピアな箱庭の中でずっと遊んでいたいという気持ちなんだろうね。だから、作品の外側からその気持ちを正当化できる物語にしたかったんだと思う。
メタフィクショナルな自意識、要するに単なる読者がユーザーになっていて二次創作もすれば意見も発信すれば、もっと自由に戯れるわけなんだけどそういった現代的なユーザーを本来は高橋留美子は想定できない。想定したくなかった人なんだと思う。
ちなみに、あの時期に高橋留美子は青年誌で「老い」というものをテーマに描いていた。
高橋留美子のキャラクターだとおじいちゃんやおばあちゃんがいると八宝斎だとか錯乱坊(チェリー)の二頭身になっちゃうじゃない。高橋留美子ってずっと「老い」から逃げてきた人なのね。
──たしかにおじいちゃんやおばあちゃんだと極端にコミカルなキャラクター造形になっていますね。
宇野 普通に六等身か七頭身の大人のキャラクターが年を取っていて、それをどう受け入れるかというテーマで十年ぐらい描いている短編集『高橋留美子劇場』というのがある。それと『犬夜叉』が完結に向かっている時期って重なっていた。だから高橋留美子なりに「老い」というものを引き受けるということを『犬夜叉』を描いている時期に、何か現代的なメタフィクショナルな感性、これまでと違った虚構との付き合い方を模索していたはずなんだよねっていう話をしだしたら本当にあと10万字かかるんだよ。
──高橋留美子に関しては途中の押井守論に入ってきたので、今回は一章分ではなく取り込む形にしたんだなって思いました。でも、丸ごと一章文で読みたいです。
宇野 これが売れたら高橋留美子論で一冊書いて出したいよね。それは宿題にさせてほしい。
──本当に高橋留美子論ってあまり聞かないですね。
宇野 そうでしょ? 『新潮』時代から温めていた「母性のディストピア」というアイデアを宮崎・富野・押井というそれぞれ一冊分かけて書かないといけないような巨人たちの仕事への批評として結実させること、さらにそこでここ数年編集者としてやってきた情報社会論や戦後論を接続させる、というコンセプトを決めた時点で、分量的に高橋留美子については削るしかなかった。
母性のディストピアは、情報社会によって強化された
──では、別の機会ということですが高橋留美子以外で「母性のディストピア」として取り扱うべき女性作家というと誰になりますか?宇野 『新潮』版では過剰に母になろうとする高橋留美子と母になることを心のどこかで拒否する近藤ようこの対比で論を展開したんだよ。最終的には『犬夜叉』と『水鏡綺譚』の対比になっていく。『犬夜叉』は高橋留美子なりのビルドゥングスロマンを再構築しようとした作品で、その結論が「戦国時代に嫁に行く」という選択。
──あるいは遊び続けるようなことですね。
宇野 ただし、『うる星やつら2 ビューティフル・ドリーマー』みたいに虚構に耽溺するのではなくて自由に現実と往復するというインターネット以降の感性を取り込むことによって、押井守がかつて批判した「母性のディストピア」が情報社会の感性というか現代の前提としてメタフィクショナルなユーザーの自意識と結託していってむしろ強化されてしまっていた。
──そう本書にも書かれていましたよね。
宇野 そう、まさに本書で言う「情報技術によってより強化された母性のディストピア」だよね。
『ビューティフル・ドリーマー』の世界っていつかは破綻するわけなんだよ。ラムちゃんの無意識が都合の悪い他者を一人ずつ粛清して人柱にしていったらどんどん人はいなくなっていくし、その度にあたるはラムと向き合わなきゃいけない日が近づいていく。でも、『犬夜叉』のエンディングというのは終わりがないよね。かごめは戦国時代と現代を自由にタイムスリップして行き来するわけであってさ、現実で嫌なことがあれば自分がヒロインになれる戦国時代にワープして癒されるわけだ。そして現実にときどき帰ってくれば彼女は戦国時代にも責任を取らなくていいい。だから情報社会によって「母性のディストピア」という日常は完成してしまったんだよ。
対して近藤ようこというのは、徹底してどちらかというと母になれない女性の葛藤というものを描いていて、彼女の方がファンタジーというか、『水鏡綺譚』だと一周回って通過儀礼としてのボーイミーツガールの冒険譚というものを素朴に信じられる。この逆説だよね。そこにある奇妙なねじれというものを実は「新潮」版で書いていて、それをアップデートする形で今度は高橋留美子論を、半分は近藤ようこ論として書きたいなって思っている。ちなみに近藤ようこの坂口安吾シリーズは読んでる? 最高だよ。 ──どういうタイトルのものがオススメですか?
宇野 『夜長姫と耳男』(外部リンク)や『桜の森の満開の下』(外部リンク)だね。それに『戦争と一人の女』(外部リンク)。そういったところも含めて高橋留美子&近藤ようこ論をどこかで書きたいなと思ってる。
──『母性のディストピア』の反響が大きければいけそうですね。
宇野 そうだね、『母性のディストピア外伝 高橋留美子と近藤ようこ』みたいなものを。
──外伝であり本質的な部分も兼ねていますね。
宇野 この本を読んでね、フェミニズム関連の研究者あたりにここで書かれている母性は男性から見たものであり、母性に対する内在的な批判ではない、という批判はあるんじゃないかと思う。的外れな批判ではあると思うけど、たしかに僕は今回は意識的に日本の近代の「男性的な」自意識の問題として母性というものを描いているからね。
男性が父になれない、家長になれない崩れの男性の精神的な依存先としての母性であって、究極的に言うと江藤淳や村上春樹にとっての母性。男の妄想的産物の母性だという批判は当然来るだろうけど、僕は今回に限って言えばそれ以外は最初から扱う気はかったんだよ。母性そのものの内在的な批評というものと、戦後日本の「母性のディストピア」的な閉鎖性を組み合わせて論じるにはあと二冊ぐらいいると思うんだよ。それはちょっとこれも宿題にさせてほしい。さすがに40万字書いたんだから、「○○が入っていない」みたいな批判は勘弁して欲しいだよね(笑)。それに関しては他の機会に譲らせてほしい。
続きはこちら!

この記事どう思う?
関連リンク
宇野
評論家
1978年生まれ。評論家。批評誌〈PLANETS〉編集長。著書に『ゼロ年代の想像力』(早川書房)、『リトル・ピープルの時代』(幻冬舎)、『日本文化の論点』(筑摩書房)、石破茂との対談『こんな日本をつくりたい』(太田出版)、『静かなる革命へのブループリント この国の未来をつくる7つの対話』(河出書房新社)など多数。企画・編集参加に「思想地図 vol.4」(NHK出版)、「朝日ジャーナル 日本破壊計画」(朝日新聞出版)など。京都精華大学ポピュラーカルチャー学部非常勤講師、立教大学兼任講師。

碇本
ライター
『水道橋博士のメルマ旬報』にて「碇のむきだし」、『週刊ポスト』にて「予告編妄想かわら版」連載中。

連載
評論家・宇野常寛の6年ぶりの単著『母性のディストピア』は、宮崎駿、富野由悠季、押井守という3人のアニメーション作家に焦点を当てている。 彼らはどのようにして「母性」と対峙したのか、その精神性は社会にどのような影響を与えたのか。 「政治と文学」から「市場とゲーム」へと価値観が移り変わっていく社会を示唆した本作をさらに深く読み解くための、超ロングインタビュー。




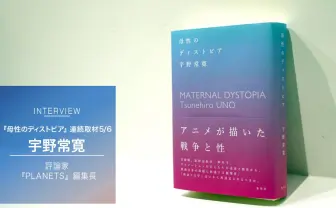




0件のコメント