前回は『母性のディストピア』で実現したかったこと/したことを、『母性のディストピア』内では論じきれなかった高橋留美子『犬夜叉』を読み解き、その「母性」の在り方を思考することで浮かび上がらせた。 そして今回は、宇野常寛という評論家自身について多く語られることになった。テレビに出演していた理由、ドラマやアニメ、特撮といったサブカルチャー批評を行わなくなったかのように見えた理由など──それは時代の要請と、文化的な変容がもたらしたものだった。
10月26日に刊行された新刊『母性のディストピア』はどのようなスタンスで描かれた評論なのか。より広い視座から迫っていく。
取材/インタビューテキスト:碇本学 文:米村智水
小松左京ではなく、惹かれるのは光瀬龍
──江藤淳と村上春樹の話が出てきました(前回の記事)。僕は昔から村上春樹と宮崎駿がどうも苦手だったんです。その理由はおそらく本書に書かれているような、宮崎駿だったら「女の子が一緒にいないと飛べない」とかそういうことが本能的にダメだったんだなと思いました。しかし、日テレで毎年のように宮崎駿、ジブリ作品を放送していた時期がありました。それが今は『エヴァ』に変わっただけですが、そのことが日本における「母性のディストピア」を強化していったんじゃないかなと思ったのですが。宇野 それはいい指摘だよね。僕が小二の時に母親と弟と一緒に『天空の城ラピュタ』を1986年にリアルタイムで観にいったんだよね。ある意味ジブリで育った最初の世代だと言えるんだけど、子供の頃は普通に好きだった。でも小学校高学年とか中学生ぐらいになってくると面白いんだけどそこまで好きな作品じゃないなって。ジブリの中でも『魔女の宅急便』や『となりのトトロ』のほうが次第に好きになっていった。それはなぜかと言うと男は強くなきゃ、女の子を救わなきゃいけないみたいなことに少し違和感があったんだよ。なんか「女の子を救う」なんて自己満足っぽくて嫌だなあ、と感じていたんだよね。頭でっかちな子供だったから、もうちょっと普遍的な社会正義とかの方が大事なんじゃないかなと思ってた。
宮崎駿『天空の城ラピュタ』amazon.jp
──それは『汎イメージ論』(外部リンク)でも書かれてるチームラボの猪子寿之さんに繋がってるんですか?
宇野 そうだね。だから今でも女の子を救うとか全然好きじゃない。思春期の頃のような嫌悪感も薄くなったけど。その辺に僕が「仮面ライダー」が好きな理由が関わってくるんだけど、僕はそもそも人間の顔とか、そんなに好きじゃない。いや、好きなんだけど普通に人の顔をしたキャラクターよりは異形のヒーローに惹かれてきた。人間が人間でないものに変化していくことにワクワクする人間で、「この女は俺が守ってるぜ」みたいな充実感にワクワクしない人間だったんだよね。
立派な人間に、「父」に「成熟」するんじゃなくてさ、まったく別のものに「変身」する方に惹かれていたんだよ、ずっと。これは『リトル・ピープルの時代』のテーマだった。それは生理的なものだったんだと思うんだけど、その違和感みたいなものを僕も君みたいに感じていた。
──この本を読んでいてすごく納得がいったのがそこです。どうしてみんながあんなに好きって言っているものを僕は苦手なんだろうと考えたら理由はそこの部分にあるんだろうなと。僕も女の子を救いにいく話というものに感情移入したりないですし、また母性的なものに包まれたいという欲求もさほどありません。
先ほど宇野さんが言われたように、歴史のような大きな流れや、個人みたいなものに興味があります。その中の一部分が誰かや何かを救う物語だったら全然いいんですけど、それがメインだったり、『君の名は。』みたいなものになるとやっぱりノレないです。
宇野 だから、僕は小松左京か光瀬龍かと言われたら『百億の昼と千億の夜』の光瀬龍なんだよ。小松左京はそういった巨大な時間の流れだったり超越者の存在だったりというものを家族や父と子の物語に接続していくわけでしょう? 『百億の昼と千億の夜』はそれと対となる作品だけど、そういった個人の意識の問題を越えた現象として、宇宙にとって人間の知性とは何か、ということをすごくマクロな視点から書いている。 宇野 単に巨大なものを直視すればいい、という話ではなくてさ。まずは人間不在の途方もない世界の大きさが、広さがあって、その中のほんの塵のような人間の存在、という視点なくして、大きなものと小さなものの関係──この本で言うところの世界と個人、政治と文学の関係なんて語りようがないと思う。すべて自意識の問題に比喩してしまえるなら、そもそも思想も文化も必要ない。宮台真司風に言うと「自分の物語」だけではなく「世界の物語」を想像し得るものが人間の知性だと思うんだよね。
現代的な視点と20世紀的サブカルチャー批評を組み合わせる
──『母性のディストピア』の中で宇野さんは批評について「圧倒的な彼我の距離の言葉を用いて破壊し、ゼロにすること。遠く離れ、本来は繋がらないはずのものを、つなげること」と書かれています。その姿勢をずっと続けられていると思うのですが、読者に届いているという感覚はありますか?宇野 届くところには届いているし、基本的にはそれでいいのだけど、いま碇本くんが言っているのはもっと国内全体の文化のシーンに影響をおよぼすことができているのか、みたいなことだと思う。だとするとちょっとそれは分からない。正直に言うと、以前ほどそういうことに興味がなくなってしまった。
例えば、僕のデビュー作の『ゼロ年代の想像力』はどちらかと言えば編集者としての僕が書いた本なんだよね。つまり、東京の業界人たちはムラの中の空気を読んで、面白いものとそうではないものを峻別しているけれど、そこからこぼれ落ちているものにきちんと目を向ければ、まったく新しい文化地図を描くことができるぞ、というのが『ゼロ年代の想像力』だった。インターネットによって様々なシーンが拡散されていった今日において、サブカルチャーの全体性なんて描けないとみんな思っているけど、しっかりとした批評的によってパースペクティブを作り直せば全体性を見渡せるんだっていう僕の編集者としての自意識が書かせた本だった。
『リトル・ピープルの時代』はどちらかというと批評家としての僕が書かせた本。村上春樹と「仮面ライダー」というまったく接続できないものを接続するとこれまでにない新しい視点が得られる、という内容の本だった。
『母性のディストピア』ではもう端的に戦後の精神史は、それも後半の35年はアニメ史から見ると最も深くその本質に触れることができるぞ、ということがやりたかったわけ。もちろん、それだけでは収まらなくて、そこからぐっと視線を現代まで引き伸ばして、戦後アニメの分析で得られたものを応用して、この本当にどうしようもなくなっている日本社会の突破口というか、あるべき主体を考えるというところまで行こう、ということをやった。だから単純に二冊分の分量になった。
実は富野由悠季論や押井守論ってまとまったものがほとんどなくて、富野論では氷川竜介さんとササキバラ・ゴウさんがそれぞれ『ザンボット3』論(外部リンク)と、『Vガンダム』論(外部リンク)を一冊ずつ。押井論に至っては野田真外さんの編著一冊くらいしかまともなものは存在していない。そして残念ながらどちらも20年ぐらい前の本で、最近の作品はフォローしていない。そういったアニメ雑誌やムックにルーツを持つ言葉と、現代のハイブリッドな批評を接続するというのも今回のテーマだった。宮台真司や大塚英志と同じように氷川竜介やササキバラ・ゴウを語っているような本ってあまりないと思うんだよね。
──ないと思います。
宇野 そういったこともやりたかったのが今回の『母性のディストピア』なんだけど、僕がやっているある種の越境的なことっていうのは、たしかにあまり理解されてはいないかもしれないね。メッセージ自体は伝わっているかもしれないけれど、こういう意図まではなかなか伝わっていない。別にそれでいいと言えばいいんだけど、これからものを作る仕事につきたい人はこういうことを考える癖をつけたほうがいいと思う。
実際にそれは僕が抱えている分裂を解消するという問題でもあって。碇本くんは昔から『PLANETS』を読んでくれていると思うけど、紙面とか扱っているコンテンツってだいぶ変わったでしょ。当然意図的にやってることなんだけど。
──変わりましたよね。昔は『クイックジャパン』的なものがありました。当時の『クイックジャパン』に対して、俺ならこう作るみたいな宇野さんの視点がありましたよね。
宇野 うん、当時僕が考えていたのは、サブカル雑誌はもっと批評と向き合わないといけない、批評という意識がないとサブカルチャーの全体性やシーンを再構築できないんだということ。東京の業界人たちには見えてないものがたくさんあって、例えばなんでこの「平成仮面ライダーシリーズ」のすごさに気づかないんだとか、ずっと思っていた。彼らには見えていないものがたくさんあって、なぜ彼らが見えていないかというとすでに確立されたジャンルの意識に捉われて、業界の空気というものの中でイケているものとイケていないものを峻別するからであって。それをぶち壊して、その空気に対抗するためには「批評」というものをしっかり持ち込まないといけないって当時の僕は考えていた。
サブカルチャーのシーンのパースペクティブを作り直さないといけないという意識、そして批評と向き合うことをやらないといけない。
ただ、現在の僕はそうは考えていない。端的に言えばサブカルチャーの社会的な機能が変わってしまったから。もっと言ってしまえばサブカルチャーの時代がもう終わったから。だからこの本は現在の視点から書かれていて、はっきり言ってしまうと、サブカルチャーの時代自体が終わっているんだと宣言してしまっている。
宇野常寛は変わったのか?
──同時に「映像の世紀」についても思っていると。宇野 そもそも20世紀最後の四半世紀におけるサブカルチャーは革命の代替物だった。革命で世界を変えるのではなく、その代わりに自分の内面を変える時代というのが20世紀の最後の四半世紀であって、この時期に先進国では若者向けのサブカルチャーが特権的な位置にあった。そして日本ではこの本で扱っているアニメもその一ジャンルだった。しかし今は違う。カリフォルニアン・イデオロギー以降、市場を通じて世界を変えるということが信じられている現在においては、かつてのサブカルチャーの機能は相対的に失われている。
宇野常寛
──確かにそういうことをしている人は他にはいないですね。
宇野 だから付き合う人も変わった。
──そうなってきますよね。
宇野 はっきり言うとね。もしかしたら碇本くんみたいな昔からの読者は若干の寂しさを感じているかもしれないね。宇野さんは変な方向に、自分の関心とは違う方向に行ってしまったと思った人はたくさんいたと思うんだよ。実際にそう言われてきたし。だってさ、「PLANETS」が法人化して最初に出した単行本が工学系の研究者の本になるとは誰も思わなかったでしょ?
──思いませんでしたね。でも、それは現在の社会と呼応していることが感じられて僕は違和感なかったです。
宇野 そう言ってもらえると嬉しい。「宇野さんや『PLANETS』は社会評論やテクノロジーの話が多くなって、サブカルチャーを捨ててしまったんですね」ってずいぶん言われたよ。でも、僕の中ではやっていることは変わってないんだよね。
20世紀の最後の30年において、サブカルチャーの位置にあったものが今だったらなんだろうと考えた結果、例えば情報社会論だったりビジネスの話だったり、あるいはテクノロジーやメディアアートの話だったりをしているんだよね。
──さっき言われたように宇野さんを変わってしまったと言っている人たちはおそらく表面上をなぞっているだけで読めていない可能性が高いので、届けるのは少し難しいのかもしれないですね。
宇野 でもね、そこは聞く耳を持った人しか聞かないから。最初から結論が分かっているものにしか触れたくない人のほうが、いまや文化論や批評の読者にも多いと思う。聞く耳を持たない人に届ける仕事というのは、批評的な言語というものとは違うやり方をした方がいいと思っている。
──それと『スッキリ』に出演していたことは関係があるんでしょうか?
宇野 テレビに関してはね……なんて言ったらいいのかな。僕がテレビでやろうとしていたことは一つで「こんなものを見ていたら頭がバカになる」ということを伝えることだったんだよ。だから、2年間ずっと今のこのテレビというシステム自体が間違っていると週に一回言い続けてきた。もちろん、ここで言う「テレビ」はそこに付随するインターネットも含めて、だね。その結果、テレビにTwitterで突っ込んでばかりいると本当にバカになるぞ、って気づいてくれた人が1人でも、2人でもいればいい。それ以外の効果は期待していない。
──だから、宇野さんがアニメについて論じるって言った時に驚く人もいるわけですもんね。
宇野 うん、それはけっこういい効果だと思う。今まで届かなかった人に僕の仕事のことに関心を持ってもらっているということだからね。そういう意味では2年間我慢して出てよかったなと思っている。
──Twitterでそういう声を見て、テレビで宇野さんが言われていることを感じた人たちが仕事に興味を持っているのはすごいことだと思います。
宇野 『スッキリ』で僕を知った人にあそこで僕が喋っていた背景にこういう思考があったんだと知ってくれると一番嬉しいね。
「映像の世紀」と「自動車の世紀」の終わり
──20世紀は「映像の世紀」であり、同時に「自動車の世紀」でした。「PLANETS」でも根津孝太さんの『カーデザインは未来を描く』が刊行されています。宇野 落合陽一さんの『魔法の世紀』というのは「映像の世紀」の終わりの話で、『カーデザインは未来を描く』は「自動車の世紀」の終わりの話なんだよね。どちらもなくなるのではなくて、20世紀に占めていた特権的な位置を失っていくということ。むしろもっと上位の、はっきり言ってしまえば人工知能とIoTの組み合わせなんだけど、21世紀に普及するそういうものの付属物として変化していく。例えば車でいうと自動運転になっていって操縦するものではなくなっていくから20世紀に帯びていたような男性性と市民性の象徴ではなくなっていく。 宇野 考えてみて欲しいんだけど、車って1.5トンとかある鋼鉄の塊を内燃機関で動かしているんだから、要するに爆弾と一緒だよね。あんなものを個人が運転するって免許制といえどものすごい権力なんだよ。20世紀の人は社会を急速に発展させるためとはいえ無茶してたなって、免許制とはいえあんなものを個人が扱っていたんだから恐ろしい時代だったんだなと21世紀以降の人間は思うはずなんだよ。しかし、それが自動運転や電気化によってだいぶ変わっていく。もっと言ってしまえば家電化していく。スマホの次の、人間の隙間の時間をデザインするものになる。
同じように映像というのもバラバラなものを統合するためのものだったけど、間違いなくその位置づけが変わる。映像と放送技術という組み合わせで人類は20世紀の国民国家を維持できていたわけだからね。ハリウッド映画なんて本当の意味で聖書以降初のグローバルコンテンツなんだよ。
しかし、インターネットが普及すると20世紀の人間のように誰もが同じものを見ているという状況は考えづらくなっていく。バラバラのものがバラバラのままで生きていけるようになるし、それを支援する人工知能も発達していく。映像の共同幻想の器としての役割が解体されていくと思う。映像と車というのはどちらも20世紀の社会におけるバラバラなものを繋ぐためのもので、そしてそれゆえにその役割をどちらも終えていくということだよね。
──その先の未来を僕たちは生きていくんですね。
宇野 うん、映像や車がなくなるということではなく、役割が変化しているってこと。
──役割が変化していっているのに、それを認識できていない20世紀的な社会システムに拘泥してしまう人がいることが様々な断絶を生んでるのかもしれないですね。
宇野 そうだね、例えば豊田章男さん(第11代 トヨタ自動車株式会社代表取締役社長)が「車を持てば、女性にもてる」って言って炎上したけど彼には全然悪意はなくて、若い人に車の魅力を伝えたいと思って尽くした結果、変に誤解されて炎上してしまった。ただ、残念ながらそういう時代じゃないよね。「新潮」版の『母性のディストピア』の連載で片岡義男論を少しやったんだけど、あの頃はオートバイとか自動車のようなエンジンがついた乗り物は大人の男の象徴だったんだよね。そういう時代のことを念頭に置いて章男さんは言っているわけだ。かつて自動車は成熟した大人の男性の象徴だった。しかし今車が大好きでお金をかけているような奴は『頭文字D』の走り屋みたいな人たちで、彼らはどちらかというと青年のホモソーシャルに止まっている人たちだよね。
──そうですね、そこには女性がいらないですね。
宇野 どちらかというと狭い意味で成熟を拒否するような人たちだよね。そういう意味では『頭文字D』は僕が高校生の頃からだから90年代後半からすでに自動車が成熟の象徴ということは終わっていた。そういうズレは確かにあるよね。
宇野常寛『母性のディストピア』連続インタビュー

この記事どう思う?
関連リンク
宇野
評論家
1978年生まれ。評論家。批評誌〈PLANETS〉編集長。著書に『ゼロ年代の想像力』(早川書房)、『リトル・ピープルの時代』(幻冬舎)、『日本文化の論点』(筑摩書房)、石破茂との対談『こんな日本をつくりたい』(太田出版)、『静かなる革命へのブループリント この国の未来をつくる7つの対話』(河出書房新社)など多数。企画・編集参加に「思想地図 vol.4」(NHK出版)、「朝日ジャーナル 日本破壊計画」(朝日新聞出版)など。京都精華大学ポピュラーカルチャー学部非常勤講師、立教大学兼任講師。

碇本
ライター
『水道橋博士のメルマ旬報』にて「碇のむきだし」、『週刊ポスト』にて「予告編妄想かわら版」連載中。

連載
評論家・宇野常寛の6年ぶりの単著『母性のディストピア』は、宮崎駿、富野由悠季、押井守という3人のアニメーション作家に焦点を当てている。 彼らはどのようにして「母性」と対峙したのか、その精神性は社会にどのような影響を与えたのか。 「政治と文学」から「市場とゲーム」へと価値観が移り変わっていく社会を示唆した本作をさらに深く読み解くための、超ロングインタビュー。




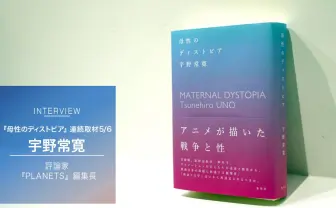




0件のコメント