2017年9月でサービス10周年を迎えたイラストコミュケーションサービス「pixiv」。その10年の軌跡をまとめた記念書籍書籍『pixiv archive 2007-2017』が発表された。
3000部限定で装丁にこだわった豪華な書籍で、全632ページ、重量3kgという異様な形態には「頭おかしい」「鈍器」といった反響が。その中身は、pixiv10年のイラスト文化の変遷を辿るもの。
驚異的な数字は、投稿だけではない。「全タグ数は681万4745件、ブックマーク数の総計は25億8096万4529回、閲覧数の合計は1063億9787万4488回、評価回数は32億7774万5053回」だという。
※計測期間はいずれも2007年9月10日から2017年9月10日まで
pixivの創始者であり、ハンドルネーム「馬骨」で親しまれている上谷隆宏さんと、黎明期からクリエイターとして「pixiv」を見てきたネットイラストに造詣の深いイラストレーター・虎硬さんの2人をゲストに、実際の書籍をレビュー。当日は書籍の担当編集も同席した。
この10年のイラストレーションを振り返ると共に、「pixiv」の登場は何を変えたのかを見ていきたい。
取材・文:千葉秋楽/新見直 編集:新見直
虎硬 取材の前にいただいたデータを拝見してしました。もうめちゃくちゃ懐かしくて、なぜか涙が出ました(笑)。
僕はpixivが始まって1週間くらいで登録をしました。IDが3646番なのでかなり古参だと思ってます。だから、10年間ずっといちユーザーとしてpixivを閲覧してきて、素直に感慨深いですね。
「このイラストは本当に素晴らしかったな〜」という思いと同時に「この頃は大学生だったな」や「バイト辞めてニートだったな」とか「このタイミングでpixivから仕事が来て、絵描きとして食っていけるようになったな」など、自分の個人的な部分も思い出しました。
──一方、馬骨さんは開発者としてこの本をご覧になっているわけですが、いかがでしょうか?
僕はとっくにpixivの開発からは退いてしまったので、一歩引いて見た時、ここからトレンドやカルチャーの変遷が俯瞰できるなと。
──そもそもpixiv登場以前は、イラストレーターの方たちはどこでイラストを発表していたのですか?
虎硬 “共有する”という概念でいえば、お絵かき掲示板やお絵かきチャット(絵チャ)もあったんですが、たいていの方たちは個人サイトを持っていて、そこでイラストを公開してましたね。pixivができて、それが一気に集約された印象です。
“プラットフォーム”と言う概念は今でこそ当たり前のものですが、当時は一般的ではなかったですから。pixivができて、ジャンルが異なる絵描きがひとつの場所に集まって、「世の中にこんな絵の上手い人がいるんだ!」と衝撃を受けるという……。
馬骨 僕がpixivを思いついたのもまさに、僕自身が絵を描くし、絵を見るのも好きなんだけど、それぞれの個人サイトをチェックするのが面倒くさかったから、という理由です(笑)。
ブラウザのブックマーク数が100とか200になっていて、更新されたか見に行くまでわからないし、それはあまりに大変だなと。
──イラストを観る側にとっては集約されていて見やすいというメリットがあり、描く/投稿する側にとっては集約されることで新しい人にも作品を観てもらえるという。それが盛り上がりに寄与した部分もあると思います
編集 「pixiv」は当初、マンスリーランキングが存在しなかったんです。マンスリーランキングは2008年4月から実装されました。
ただし、ユーザーの閲覧データは残っているので、現在のマンスリーランキングのガイドラインに沿って10年間のログから算出したデータをもとに改めてランキングを出しました。「この時一番観られてたのは、実はこれだった」というデータになっています。
あとはコザキユースケさんのこのイラスト、大好きです。制作自体はpixivよりさらに昔だったと記憶してます。pixiv初期に自分の古いイラストを上げる流れがありました。コザキさんは個人サイト時代からネットで多くのファンがいる方ですよね。最近では『ポケモンGO』で非常に有名になりました。
──このイラストはつくしあきひとさんですよね?
馬骨 僕もサイトをブックマークしてました。『メイドインアビス』がアニメ化されて去年ヒットしましたね。
虎硬 続編も決定していますよね。大ベテランというか、インターネットのイラスト黎明期、2000年初頭からもう有名な方でした。当時からこういうタッチの世界観が素敵なイラストの絵を描かれていて、ある時から漫画を描きはじめてそれが今大ヒットという……。
虎硬 当時のmebaeさんは、今とは少し違った雰囲気の絵を描かれてます。この頃からアニメーションはかなりユニークなものをつくられていて、卒業制作アニメは衝撃でした。そして、いつ見ても絵柄に”新しさ”が宿ってます。絵描きとして格好いいな〜と思いますね!mebaeさんの卒業制作アニメ
虎硬 当時はネットでイラストを描いている人たちがこぞって飛びついた印象ですね。
馬骨 この頃は約8割のユーザーがクリエイターだったと思います。描いてる人と評価してる人が同じクリエイター同士で、当時のpixivは極めて玄人向けでした。キャラクターというより、コンセプトアートや背景が高く評価されていましたし。
今は裾野が広がって、1割がクリエイターの方たちで、残りは鑑賞する人たちという感じで逆転してきてますよね。
──当時のpixivのコンセプトで“イラストが集まる場所”というキーワードがあったかと思いますが、当時どういうイラストが集まると想定されていましたか?
馬骨 ここまで多種多様なイラストが集まるとは思っていませんでした。僕的にはやっぱり、最初からキャラクターものが集まるのかなと思っていましたね。
hukeさん、redjuiceさん。さらには三輪士郎さん、六七質さん、瀬尾さん、こよりさん、赤りんごさん、バーニア600さん、bobさん、マサリロさん、藤ちょこさん……。有名なクリエイターが勢揃いです。
虎硬 あとは、1月から始まった『pixivファンタジア』。今では、10回を超える大人気企画になりましたね。
──pixiv初期のユーザー企画ですね。
馬骨 pixivの中でユーザーの方が自主的に立ち上げる「ユーザー企画」はいくつかあったんですけど、一番盛り上がったのが『pixivファンタジア』ですね。この当時は相当数有名なクリエイターが参加していました。
虎硬 僕も『pixivファンタジア』には最初から参加していました。この当時の盛り上がりは本当にすごくて。同時期にpixivを使って面白い遊びが出来ないか試している人はちらほらいましたが、『pixivファンタジア』は圧倒的でした。主催のarohaJさんの世界観設定のつくり込みがすごかったです。
──世界観のつくり込みがユーザーに火を付けた?
虎硬 世界観もですけど、運営の頑張りが一番の要因だと思います。arohaJさんはいちユーザーですが、投稿数を手動でカウントして毎週戦況を報告してくれる。その実況がすごかったし、何千枚もの投稿イラストを全部チェックしてコメントを付けたりしていました。
そもそもそういう企画を運営ではなく、ユーザーがつくるという体験が初めてで。それまでは個人でお題を出してイラストを描くといっても、集まるのはせいぜい10人20人です。ところが『pixivファンタジア』は、はじめから1000枚を超える規模でした。今では1万枚超えてますね。これを人力でまとめあげるのがすごい。
虎硬 初音ミクの有名楽曲『ワールドイズマイン』(ryoさん作曲)ですね。あと『サイハテ』(小林オニキスさん作曲)。今の20代にはこの辺がかなり刺さってくるんじゃないでしょうか。
虎硬 三輪士郎さんやredjuiceさんは元々有名ですね。僕の認識だと、藤ちょこさんは非常に人気が出たと思います。
「創作活動がもっと楽しくなる場所をつくる」というのは、ピクシブの企業としての理念にもなってますよね。この作品から影響を受けたという話は、ピクシブ創業者・片桐(孝憲)さんもされています(外部リンク)。
そしてまるかたさん、ほぼ毎日絵を描いて投稿されていて、ずっとランキングに入っていました。当時イラストレーター仲間の間では「よくこんな速さで描けるな」とみんな驚かされてました。
──廃墟萌えがあったり、東京幻想さんもいますね。
馬骨 自分の中では「pixiv」はイラストサイトだと思っていたので、漫画が流行るとは思ってなかったですね。
縦に長い漫画を投稿するとサムネイルが細いドットになっていて、ユーザーの中では「つまようじ」と呼ばれていました。
漫画を意識した複数枚投稿機能は2009年9月から実装しましたが、それでもしばらくの間、縦長の細い1枚漫画を投稿されていました。ある意味、今のスマホ漫画の原点かもしれません。
馬骨 「インセイン・ブラック★ロックシューター」のクオリティはすごかったです。僕はこのフィギュアも買いましたよ。hukeさんが最近投稿してくれないのでちょっと寂しいですね……。
虎硬 憂さんの圧倒的な筆致。『初音ミク・アペンド』もこのあたりなんですね。当時、デザインを原型師の浅井真紀さんが担当したことで話題になりましたね。
──“中国塗り”って、具体的にはどういうことですか?
虎硬 個人的見解ですが、中国の高等教育を受けた人が日本カルチャーに触れた時に、謎の突然変異をするんですよ。厚塗りがベースなのですが、そこに日本的な絵の記号を上手く乗せています。
あと、このhageさんの水ミクは、初音ミクの中でいうと歴代でもトップではないでしょうか。閲覧数が現在120万……スゴい。
──二次創作のイラストが一層厚みが増してきた時代ですね。
馬骨 二次創作は、作品に対する愛がないと描けないですからね。
虎硬 3話は色々な意味で衝撃的でした。『まどマギ』は2010年代を代表する作品になりましたね。最近ではアプリゲームも大ヒットしてます。
──『まどマギ』は、東日本大震災の影響もあって最後の放送が延期になったことも大きな反響を呼んだ記憶があります。
そして、この水あさとさんの「あいさつの魔法。」も話題になりました。やはり2011年は東日本大震災の影響はあらゆる場所で起こっていて、当時、CMのほとんども各社自粛を受けてACジャパンが独占していました。そのためネットでは、被災者へのエールだけではなく、ACジャパンの二次創作が増えましたね。
馬骨 このJH科学さんの真空管ヘッドホンほしいです。
──わずか3年の間でキャラクター、アート、背景、コンセプト、企画など、多様性があります。3年振り返るだけで軽く1時間以上かかっています…。
虎硬 ザッと眺めても、確かにエッセイ漫画増えましたね。
──例えば、話題作の一つ、御手洗直子さんの『31歳同人女が婚活するとこうなる』は、とあるオタク女性が結婚に向き合う様をギャグとして描き、実際に結婚をされた本人の体験エッセイですね。後、旦那さん視点での漫画も刊行されるという(笑)。
あ、コーラさんの背景イラストもありますね。
馬骨 コーラさんのイラストのどこかにうっすらと必ず「コーラ」と描いてあるんですよね。投稿されたらそれを探し、そしてタグを付ける文化。
3000部限定で装丁にこだわった豪華な書籍で、全632ページ、重量3kgという異様な形態には「頭おかしい」「鈍器」といった反響が。その中身は、pixiv10年のイラスト文化の変遷を辿るもの。
驚異的な数字は、投稿だけではない。「全タグ数は681万4745件、ブックマーク数の総計は25億8096万4529回、閲覧数の合計は1063億9787万4488回、評価回数は32億7774万5053回」だという。
※計測期間はいずれも2007年9月10日から2017年9月10日まで
pixivの創始者であり、ハンドルネーム「馬骨」で親しまれている上谷隆宏さんと、黎明期からクリエイターとして「pixiv」を見てきたネットイラストに造詣の深いイラストレーター・虎硬さんの2人をゲストに、実際の書籍をレビュー。当日は書籍の担当編集も同席した。
この10年のイラストレーションを振り返ると共に、「pixiv」の登場は何を変えたのかを見ていきたい。
取材・文:千葉秋楽/新見直 編集:新見直
pixivの10年、インターネット文化の10年、自分の10年を振り返る
──本の中身はもうご覧になりましたか?虎硬 取材の前にいただいたデータを拝見してしました。もうめちゃくちゃ懐かしくて、なぜか涙が出ました(笑)。
僕はpixivが始まって1週間くらいで登録をしました。IDが3646番なのでかなり古参だと思ってます。だから、10年間ずっといちユーザーとしてpixivを閲覧してきて、素直に感慨深いですね。
「このイラストは本当に素晴らしかったな〜」という思いと同時に「この頃は大学生だったな」や「バイト辞めてニートだったな」とか「このタイミングでpixivから仕事が来て、絵描きとして食っていけるようになったな」など、自分の個人的な部分も思い出しました。
──一方、馬骨さんは開発者としてこの本をご覧になっているわけですが、いかがでしょうか?
虎硬さん
僕はとっくにpixivの開発からは退いてしまったので、一歩引いて見た時、ここからトレンドやカルチャーの変遷が俯瞰できるなと。
──そもそもpixiv登場以前は、イラストレーターの方たちはどこでイラストを発表していたのですか?
虎硬 “共有する”という概念でいえば、お絵かき掲示板やお絵かきチャット(絵チャ)もあったんですが、たいていの方たちは個人サイトを持っていて、そこでイラストを公開してましたね。pixivができて、それが一気に集約された印象です。
“プラットフォーム”と言う概念は今でこそ当たり前のものですが、当時は一般的ではなかったですから。pixivができて、ジャンルが異なる絵描きがひとつの場所に集まって、「世の中にこんな絵の上手い人がいるんだ!」と衝撃を受けるという……。
馬骨 僕がpixivを思いついたのもまさに、僕自身が絵を描くし、絵を見るのも好きなんだけど、それぞれの個人サイトをチェックするのが面倒くさかったから、という理由です(笑)。
ブラウザのブックマーク数が100とか200になっていて、更新されたか見に行くまでわからないし、それはあまりに大変だなと。
馬骨さん
──イラストを観る側にとっては集約されていて見やすいというメリットがあり、描く/投稿する側にとっては集約されることで新しい人にも作品を観てもらえるという。それが盛り上がりに寄与した部分もあると思います
from 2007 to 2017 pixiv10年のイラストの旅
──『pixiv archive 2007-2017』を元にこの10年を振り返っていきたいのですが、掲載されているイラストの基準は何ですか?編集 「pixiv」は当初、マンスリーランキングが存在しなかったんです。マンスリーランキングは2008年4月から実装されました。
ただし、ユーザーの閲覧データは残っているので、現在のマンスリーランキングのガイドラインに沿って10年間のログから算出したデータをもとに改めてランキングを出しました。「この時一番観られてたのは、実はこれだった」というデータになっています。
2007年:pixivの誕生
──では早速中身を見ていきましょう。あとはコザキユースケさんのこのイラスト、大好きです。制作自体はpixivよりさらに昔だったと記憶してます。pixiv初期に自分の古いイラストを上げる流れがありました。コザキさんは個人サイト時代からネットで多くのファンがいる方ですよね。最近では『ポケモンGO』で非常に有名になりました。
──このイラストはつくしあきひとさんですよね?
馬骨 僕もサイトをブックマークしてました。『メイドインアビス』がアニメ化されて去年ヒットしましたね。
虎硬 続編も決定していますよね。大ベテランというか、インターネットのイラスト黎明期、2000年初頭からもう有名な方でした。当時からこういうタッチの世界観が素敵なイラストの絵を描かれていて、ある時から漫画を描きはじめてそれが今大ヒットという……。
虎硬 当時のmebaeさんは、今とは少し違った雰囲気の絵を描かれてます。この頃からアニメーションはかなりユニークなものをつくられていて、卒業制作アニメは衝撃でした。そして、いつ見ても絵柄に”新しさ”が宿ってます。絵描きとして格好いいな〜と思いますね!
虎硬 当時はネットでイラストを描いている人たちがこぞって飛びついた印象ですね。
馬骨 この頃は約8割のユーザーがクリエイターだったと思います。描いてる人と評価してる人が同じクリエイター同士で、当時のpixivは極めて玄人向けでした。キャラクターというより、コンセプトアートや背景が高く評価されていましたし。
今は裾野が広がって、1割がクリエイターの方たちで、残りは鑑賞する人たちという感じで逆転してきてますよね。
──当時のpixivのコンセプトで“イラストが集まる場所”というキーワードがあったかと思いますが、当時どういうイラストが集まると想定されていましたか?
馬骨 ここまで多種多様なイラストが集まるとは思っていませんでした。僕的にはやっぱり、最初からキャラクターものが集まるのかなと思っていましたね。
2008年:初年以上のビッグバンが起こる
虎硬 この年はほんっとうにビッグバンですね!hukeさん、redjuiceさん。さらには三輪士郎さん、六七質さん、瀬尾さん、こよりさん、赤りんごさん、バーニア600さん、bobさん、マサリロさん、藤ちょこさん……。有名なクリエイターが勢揃いです。
虎硬 あとは、1月から始まった『pixivファンタジア』。今では、10回を超える大人気企画になりましたね。
──pixiv初期のユーザー企画ですね。
馬骨 pixivの中でユーザーの方が自主的に立ち上げる「ユーザー企画」はいくつかあったんですけど、一番盛り上がったのが『pixivファンタジア』ですね。この当時は相当数有名なクリエイターが参加していました。
虎硬 僕も『pixivファンタジア』には最初から参加していました。この当時の盛り上がりは本当にすごくて。同時期にpixivを使って面白い遊びが出来ないか試している人はちらほらいましたが、『pixivファンタジア』は圧倒的でした。主催のarohaJさんの世界観設定のつくり込みがすごかったです。
──世界観のつくり込みがユーザーに火を付けた?
虎硬 世界観もですけど、運営の頑張りが一番の要因だと思います。arohaJさんはいちユーザーですが、投稿数を手動でカウントして毎週戦況を報告してくれる。その実況がすごかったし、何千枚もの投稿イラストを全部チェックしてコメントを付けたりしていました。
そもそもそういう企画を運営ではなく、ユーザーがつくるという体験が初めてで。それまでは個人でお題を出してイラストを描くといっても、集まるのはせいぜい10人20人です。ところが『pixivファンタジア』は、はじめから1000枚を超える規模でした。今では1万枚超えてますね。これを人力でまとめあげるのがすごい。
虎硬 初音ミクの有名楽曲『ワールドイズマイン』(ryoさん作曲)ですね。あと『サイハテ』(小林オニキスさん作曲)。今の20代にはこの辺がかなり刺さってくるんじゃないでしょうか。
虎硬 三輪士郎さんやredjuiceさんは元々有名ですね。僕の認識だと、藤ちょこさんは非常に人気が出たと思います。
「創作活動がもっと楽しくなる場所をつくる」というのは、ピクシブの企業としての理念にもなってますよね。この作品から影響を受けたという話は、ピクシブ創業者・片桐(孝憲)さんもされています(外部リンク)。
2009年:海外勢の活躍も目覚ましい
虎硬 さよりさんは、海外クリエイターの中ではpixivに早くから投稿されていた方で、今でもずっと精力的に活動されていますね。この頃から、中国、韓国、台湾を中心に多くの海外クリエイターの作品を見る機会が増えました。そしてまるかたさん、ほぼ毎日絵を描いて投稿されていて、ずっとランキングに入っていました。当時イラストレーター仲間の間では「よくこんな速さで描けるな」とみんな驚かされてました。
──廃墟萌えがあったり、東京幻想さんもいますね。
馬骨 自分の中では「pixiv」はイラストサイトだと思っていたので、漫画が流行るとは思ってなかったですね。
縦に長い漫画を投稿するとサムネイルが細いドットになっていて、ユーザーの中では「つまようじ」と呼ばれていました。
漫画を意識した複数枚投稿機能は2009年9月から実装しましたが、それでもしばらくの間、縦長の細い1枚漫画を投稿されていました。ある意味、今のスマホ漫画の原点かもしれません。
馬骨 「インセイン・ブラック★ロックシューター」のクオリティはすごかったです。僕はこのフィギュアも買いましたよ。hukeさんが最近投稿してくれないのでちょっと寂しいですね……。
2010年:中国塗りの台頭、二次創作のさらなる活性化
──2010年は、会員数が160万人を超えたくらいですね。虎硬 憂さんの圧倒的な筆致。『初音ミク・アペンド』もこのあたりなんですね。当時、デザインを原型師の浅井真紀さんが担当したことで話題になりましたね。
──“中国塗り”って、具体的にはどういうことですか?
虎硬 個人的見解ですが、中国の高等教育を受けた人が日本カルチャーに触れた時に、謎の突然変異をするんですよ。厚塗りがベースなのですが、そこに日本的な絵の記号を上手く乗せています。
あと、このhageさんの水ミクは、初音ミクの中でいうと歴代でもトップではないでしょうか。閲覧数が現在120万……スゴい。
──二次創作のイラストが一層厚みが増してきた時代ですね。
馬骨 二次創作は、作品に対する愛がないと描けないですからね。
2011年:東日本大震災の影響は大きく
虎硬 ここでRellaさんが登場するのか……! Rellaさんは、僕が最も尊敬するクリエイターの一人です。ミクのイラストが多いですけど、投稿するたびにランキング上位に入り続けていますね。虎硬 3話は色々な意味で衝撃的でした。『まどマギ』は2010年代を代表する作品になりましたね。最近ではアプリゲームも大ヒットしてます。
──『まどマギ』は、東日本大震災の影響もあって最後の放送が延期になったことも大きな反響を呼んだ記憶があります。
そして、この水あさとさんの「あいさつの魔法。」も話題になりました。やはり2011年は東日本大震災の影響はあらゆる場所で起こっていて、当時、CMのほとんども各社自粛を受けてACジャパンが独占していました。そのためネットでは、被災者へのエールだけではなく、ACジャパンの二次創作が増えましたね。
馬骨 このJH科学さんの真空管ヘッドホンほしいです。
──わずか3年の間でキャラクター、アート、背景、コンセプト、企画など、多様性があります。3年振り返るだけで軽く1時間以上かかっています…。
2012年:エッセイ漫画の増加
──2012年頃から、エッセイ漫画を見かけるようになりました。虎硬 ザッと眺めても、確かにエッセイ漫画増えましたね。
──例えば、話題作の一つ、御手洗直子さんの『31歳同人女が婚活するとこうなる』は、とあるオタク女性が結婚に向き合う様をギャグとして描き、実際に結婚をされた本人の体験エッセイですね。後、旦那さん視点での漫画も刊行されるという(笑)。
あ、コーラさんの背景イラストもありますね。
馬骨 コーラさんのイラストのどこかにうっすらと必ず「コーラ」と描いてあるんですよね。投稿されたらそれを探し、そしてタグを付ける文化。

この記事どう思う?
関連リンク

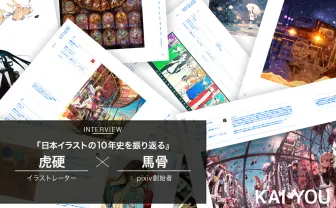
0件のコメント