精神疾患の描写を巡る批判と修正は妥当だったか
このような『ルックバック』にて描かれるフィクションの限界と到達に対し、同じくあの事件に打ちひしがれた人間たちの共感を大いに呼び、SNSでも絶賛の声が湧き上がった。ただしそのような肯定的反響の中、この作品、特に京本を殺害した「通り魔」の描写に対し、批判の声が一定数寄せられたことにも触れなければいけない。精神科医の斎藤環氏は、作品そのものを「傑作」と評した上で「やむを得ないとは思うけれど通り魔の描写だけネガティブなステレオタイプ、つまりスティグマ的になっている。単行本化に際してご配慮いただければ」と指摘している。
そのような批判を踏まえた上か、8月2日、『少年ジャンプ+』編集部は「不適切な表現があるとの指摘を読者からいただいた」ことを根拠に、『ルックバック』の描写を一部修正した。ただし1点だけ。やむを得ないとは思うけれど通り魔の描写だけネガティブなステレオタイプ、つまりスティグマ的になっている。単行本化に際してはご配慮いただければ。
— 斎藤環 3.15発売「まんが やってみたくなるオープンダイアローグ 」 (医学書院) (@pentaxxx) July 19, 2021
具体的な修正箇所は伏せられているが、主に「通り魔」のセリフが「さっきからウッセーんだよ!!ずっと!!」「元々オレのをパクったんだっただろ!?」など、幻聴や被害妄想を思わせる内容が、「今日死ぬって思ったか?」など突発的な殺意を思わせる内容に置き換えられた。
まず、筆者自身、斎藤氏の批判を尊重する。作品を語る前に、そもそも日本に住む419万人もの精神障害者のうち(内閣府資料/外部リンク)、その多くがいまだ社会的な偏見や差別に晒されながら不自由な生活を送っている実情が存在する。『ルックバック』作品内に不適切な表現があるとの指摘を読者の方からいただきました。⁰熟慮の結果、作中の描写が偏見や差別の助長につながることは避けたいと考え、一部修正しました。
— 少年ジャンプ+ (@shonenjump_plus) August 2, 2021
少年ジャンプ+編集部https://t.co/Vag51clfJc
その上で何かの作品を通じて、彼らへの「会話が通じない」「短絡的に暴力を振るう」といったステレオタイプが強調されることが起きるのではないかという懸念は、当然予想されるものだ。 ただしこの懸念は重要であるものの、作品に対する批判として妥当なものか。とりわけ、斎藤氏がTwitterで要請し、今回集英社が決断に至った「修正」が必要なほどに喫緊の問題なのかは、熟慮の余地がある。
特に考慮すべきなのは、この作品を通じて本当に精神障害者に対する偏見が読者の間で拡張され、現存する精神障害者への憎悪や偏見に繋がりうるものか、という点である。読者全員が共有する表現を「修正する」、言い換えれば、一度作品を破壊し、作り直すに至るだけの根拠があるのか。
当然ながら、客観的に『ルックバック』という漫画作品が、具体的にどれほどの人間に、どれほどの深度でもって、どれほどの偏見を助長したのかという結果を調査することは、わたしを含める誰にもできない。
ただ1つ、『ルックバック』という漫画を論じる上で明らかにしたいのは、143ページという圧巻のスケールと、藤本タツキが描く狂気的なディティールにより、京本と藤野が生きる虚構世界を原初から創造を試みることにより、この悲劇が既に現実的なスケールで論じること自体、難しくなっていることである。
「山形美大生通り魔殺人」の再構築によってなしえる虚構内での悲劇と再生
そもそも、この作品は精神疾患を描こうと試みていない(もっと厳密にいえば、この作品には精神疾患と断定された人間は1人もいない)し、京都アニメーションを襲った惨劇をトレースしていながら、惨劇そのものを描いたわけでない。それは、京都ではなく山形だとか、会社ではなく学校だとか、現実の事件が7月18日ではなく19日だったように、「山形美大生通り魔殺人」という似ているけど、別物として描く「ずらし方」から断言できる。
にもかかわらず、なぜわたしたちは「山形美大生通り魔殺人」にこれほど震え、悲しんだのだろうか。セリフも、感情さえ失った藤野の心境を理解できたのか。それは、藤野と京本という2人の人間のクリエイターとしてあまりにリアルな描写により、2人が実存するかのような親近感と敬意を覚えたからではないか。
実際、『ルックバック』の中盤まで、藤本タツキの驚くほど細やかな心理描写により、わたしたちは藤野と京本への敬意を抱え込んでいた。また、学年新聞における『真実』や『夏祭り』という2人の劇中劇により、わたしたちは藤野と京本という創作者への敬意を少なからず共有した。「藤」と「本」、藤本タツキの名前を分けあって産まれた、ありふれた2人の小学生が、かけがえのない絆で結ばれていく様子を、わたしたちは確かに人間的な親近感で確認した。
そして、京本は殺された。藤野は死にはしなかったが、ほとんど殺された。今しがた、100ページを読んだわたしたちが確認した2人の絆が、今まさに、目の前で粉砕された。
同時に、彼女たちの姿に親近感を覚えたわたしたちにも、強い痛みが走った。現実では存在すらしないはずの2人の人間が死んだ、たったそれだけのことが、どうしようもなく辛かった。京アニの記憶がフラッシュバックすることも確かにあった。しかし何より、わたしにとっては「京本」というかけがえのない人間が殺されたことが、もう2人で漫画が作れなくなったことが、悔しくて仕方なかった。
藤野と京本が、まさに虚構から産まれ、ここまで成長する様子が丁寧に描かれた。同じく藤本タツキによる『ファイアパンチ』や『チェンソーマン』で容赦なく人々が殺されても、読者がその感情の行き場を現実に持ち出せなかったように。京本が殺されたことの悲しみは、虚構に向けられた悲しみは、虚構にしかぶつけようがない。
同時に、「山形美大生通り魔殺人」によってわたしたちが得た悲しみは、2021年7月19日までわたしたちの誰もが知らなかった、藤野と京本にのみ向けられるものだった。藤野と京本は、才能あるクリエイターの象徴であれど、京都アニメーションのスタッフそのものでは決してない。
それでも京本が死んで悲しい、苦しい。その読者の感情は、「かけがえのなさ」は、確かに藤野と京本という2人の人生を見守ったことに起因する、生の、漫画を読んだこの一瞬に得る感情だ。そのようにして一度顔を沈め、再びページをめくったわたしたちが目にするもの、それは藤野が、あるいは藤本タツキや他のクリエイターが、今まさに何かを創らんとする背中(バック)だ。
言い換えれば、藤本タツキは、事件、加害者の描写は頑なに過去を忘れまい、あの悲しみを軽んじるまいという断固たる決意と同時に、ともすれば2年前の事件にあっても人として隠しきれなかった、怒り、憎しみ、はては謂われない精神障害者への偏見を、殺そうという覚悟を、「犯人を蹴り飛ばす」という甘い夢を捨てても液タブへ向かう藤野の背中に預けているのだ。
従って、極めてシビアなバランスでありながら(しかし、シビアであらねばならない)、『ルックバック』は精神疾患に対するステレオタイプを強化するものでも、不条理に対して暴力や差別で報いることを、決して是としていないし、是とするための作品ではない。斎藤氏が懸念する「原因や背景を想像せずにはいられない」という(やや暴力的な)懸念にすら、『ルックバック』は抗うだけの描写を伴っている。
「2019年7月18日」に至る、限りなく現実に近しい世界と人間を143ページかけて作り直すという途方も無い労力の中にこそ実現した、藤本タツキのみ登場人物の人生に破壊と再生を与えうる、悲劇のシミュレーション。ある種、フィクションの力学の極地と言える。
無論この虚構における神の振る舞いは、藤本タツキにのみ許されたものではない。本作が最もリスペクトしたタランティーノ監督の『ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド』においても、その単純かつ痛快な大筋からは想像もできないほど、小道具の1つひとつが入念に1960年代のものを再現し、映画ファンを唸らせるような何重ものメタファーをこらし、演技、編集、カメラどれをとっても余念がない。どこをとっても齟齬のない完璧な映画だからこそ、「虚構の反逆」とも言うべきテーマは結実したのである。

この記事どう思う?
関連リンク
Jini
ゲームキュレーター/ライター/ゲーマー日日新聞主宰
3000万pvブログ「ゲーマー日日新聞」→月額購読者800人のnote「ゲームゼミ」 | 著『好きなものを「推す」だけ』テレビラジオ出演や各紙連載など
・ゲーマー日日新聞
・Twitter
・note

15件のコメント


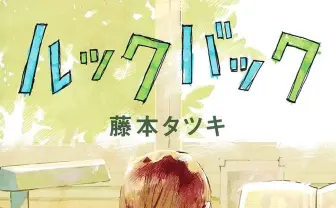
匿名ハッコウくん(ID:8357)
素晴らしい書評だと思います。
日本猿ジュセヨw
この自分の言葉に寄ったような感想文みたいな記事がとにかく気色悪い
匿名ハッコウくん(ID:6103)
https://kakuyomu.jp/works/16816700427029859905/episodes/16816700427029916338