新曲「Pale Blue」制作の裏側を、恒例のYouTubeラジオで米津玄師が話していた。
「今までの人生の中で一番つくるのが大変だった」と米津が語るのは、「恋愛とは何だ?」という自問のドツボにハマってしまったからだという。
それで米津が導き出した解は、「失恋こそが恋愛において本質的なものなんじゃないか?」というものだった。それはいわゆる「さよならだけが人生だ」的な意味では全然ない。
「ような」を強調する米津は「それは錯覚だと思うんですけど」と続ける。恋とは「独りでいることをとことんまで実感させられる体験」だと。「ひとたび恋愛の対象となる人間と出会ってしまうと、その瞬間に半身をもがれたような気持ちになる。自分の人生には初めからこの人が足りなかった、この人がいて初めて個として成立する“ような”気分になる」
(米津玄師 Pale Blue Radio)
奇妙な感覚だ。ここには2つの倒錯が同居している。
「運命の相手」という倒錯が物語を駆動する
まず、「運命の相手がいる」という錯覚。そして、その錯覚さえ描写していない、「もともとは一つだったものが離れ離れになっていた(だから自分は不完全な存在である)」という倒錯。ある錯覚そのものではなく、そこに描かれなかったものを遡及的に確信するという感覚はとても不思議だと思う反面、特定のジャンルを知る人間にとっては親しんだものでもある。
運命の相手がどこかにいるはずだ、というこの感覚。それは、いわゆる「セカイ系」と呼ばれてきた物語および想像力に通じるものだ。 当然ながら、運命などというものは存在せず、運命の相手なんているはずがない。
だから、米津自身が言うように、運命の相手がどこかにいるという感覚は、紛れもなく錯覚だ。そして、その錯覚こそが物語を駆動する鍵になる。
セカイ系の病理をえぐる「Pale Blue」
セカイ系の本質は「『運命の相手がどこかにいるはずだ』という感覚から遡行的に導き出されるファンタジーだ」と、かつてセカイ系的想像力を批評活動の軸に据えてきた東浩紀は説明した。これは東浩紀の『君の名は。』評の一節でもある。
『君の名は。』は、瀧と三葉が名前も知らないながら、お互いに出会った瞬間に運命を感じたラストのあの瞬間を起点に、運命を感じた理由を“可能世界”という形で描いてみせたファンタジーなのだと東は言う。
ひとつ繰り返しておきたいのは、あの作品は運命の相手と結ばれる作品では【なく】、なぜ人々が運命の相手がいると思い込んでしまうのか、その理由こそが語られた作品だということです。この読みの背景には「ゲーム的リアリズム」があるのですが・・でもこれもツイッターでは説明不可能ですね(笑)
— 東浩紀 Hiroki Azuma (@hazuma) September 4, 2016
米津玄師がセカイ系? きっとほとんどの人がこじつけだと思うだろう。運命の相手なんていないんですよ。ただ「運命の相手がいるはずだ」という感覚だけがある(これはもっているひとともっていないひとがいる)。そこから遡行的に見いだされるファンタジーがセカイ系の本質です。
— 東浩紀 Hiroki Azuma (@hazuma) September 4, 2016
セカイ系には「ワタシとアナタ」だけがあって、そこでは世界への想像力が欠如しているということがしばしば指摘される。
もっと言えば、そのファンタジーにおいてはあくまで「ワタシ」が「こうしたい」という感覚がすべてで、究極的に言えばそこには「アナタ」さえいない。
一字一句引用しているこれは、間違いなくこの2021年に米津玄師が自作を解題するために「恋愛」について語った言葉であるのと同時に、セカイ系およびその本質的な病理へのメタ的な言及として読み換えてもほとんど違和感のない説明でもある。「世界では自分とアナタしかいないんじゃないかという誇大妄想」「恋とは相手に要請する力で、突き詰めて考えると、相手のことは至極どうでもいい(中略)そういう倒錯状態を恋と呼ぶのではないか」
(米津玄師 Pale Blue Radio)
屈託のない新海誠と、ズレを抱えたまま生きる米津玄師
東浩紀の言葉を借りれば、敗戦国である戦後日本は、敗戦と占領によって「言葉と現実、文学と政治、理想と実践のあいだに大きな『ねじれ』を抱え込んでしまった」(『ゲンロン4 現代日本の批評III』所収「批評という病」より)。三島由紀夫も村上隆も宮崎駿も、日本の文学も批評もアニメも漫画もそのほとんどがその磁場の中にあると。たしかに、自分が惹かれる作品には、物語(あるいは言葉)と現実とはいつもどこかがズレているという葛藤が必ず刻まれてきた。
米津の自作への言及は、他ならぬ彼自身がこの磁場の真っ只中にいて、なおかつそれに限りなく自覚的であることの告白に聞こえてしまった。
不可逆な別離を、切り分けた果実の片方を失ったと表現した「Lemon」にわかりやすいが、運命を信じようとするからこそいつもあらかじめ何かが失われているという米津の倒錯的な世界観は、彼がまだ「ハチ」を名乗っていた頃の「WORLD'S END UMBRELLA」や「clock lock works」などにも強く表れてきた。
米津玄師は今も、そのズレを抱えたまま、なぜか国民的音楽家として生きている。
これは別にどちらが良い悪いの話ではなく、ただ、ある種のズレを抱え続ける想像力がかつて日本のあらゆる文化に根ざしていた。
戦後日本に横たわり続けたこの言葉と現実とのズレは、批評史の中では東浩紀が言うように柄谷行人が抱えて続けてきたものだし、個人的には「言葉こそが苦しみの原因で人間を俗世に縛るものだ」と考える仏教思想にも通じるものに感じる。
言葉と現実との乖離に苦しみ続けた三島由紀夫の遺作『豊饒の海』シリーズがなぜ仏教色の濃い輪廻転生の物語でなければならなかったのか。自分なりにようやく腑に落ちてきた。
同時に、そうかだから自分は米津玄師に惹かれ続けてきたんだという強い納得もあった。
三島由紀夫と米津玄師、50年の時を経た共時性
米津玄師が仏教的価値観に強く影響されているのも納得がいく。仏教において、一つとして変わらないものはないのが諸行無常で、実体のない無こそが本質だというのが色即是空で、人の一生は連続する刹那だ。それで先日、米津玄師がインスタライブで最近読んだ本として東浩紀の『ゲンロン戦記』を挙げてたそうでマジでビビった。見てねえよインスタライブ! アーカイブしてくれ!!
三島由紀夫と東浩紀と米津玄師が同一線上に並んだこの瞬間の興奮よ伝われ。ゲンロン戦記が妙に検索で引っかかるなと思っていたら米津玄師氏が読んだと公言したのね。じつは彼はむかし僕の読者だったという説があり、読んでくれたら響くのではないかと思っていたので光栄です。
— 東浩紀 Hiroki Azuma (@hazuma) June 21, 2021
1967年、当時80万部を誇った若者向けの人気雑誌『平凡パンチ』で行われた「現在の日本でのミスター・ダンディ」要するに今で言う「日本のカリスマ男性」を決める読者投票で、並みいる俳優やスポーツ選手をおさえて三島由紀夫が1位に輝いた。
三島は50年前、間違いなく日本のスターだった。一介の小説家がそんな評価を受けていた時代なんて、今では想像しづらい。でも、米津玄師がスターとなっている現在も同じくらい特別な時代であることは、ここまで読んだ人には多少は伝わるのではないか。
大げさに言えば、そのことは、この国の数少ない希望の一つであるように思う。
KAI-YOU Ptremium編集長・新見のコラムを読む
ディープに読み解くポップカルチャー

この記事どう思う?
関連リンク
2件のコメント


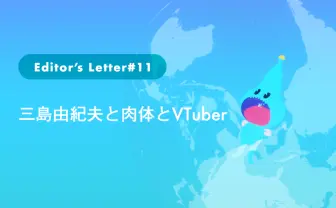

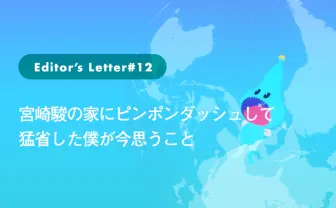
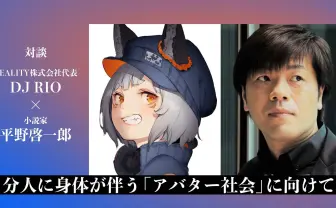





匿名ハッコウくん(ID:12759)
浜崎あゆみ part of me で とっくに歌われたテーマですね
匿名ハッコウくん(ID:4563)
面白く拝見いたしました。敗戦国であるが故の肩身のせまさ。
言語を奪わない代わりにアメリカ製品市場としての支配。糖質ダイエットと称して米を食べない日本人はアメリカの思うツボ