TCGは金になる──ポケカバブルの背景、ONE PIECEカードゲームの成功戦略
『ポケモンカードゲーム』、『遊☆戯☆王オフィシャルカードゲーム』、『デュエル・マスターズ』の3タイトルを「2025年現在も、国内トップクラスの市場シェアを誇る」と述べたが、このうち『遊☆戯☆王オフィシャルカードゲーム』と『デュエル・マスターズ』の2タイトルと、『ポケモンカードゲーム』とでは、辿ってきた道のりがやや異なる。
前者の2タイトルは発売後から長期間にわたりトップクラスの売り上げを維持してきたが、『ポケモンカードゲーム』はリリース直後のブームが落ち着いた後、あまり目立たない時期があったのだ。
国内のTCG市場を売上額で見ると、2010年代の大部分は『遊☆戯☆王オフィシャルカードゲーム』と『デュエル・マスターズ』がTier 1で、その下に『ヴァイスシュヴァルツ』や『カードファイト!! ヴァンガード』といったブシロードタイトルや『バトルスピリッツ』がTier 2、『ポケモンカードゲーム』はさらにやや下のTier 3集団に属していた。
『ポケモンカードゲーム』がTier 1に匹敵するほどの売れ行きを見せ始めたのは、2018年ごろからである。その正確な理由は明らかではない。
2018年にYouTuberはじめしゃちょーが取り上げたことがきっかけだとする説もあれば、2017年に『遊☆戯☆王オフィシャルカードゲーム』で行われたルール改訂により、プレイヤーが移行してきたとする説もある。さらに、安価で魅力的な「GXスタートデッキ」など、巧みに設計された商品構成も、要因の一つと考えられる。
いずれにせよ、こうした複合的な要因によって『ポケモンカードゲーム』は急速に売り上げを伸ばし、瞬く間にTier 1に追いついた。
そして、ここで新型コロナウイルス感染症の流行が世界を襲う。余った時間とお金の一部はTCG、特に『ポケモンカードゲーム』に流入。ギャンブル的な購入や投機目的の売買も横行し、『ポケモンカードゲーム』の売り上げはさらに急増。Tier 1を大きく飛び越え、Tier 0とも言うべき状態に至る。
本記事の冒頭で、カードゲームの売り上げが「2020年度の1222億円から、わずか2年で倍増」していると述べたが、この増分の多くが『ポケモンカードゲーム』の躍進によって説明できる。『ポケモンカードゲーム』は信じられないほど売れており、あらゆるゲームの中でも、国内売上が最も大きいタイトルの一つになっている。
なお、新型コロナウイルス感染症が流行する以前、YouTuberヒカルのオリジナル楽曲『俺たち金持ちYouTuber』(2018)には、以下のような歌詞がある。
そうさ俺たち 金持ちユーチューバー
金を使うのを みんなが見たいのさ
競馬、競艇、宝くじ、カードゲーム
買えば買うほど 金入るのさヒカル『俺たち金持ちYouTuber』より
この時点ですでに、一部のYouTuberは「開封動画」をコンテンツとしており、この流れがコロナ禍によって顕著になった、というのが正確な理解だろう。
このように『ポケモンカードゲーム』が強烈な成長を遂げたことで、TCGを販売していた企業は、TCGが持つビジネス上のポテンシャルに改めて気づくこととなった。
数多あるキャラクターグッズの一つとして制作・販売するのではなく、長期運営を前提とし、多くの予算をかけ、高品質なものをつくり、競技大会なども含めた大規模なプロモーションを行えば、数百億円の収益を上げるチャンスがある。
そうした中で登場し、瞬く間にTier 1の仲間入りを果たしたのが『ONE PIECEカードゲーム』(2022)である。同タイトルを販売するバンダイのプロデューサー座談会が、ムック本『カードゲーマー スペシャル Vol.2』(2023)に収録されているが、そこには次のような興味深い発言がある。
「でも正直に言うと、バンダイには作品の力だけでカードゲームが売れるだろうと思い込み、失敗してきた過去があります。」
「その意識が変わってきたのは、ここ数年ですね。売ったらそこで終わり、という考え方が古いというのが、ようやく社内に浸透してきました。」『カードゲーマー スペシャル Vol.2』(2023)
これらの発言が示すとおり、『ONE PIECEカードゲーム』をはじめとするバンダイの新作TCGは、洗練されたゲームシステムとビジュアルを備え、リリース直後から全国規模のイベント施策を精力的に展開している。こうした傾向は、バンダイに限らず、他の大手パブリッシャーが手がけるタイトルにも共通して見られる。
こうして、国内のTCG市場は新たな局面に到達した。新しくリリースされるタイトルの数が急増したわけではないものの、ゲーム・ビジュアル・イベント施策で高いクオリティを持つタイトルが増え、売り上げも伸び、二次流通価格が高騰するカードが増加し、良くも悪くもTCG市場全体が“バブル”に沸いている。
『Shadowverse EVOLVE』(2022)、『ユニオンアリーナ』(2023)、『ドラゴンボールスーパーカードゲーム フュージョンワールド』(2024)、『名探偵コナンカードゲーム』(2024)、『ディズニー・ロルカナ・トレーディングカードゲーム(日本語版)』(2025)などが国内の話題作だ。
『デュエルボーイ』の可能性──ゲームデザイナーが予想するTCGの未来
今後、TCGの世界はどうなっていくだろうか。筆者の予想をいくつか挙げてみたい。
まず考えられるのは、インディーTCGの増加である。これまでも『フラグメントディグレイン』(2018)など、インディー・小規模開発によるタイトルが長期間にわたり新カードのリリースを継続した例は存在していたものの、TCG市場の拡大、クラウドファンディングの普及、そして生成AIの普及により、今後はこうした小規模開発への挑戦が一層活発になると考えられる。
生成AIの利用については賛否があり、従来型の企業が直接導入することは難しいと思われるが、TCGの開発において最も費用がかかるのがイラストであることも否定できない。資金のないチームや個人開発者が、イラスト生成AIをTCG開発に導入する事例はすでに見られ、今後も増えていく可能性が高い。
一方、既存のTCG開発・販売企業がAIを導入するとすれば、それはゲームデザインの領域になるだろう。
『Magic: The Gathering』『ポケモンカードゲーム』『遊☆戯☆王オフィシャルカードゲーム』『デュエル・マスターズ』といった著名タイトルはすでにすべてデジタル化されており、AIによるプレイが可能である。もしAIが高精度で人間に近い挙動を実現できるようになれば、バランス調整のためのプレイテストをAIに代行させることができる。
この種の研究が進められていることは、いくつかの企業が技術者向けカンファレンス(外部リンク)や、プレイヤー向けのイベントで公表している(外部リンク)。
将来的にこのような技術が実用化されれば、バランス調整のコストは大幅に削減され、TCGのゲーム面における品質がより安定する一方で、「面白いTCGとは何か?」「プレイヤーが好むカードはどのようなものか?」といった高度な問いが、ゲームデザイナーにとってより重要になっていくだろう。
次に考えられるのが、扱われる題材のさらなる拡大である。『hololive OFFICIAL CARD GAME』(2024)や、『デュエル・マスターズ』の拡張パック『にじさんじコラボ・マスターズ「異次元の超獣使い」』(2025)など、VTuberはTCGの題材としてもその勢力を拡大している。
また、TCG漫画をSNSで連載するインフルエンサーによるクラウドファンディングから生まれた『アニマルカードゲーム』(2024)など、インディーTCGの増加に伴い、TCGが取り扱う題材は今後ますます広がっていくだろう。
制作や情報発信のハードルが下がるにつれ、視聴者・プレイヤー・インフルエンサー・クリエイターといった立場の境界も曖昧になりつつある。
こうした流れは、さまざまなゲームジャンルやエンタメ全般に共通して見られる。なかでもTCGは、紙とペンさえあれば新しいゲームやカードを創作できるため、コミュニティ主導の自主制作や改造との相性が非常に良い。実際、『Magic: The Gathering』では、プレイヤーが自発的に考案したオリジナルルール「統率者戦」が、現在では人気フォーマットとして広く定着している。
こうしたDIY的な創作活動は、今後TCG文化のなかで、さらに顕著な広がりを見せていくかもしれない。
最後に、興味深い小規模開発タイトルを紹介しておこう。『デュエルボーイ』(2022)は、アナログゲームの即売イベント「ゲームマーケット」で販売されたタイトルで、当日に会場で遊ぶことを前提としたその時限りのパックを購入する「一日遊びきり」のゲームである。
ゲームマーケットで販売された『デュエルボーイ』(2022)
初回販売で好評を博した『デュエルボーイ』は「ゲームマーケット」の公式イベントとなり、複数タイトルとのコラボバージョンもリリースされている(外部リンク)。
こうしたリプレイ性の優先順位を下げたゲームは、『Fortnite』(2017)などにおける「ワンタイムイベント」の延長線上にある「ワンタイムゲーム」として、今後より大きな注目を集めていくかもしれない。将来、このような斬新なタイトルがいくつも現れることに期待したい。
では、TCGは参入困難な寡占市場なのか? いや、そうではない
この記事では、TCGの歴史を振り返ってきた。筆者は25年以上にわたりTCGをプレイしており、また、仕事としてもTCGの開発・運営に携わっている。その立場から見ても、近年のTCG市場の盛り上がりには、やや過熱気味な印象を受ける。
TCGは、プレイヤーが増えるほど楽しさが増し、さらに人口が増加するという、いわゆる「ネットワーク効果」の強いゲームジャンルである。一方で、人口が減少すれば楽しさも減り、加速度的にプレイヤーが離れていくこともある。
事実、人気を得られないまま運営を終えるタイトルも少なくない。前述のとおり、数多く存在するTCGタイトルのなかで、長期的な運営を実現できるものはごくわずかであり、"5年継続率"は10%を下回ると推測される。
では、TCGは歴史のある著名タイトルや、大きな資本を持つ企業のタイトルに対し、参入の困難な寡占市場なのだろうか。筆者はそうは考えていない。
ここで言う「人口」とは、実際には自分の身の回りにいるプレイヤー、つまり「人口密度」である。自分の視界の外にいくら多くのプレイヤーがいても、それが直接意味を持つとは限らない。逆に、身近な環境に熱心なプレイヤーが十分いれば、楽しく遊ぶことができる。仮に世界にプレイヤーが30人しかいなくても、その全員が自分の友人であれば、そのタイトルは自分にとっての“覇権タイトル”なのだ。
例えば、プレイヤーの分布する場所や時間を意図的に限定することで、楽しい体験を成立させている好例が、前述の『デュエルボーイ』である。
TCGに必要なのは、単なるプレイヤー数ではなく、その活動の「密度」であり、その実現にはコミュニティやプレイヤーの熱意が欠かせない。ターゲットに適したルールデザインやプロモーション施策など、コンセプトの一貫性も、その一助となるだろう。
いずれにせよ、運営の継続性という観点からは、ただプレイヤー数や売り上げを追い求めるのではなく、人口密度の高い、活発なコミュニティを育てることを目指すべきである。
どれほどプレイヤー数が多かろうと、最終的にタイトルを支えるのは、人と人との関係である。プレイヤー一人ひとりに愛されるタイトルとなることを、TCGの開発・運営者は目指すべきだと筆者は考える。
現状のTCG市場のこの盛り上がりは、いずれ落ち着く時が来るだろう。そして世間では「バブル崩壊」といった言葉が使われるかもしれない。しかし筆者は、TCGというゲームジャンルそのものが衰退することは、当面はないと確信している。この記事で見てきたとおり、TCGは豊かな歴史を持つだけでなく、今まさに新たな潮流やコミュニティが生まれ、成長を続けている文化である。
筆者自身、TCGを通じてかけがえのない思い出を得るとともに、数多くの友人にも出会ってきた。もしこの記事を読んでいる方の中に、まだTCGを体験したことのない方がいらっしゃるなら、ぜひ一度、その広く深い世界に足を踏み入れてみてはいかがだろうか。
参考文献
『ユーロゲーム ― 現代欧州ボードゲームのデザイン・文化・プレイ』ニューゲームズオーダー(2021)スチュワート・ウッズ (著), 沢田 大樹(翻訳), 山本 拓(翻訳)
『ポケモン・ストーリー』日経BP(2000)畠山 けんじ (著), 久保 雅一 (著)
『煽動者 徹底プロモーション 仕掛人の哲学』ホビージャパン(2013)木谷高明 (著)
『カードゲーマースペシャル Vol.2』ホビージャパン(2023) ゲームメディア編集部 (著)

この記事どう思う?







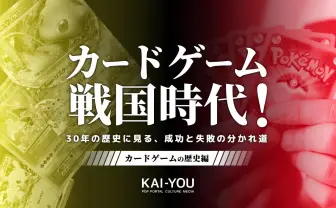
0件のコメント