1000を超える世界のTCGタイトル
ここまでは、国内TCG市場の流れを、主にIP活用の視点から見てきた。しかし、ここで紹介したタイトルは、世界に存在するTCGのうちほんの一握りに過ぎない。
国内でリリースされたTCGをまとめたサイト「ジャガーノーツのTCGカタログ」には、300以上のタイトルが掲載されている(外部リンク)。また、Wikipedia日本語版の「トレーディングカードゲームのタイトル一覧」には、180以上のタイトルが掲載されている。
これらのうち、「5年以上新規カードの開発・出版を継続した」ことを筆者が把握できたタイトルは35タイトルのみである(表1)。
35タイトルのうち、10年以上にわたり開発・出版を継続した、または2025年現在も継続しているタイトルは20あり、新規タイトルが苦戦しやすい一方で、一度定着したタイトルは長寿化しやすい傾向が見て取れる。
新規タイトルの定着が難しいのは、海外でも同様だ。ボードゲームのデータサイト「BoardGameGeek」のデータベースで、「Card Game(カードゲーム)」「Collectible Components(収集可能なコンポーネント)」に該当し、「Expansion for Base-game(拡張セット)」に該当しないタイトルを検索すると、英語圏のタイトルを中心に1000件以上がヒットする(外部リンク)。また、Wikipedia英語版の「List of collectible card games」には、400以上のタイトルが掲載されている。
これらのうち、営利目的での開発・出版が5年以上継続したと把握できたTCGは44タイトルに過ぎない(表2)。
『Shadowfist』(1995、2000、2006、2013)や『Deadlands: Doomtown』(1998、2014、2018)など、開発・出版が一度打ち切られたあとに別の企業が版権を取得し、開発・出版を引き継ぐケースが見られるのは、海外ならではの特徴だ。
開発・出版を引き継ぐのは企業だけでなく、『Star Trek Customizable Card Game』(1994)や『Star Wars Customizable Card Game』(1995)では、プレイヤーのサークル(継続委員会)が開発を引き継ぎ、新カードの印刷用データを無償公開している。
『Star Wars Customizable Card Game』(1995)
さらに、海外では、『Legend of the Five Rings』(1995、2017)や『A Game of Thrones: The Card Game』(2002、2008)のように、版権を取得した企業が、当初TCGとしてリリースされたタイトルを、固定カード販売方式(ランダムパックではなく、固定セットを販売する形式)にリメイクするケースもある。Fantasy Flight Gamesは、固定セット販売方式のTCGを「Living Card Game(LCG)」と名付け、過去の人気TCGをリメイクしたLCGを多数リリースしている。
なお国内では、ほぼ唯一、ホビージャパンが自社タイトル『ラストクロニクル』(2013、2022)を固定セット販売方式にリメイクした事例がある。
また、海外では『Vampire: The Eternal Struggle』(1994)や『Call of Cthulhu: The Card Game』(2004、2008)など、ロールプレイングゲームを題材にしたタイトルが多く見られるのも、日本との違いの一つだろう。
「BoardGameGeek」やWikipediaには、重複登録やTCGとは言えないタイトルの掲載も見られるが、各種サイトの情報を総合すると、累計1000以上のTCGが存在している可能性が高い。長期間にわたってカードをリリースし、多くの人に認知されているタイトルは、ごく一部の「成功者」のみと言える。
TCGの歴史は、『ハースストーン』以前・以後に分かれる
TCGは紙のカードを使って遊ぶジャンルとして誕生したが、パソコンやゲーム機などのデジタル端末を用いたTCG(以下、DTCG)も、1997年の『Chron X』を皮切りに、さまざまなタイトルが登場している(なお、『Chron X』は「First online trading card game」(世界初のオンラインTCG)として、ギネスに認定されている)。
DTCGには、『Magic: The Gathering』のようなアナログTCGをデジタル化したタイトルと、完全オリジナルのタイトルがある。また、アナログTCGと同様に仮想のカードパックを販売するタイトルと、ソフトウェアの利用権のみを販売する買い切り型のタイトルがある。
デジタル化・パック販売型タイトルの代表例は、『Magic: The Gathering』のデジタル版『Magic Online』(2002)だ。これらのタイトルは、元のアナログTCGをインターネット上でプレイ可能にすることを主目的としており、継続的なアップデートによってその内容を忠実に再現し続けることが期待される。
それに対し、デジタル化・買い切り型タイトルは、アナログ版のチュートリアルとして設計されていることが多く、ストーリーを進めながらCPUと対戦できるソロプレイモードが充実している傾向がある。
『ポケモンカードGB』(1998)、『遊☆戯☆王デュエルモンスターズ』(1998)は、いずれもゲームボーイ用ソフトとして100万本以上の出荷を記録した大ヒット作である。ゲームボーイ向けタイトルが多かったのは、携帯端末が各プレイヤーの手札を隠すのに適していたという事情もあるだろう。
DTCGオリジナルタイトルにはさまざまなものがあり、パック販売型には前述の『Chron X』や『PoxNora』(2006)、『Shadow Era』(2011)などがある。
また、老舗ゲーム企業であるSEGAは、『WORLD CLUB Champion Football』(2002)、『甲虫王者ムシキング』(2003)、『三国志大戦』(2005)などのアーケードゲームに、トレーディングカード要素を導入。2013年には、従来のTCGに近いルールを持つアーケードDTCG『CODE OF JOKER』をリリースするなど、独自の路線でDTCGの可能性を切り開いた。
一方、買い切り型のオリジナルタイトルによく見られるのは、別のジャンルのゲームにTCG要素を組み合わせたタイプである。ボードゲーム『モノポリー』とTCGを融合させた『カルドセプト』(1997)、アクションゲームにTCG要素を加えた『バトルネットワーク ロックマンエグゼ』(2001)や『キングダムハーツ チェインオブメモリーズ』(2004)などが広く知られている。
パック販売型で挙げた『PoxNora』も、ストラテジーゲームにTCG要素を加えており、こうしたオリジナルのDCGは総じて、アナログTCGでは実現困難なルールを用いる傾向がある。
ストラテジーゲームのようにパラメータの種類が膨大なジャンルや、アクションやリアルタイムストラテジー(RTS)のようなリアルタイム性の高いジャンルは、アナログTCGと相性が悪い。「TCG」とは言えないが『クラッシュ・ロワイヤル』(2016)も、RTSとカードゲームを掛け合わせている。
このように、ゲームジャンルとしては古くからあるDCGだが、『Hearthstone(ハースストーン)』(2014)以前は比較的ニッチな存在だった。DTCGが対戦ゲームの代表的なジャンルの一つとなったのは、『Hearthstone』以降のことである。
原作IP『Warcraft(ウォークラフト)』シリーズ(1994)の人気に加え、Blizzard Entertainmentのブランド力やプロモーション力も相まって、『Hearthstone』は瞬く間に世界中で人気を博し、DTCG市場を1タイトルで急拡大させた。
『Hearthstone』は、売上額だけを見ればアナログTCGも含めたTCG全体の中で突出した存在とは言えないが、『Shadowverse』(2016)、『The Elder Scrolls: Legends』(2017)、『ドラゴンクエストライバルズ』(2017)といったフォロワーのリリースや、『遊戯王 デュエルリンクス』(2016)、『Magic: The Gathering Arena』(2019)、『デュエル・マスターズ プレイス』(2019)、『遊戯王 マスターデュエル』(2022)、海外でのみ展開されている『Pokémon TCG Live』(2023)など、人気TCGのPC・スマートフォン向けデジタル版のリリースを引き起こした。
『Magic: The Gathering』の競技大会制度が『Magic: The Gathering Arena』と統合された(2019~2021)ことからもわかるように、TCGのデジタル化の波はアナログ側の運営方針にも影響を及ぼしている。
『Magic: The Gathering』は、ゲームデザインの方針もデジタル側の影響を受けており、TCG市場全体が『Hearthstone』およびDTCGの普及による影響から逃れられなくなっている。デジタル化の影響は今後もさらに拡大する可能性が高く、「TCGの歴史は『Hearthstone』以前・以後に分かれる」と言えるほどだ。『Hearthstone』の登場は、『Magic: The Gathering』以来、TCG界における最大の出来事であると筆者は考えている。
それまでのDTCGが、アナログTCGを忠実に再現するか、あるいはアナログTCGでは実現しにくい要素を追加することを志向したのに対し、『Hearthstone』が画期的だったのは、DTCGとの相性が悪い要素をアナログTCGから取り去るアプローチをした点だ。
『Hearthstone』は、従来のアナログTCGと比べてシンプルなルールを採用しており、これほどシンプルなDTCGは特異な存在であった。

この記事どう思う?







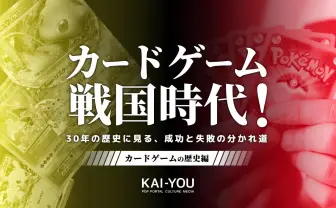
0件のコメント