恣意的に記録されうるバーチャルタレントの歴史
映画から「劇場アニメ」を無視するような態度には「恣意的な思想を入れるな」という批判がありうると先述したが、「興味のないものは興味がないという理由でVTuberの歴史に含めようとしない」という態度は実際にあるものだ。わかりやすい例としては、今年12月に劇場公開された映画『HoneyWorks 10th Anniversary “LIP×LIP FILM×LIVE”』がある。
電脳少女シロが主演の映画『白爪草』(2020年9月公開)もミニシアター上映されているが、並べて記憶されてもいいところだろう。
客観的に考えてみて、二次元キャラクターに近い立ち位置の「LIP×LIP」はともかく、活発にライブ配信を行い、YouTubeチャンネルを持つ「あすかな」をVTuberやバーチャルタレントではないとする合理的な理由は、様々な例外と照らし合わせると、筆者には見出だせない。
HoneyWorksの楽曲は「可愛くなりたい」や「ファンサ」など、歌ってみたの定番曲としてVTuberの需要も高いのだが、不思議と「ファン層が異なる」空気があるのか、HoneyWorks自体が話題となる印象は確かに薄い。
ただ、『LIP×LIP FILM×LIVE』のこうしたキャッチコピーに対して、バーチャルタレントの歴史が無視を行うとしたらなかなか奇妙なものだ(試みに、ネット上の「VTuber年表」やVTuberニュースサイトなどで関連キーワードを検索してみてほしい。バーチャルジャニーズが始動した2019年以外、ほぼ言及されなくなっているはずだ)。いま、バーチャルアイドルの歴史は更新された。
この映画で、僕らは時代を変えていく──。 『LIP×LIP FILM×LIVE』オフィシャルサイトより
仮に「主なファン層で話題にならない、客層の異なるものは無視してよい」という民主的な基準が通用するならば、やがては「大手企業のタレント以外はVTuberとして取り上げない」という潮流を招くのと同じことになる。現在でも、第一世代とも言える「古参VTuberファン」と、多くの外国人を含む新規世代の認識は齟齬が広がっていると言えるのだから。
見方を変えれば、男性VTuberの躍進が難しいのはHoneyWorksの女性ファンの取り込みができていないから、とも言える。
取り込みができていないから「あすかな」を別物として扱ってしまうのか、同じバーチャルタレントとして扱う文化になっていないから取り込めないのか、順番は逆かもしれないが。
そこには、2017年頃の「キズナアイに似ていればVTuberとして認知される」文化が、今は「メディアの報じられ方やコラボ関係を通じてVTuberの仲間として認められる」文化へと変化している、という指摘もできる。
元は二次元キャラクターで、声優もいる「VTuber可憐」や「VTuber言葉」がVTuberとして受け入れられやすかったのは、ネットトレンドの親和性や、「周防パトラと『ぶいおん!!』で共演した」などのコラボ実績に支えられていると言えるのだ(「バーチャル受肉したイラストレーター/クリエイター」がVTuberの仲間入りするのもこの傾向を持つ)。
興味深いのは、バーチャルアイドルとして2020年はTVアニメ、冠番組のseason2の放送、スマホゲーム化、シングルはオリコンウィークリー2位を連続獲得、そしてバーチャルYouTuberとしてのチャンネル再稼働などのニュースが続くなかで、アニメ・ゲームや音楽系のニュースサイトだけで情報が記事化されていたことだろう。
二期合わせて117週放送された冠番組「22/7 計算中」はソニーミュージック系のアイドルらしく「乃木坂工事中」などと同じ制作会社によるアイドルバラエティ番組だが、共演する芸人やその周囲のオタク芸人から見て「アイドル番組」としての評価がそもそも高く、一般に勧めやすい番組になっていた。
ところでVTuberというジャンル自体、オタク界で流行しているように見えて、実際は「二次元オタク」からしても「顔出しのアイドルや声優のオタク」からしても違和感を根強く持たれており、その中間的な波長に合うタイプだけがハマりやすいという人を選ぶ性質がある。言い方はよくないが、これらは「オタク同士で毛嫌いし合う」ような関係が現実にあり、そのオタク内における好みの構造だけでも別に論じる価値がありそうなのだが。
そう考えると、VTuberシーンにも二次元とリアルのグラデーションはなるべく大きな振れ幅があったほうが裾野は広がりやすいはずで、意図して無視を続ける行為にも合理的なメリットが見当たらないのだ。つまり単なる好みや、関心の差で決められることを「恣意的」と呼んでいる。
改めて強調すると、どんな総括をしようと「抜け落ちる情報」がある。ただ、VTuber文化に対するアバター文化がそうだったように、ジャンル内の細分化が洗練されていないことで各部分が見えにくくなっていくのだ。
特に、今は「コラボしそうな可能性のある範囲だけをVTuberの文化圏だと考える」という排他的な意識がとても高まっている状況にあるように思えるが、果たしてその既得権益層だけが勝ち残っていきそうな「VTuberシーン」とは、将来のVTuber文化に望まれているのだろうか? もし長く付き添い続けるとしたら、強く問い直してみてほしい問題なのだ。
2020年のVTuberシーンで起きた印象的なトピック

この記事どう思う?
4件のコメント








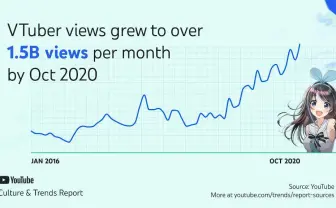
匿名ハッコウくん(ID:4362)
女性Vの場合、真面目だったり清楚よりかは、大体は下品でエロくて気易くて身近に感じられて勘違いさせてくれるVが皆好きだよな。にじホロが人気なのはそこ。絵も今どきの萌え萌えしてるものでロリやエロいものが多いしなー。キモオタの趣味ごった煮したのが強いんよ。
匿名ハッコウくん(ID:4318)
Vtuberといっても結局はその中身の魅力に人が集まる
匿名ハッコウくん(ID:4276)
ホロライブの事しか内容が書かれていなくて、比較対象がないからよくわからない。