インディーゲーム、VTuber、TRPG…新世紀を切り開く「同人」という魔法
2021.01.27
現実の代替としてではない“仮想空間”という場所。
※本稿は、2020年8月に「KAI-YOU.net」で配信された記事を再構成したもの

クリエイター
この記事の制作者たち
新型コロナウイルス感染症(COVID-19)が広まった2020年以来、各地のイベントが中止や延期を余儀なくされるなか、加速度的に注目を集めるのがVRの技術、そしてバーチャル空間だ。
仮想現実で様々なイベントの代替開催がなされ、イベントの開催スペースとしての価値に目を向けられる一方、クリエイターたちの創造性が披露される場所としての価値も広まりつつある。
KAI-YOUではバーチャルYouTuber(VTuber)のミソシタさんが制作したバーチャルワールドを紹介。
ミソシタさんの創造性が存分に披露されたサイケデリックな色彩に満ち溢れたワールドは、訪問者にシュールでポップな印象を与える。
一方で、空間設計と音楽との融合を目指す表現においては、これまでにもVTuberたちのVRライブやバーチャルSNS・VRChat上はもちろん、ゲーム制作の現場などでも多くのクリエイターが活動してきた。
今回、ミソシタさんと同じくVR空間上でのポエトリーリーディングを中心に活動してきたVTuberのキヌさんとの対談を実施。
キヌさんはVR上での音楽イベント「アルテマ音楽祭」でのパフォーマンスの他、リアルウェアとアバターウェアのコレクションを展開するファッションレーベル「chloma」のバーチャルストアのワールド制作などを手掛けてきた。
本対談後、2021年に開催されたサンリオ初のバーチャル音楽フェス「SANRIO Virtual Fes in Sanrio Puroland」で披露された「voices feat.kinu」も話題に。
バーチャル空間とそこで鳴る音楽を活動の中心に据える二人に、表現としてのバーチャルワールドについて話を聞いた。対談は、ミソシタさん制作のワールド「CRAZY POP」で行われた。
目次
- ミソシタとキヌが語る、表現の場としてのバーチャル空間
- 日本的/海外的なバーチャル表現の違い
- コロナ禍がもたらした、バーチャル空間の加速的な発展
- 仮想現実は、本当に現実の代替となり得るのか?
- 「バーチャルワールドクリエイター」を名乗ること
- 表現と交流──バーチャル空間との向き合い方
- さらに「バーチャル」が拡がっていくとしたら?

キヌさん
──そもそも、お二人がバーチャル空間を音楽表現の場として選んだのはなぜですか?
キヌ クリエイターのねこますさんの存在に衝撃を受け、以降もミソシタさん達先輩方を見て、バーチャルの創作活動に興味を深めました。
特に2018年に「VRアートイベント」でらくとあいすさんという方が演奏しているのを見て、今すぐにでもVRでつくりたいという衝動に駆られ、とにかくテンションが上がりました。
最初は音楽制作を中心にしていましたが、そこからワールドをつくるようになり、どんどんVRの制作に重心が移っていった感じです。
曲をつくるときや聴くときって、頭の中にその音楽の「空間」ができると思うんです。
VRでは、これまで自分の頭の中だけにあった「空間」を、自分で制御してつくることができる。バーチャルライブを観て、感動して、それを自分でもガンガンつくっていこうと思いました。
ミソシタ 僕も音楽つくる時はビジュアル先行というか……。

ミソシタさん
ミソシタ ポエムにトラックを合わせた「ポエムコア」という音楽をはじめたきっかけも、もともと曲をつくろうと思ったのではなく、自主制作アニメーションの音声コンテのようなものをつくるためでした。
学生のころから2Dの手書きアニメをつくっていたのですが、手書きだとアイデアが浮かんでもそれを思いのままに表現することが難しかったんです。だから、思いついたことを自分の肉声だけで記録するってのをしてて。
それに音楽をつけてつくっていたやつが「ポエムコア」っていうものに発展していったという過程がある。
そのころから世界観をつくるのが好きだったので、音楽をつくろうっていうよりも世界観自体をバーチャル空間上につくりたいなっていうのが強かったですね。だから僕にとって、ワールド制作はその音楽からできたものをビジュアルに落とす作業って感じです。
──ビジュアル先行という点で共通項がありますね。お互いの音楽やワールドについて、どのように感じましたか?
この記事の続きを読むには
あと8435文字/画像10枚
アカウントを作成
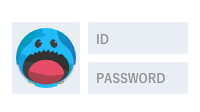
お支払い情報を入力
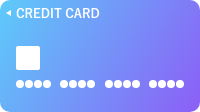
サブスク登録完了!

バーチャルライブの演出において何を大事にするか
様々なジャンルの最前線で活躍するクリエイターや識者を中心に、思想や作品、実態に迫る取材をお届け
様々な記事の中から編集部で厳選したイチオシ作品をご紹介