「恋愛」誕生秘話──なぜ「恋」と「愛」が日本で結びついたのか?
──では改めて、明治時代になって「恋愛」という言葉が誕生したと言われていると思います。この言葉はどのようにして生まれたのでしょうか?佐伯順子 明治18〜19年に、坪内逍遥『当世書生気質』で、“Love”の翻訳として「愛」や「色」や「情け」といった言葉が試験的にあてはめられてゆく過程で、「よっぽど君をラブしている」というフレーズが出てきます。おそらく当時、“Love”に相当する日本語が坪内逍遥としてもうまく見つからなかったので、「ラブしている」という表現を使いつつ、それに「愛」という漢字を当てました。それが一番初期の段階です。
明治20年代になると、さきほども触れた北村透谷の有名な「恋愛」論が女性雑誌や文学作品を通じて広まっていきました。その頃にはもう「恋愛」という言葉が、特に文学者の間では定着し始めていました。
日本人が抱きがちな西洋への憧れというものと一体化して、英語の“Love”というもともと西洋の言葉だったものを日本に無理やり当てはめるために、翻訳語として「恋愛」が定着したという経緯があります。
佐伯順子 そうなんですよ。私もずっとそこが気になっていて。愛と恋って似て非なるものなんですよね。
愛は「アガペー」、つまり相手を受け入れて、相手のために優しさとか思いやりとかをお互いに交換していくことです。むしろ愛の中には、性愛が含まれない場合がある。家族愛が代表的な例ですよね。愛というのは、性的な関係を条件としなくても成立する。
それに対して恋の場合は、憧れとか「惚れたはれた」のやりとりです。それは正直なところ、相手に対して優しさや思いやりを持っていなくても成り立つ。
つまり、英語の“Love”は性愛を伴う愛と伴わない愛を両方含んでいて、シチュエーションごとに使い分けている。“I love you”と恋人に言った時は「恋愛」だし、神の“Love”と言うときは「アガペー」。
日本の場合は「ラブ」って外来語だからどう訳しましょうとなった時に、家族に対する愛は「家族愛」、性愛を伴う場合は「恋愛」といったように表記を分ける必要が生じたんだと思いますね。
今も蔓延する「伝統的な家族観」という誤解
──近年、夫婦別姓や同性婚の法制化の議論の際に、「保守」とされる議員や論客から、しばしば「伝統的な家族観を壊しかねない」といった言葉を聞きます。ただ、お話いただいてきた通り、そもそも日本において現在の一夫一婦制や恋愛結婚といった結婚観が形づくられたのも、明治時代のことですよね。佐伯順子 はい。政治家なども含めて少なからぬ現代人が「伝統的」だと思っている家族観や結婚観は、実は明治以降につくられたもので、日本の長い歴史の中では極めて新しい現象です。
まず一夫一婦というのは、明治以降に文明開化の動きとともに、当時の知識人と言われる人たちが、欧米の結婚にならって「一夫一婦が道徳的であり、男一対女複数という形が男女不平等なのは明らかだ」という主張を始めました。明治時代には男女平等という価値観も新しく出てきたので、それと相まって、一夫一婦を奨励するという動きが出てきたわけです。
さきほど述べた通り、江戸時代以前には、男の人が遊郭に通ったり、妻以外の女性と関わったりすることに対してはあまり倫理的に問題にされなかったにもかかわらず、女性、特に武士の妻は、夫に対する貞操を厳格に守るという、性別によって異なるダブルスタンダードの倫理観がありました。
それが表向きには改革されたのが、明治維新以降ということになります。
高度経済成長期の夫婦像は、本当に“理想的”だったのか?
──明治時代に男女平等の動きとともに「一夫一婦制」が成立したわけですが、明治時代以降の恋愛観・結婚観についてはどのように捉えていらっしゃいますか。私自身は、表向きには男女平等が実現されたということになっていますが、江戸時代に色濃く存在した家父長制的な結婚観は、明治時代以降も形を変えて残存しているようにも感じます。佐伯順子 山田太一さんが脚本を書いた『岸辺のアルバム』という昭和に人気を博したドラマが、まさに家父長制的な家族関係が残っている高度経済成長期の結婚の典型だなと思っています。
そこで描かれた夫婦は、夫は収入が安定しているエリートで、お子さんが2人いらして、外から見ると理想の家族像です。しかし、夫は忙しくてあまりお子さんのことを顧みないし、お子さんも大きくなったら親離れして自分で出かけていって、妻は一人取り残されてしまう。
画像は「岸辺のアルバム|ドラマ・時代劇|TBSチャンネル - TBS」より
──いわゆる「亭主関白」的な価値観ですよね。
佐伯順子 このドラマを授業の教材として見せたら、フランスから来た留学生が「夫が妻にあんな態度を取ったら、フランスでは大問題だ」と感想を言ってたんですよ。それはそうですよね。私自身も若いころはそんなものだと見てしまっていましたが、今思えば、こういう感覚が、グローバルには正しいですよね。
この頃に理想化された家族愛とか夫婦愛は、実はすごく男性中心的です。その代わり、男の人は会社で上司や同僚にいじめられたり、深夜まで働いて朝早く出勤したりと、労働環境において苦労していました。その反動もあってか、家の中でストレスを発散しがちになってしまう。
同時に、外で仕事をする女性に対して抑圧が強くなってきて、「女性は生計労働するな」という暗黙の価値観が出てくるようになります。けれど、夫の収入で生活することになると、夫が言葉通り「主人」になってしまい、妻は逆らえない。
昭和期の家族は、日本が経済成長しているから一見幸せだと思われがちなのですが、非常に家父長制的な要素の強い家族でした。男性は男性で長時間労働して苦労するし、女性は女性で家の中で一人ぼっちになってしまう、非常にアンバランスな状況があったと思います。
だから、今の若い女性や男性がそうした家族像を目にして嫌だなと感じて、だんだん結婚しなくなっているんじゃないかというのが私の見方です。

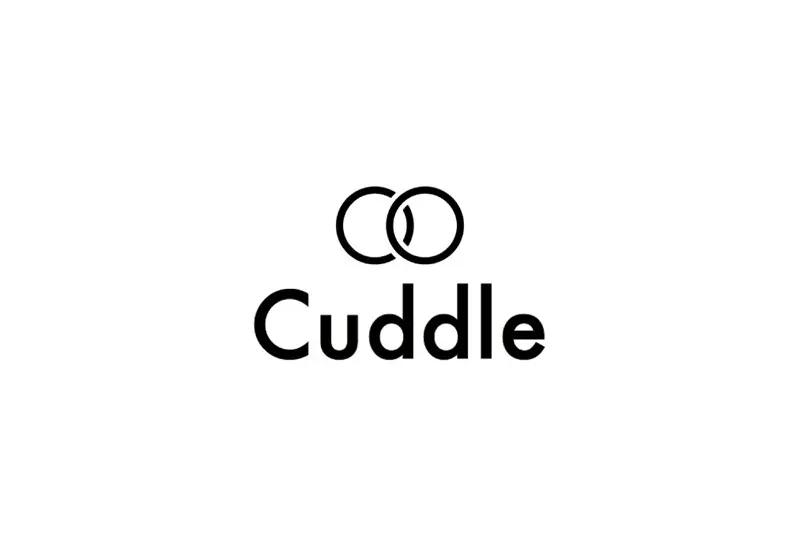



0件のコメント