そしてその言葉は、変わろうとする社会の兆しや、日本ではマイノリティである価値観や性的志向を持つ人の声を塞ごうとする時にも、良いように使われてきた。
日本社会ではむしろ、この「伝統的な家族観」から逸脱する人間や行為が極端に忌避される場面も見られる。
でも、本当にそれは日本において「伝統的」なのだろうか? そしてどのような経緯から、そうした価値観は形成されてきたのか? 改めて立ち止まって考えてみたい。
本稿は、既婚者専用のマッチングアプリ「Cuddle」のプロモーション記事である。 「既婚者専用のマッチングアプリって何?」と疑問に思う読者も多いはずだ。
そのコンセプトや実態についても記事の最後にうかがっているが、記事の主旨としては、同志社大学社会学部メディア学科教授の佐伯順子さんに、日本における結婚観・恋愛観の歴史的な変遷を皮切りに、「既婚者同士で交友関係をつくる」という結婚観・恋愛観についてお話をうかがっている。
そして、聞き手であり記事の執筆者である中村香住さんは、ジェンダー・セクシュアリティの社会学を専門とする研究者である。
中村香住さんは、日本における一夫一婦制や恋愛結婚が比較的新しい現象であることや、年長男性に権力が集中する家父長制的な側面が今も残存している点をはじめとした結婚制度の問題点に着目。
中村香住さんには、本インタビューを通してそうした点を多くの方に知ってほしいという思いからインタビュアーを引き受けていただいた。
また、「ポリアモリー」や「オープンマリッジ」といった、日本においては比較的最近知られるようになってきた関係性構築のスタイルについても、佐伯さんのお考えをお聞きしつつ、「Cuddle」チームの見解についても尋ねた。
取材・文:中村香住 リード文・編集:新見直
目次
「恋愛」という概念がなかった江戸時代以前、「結婚」と「色事」は別物だった
──最初に、江戸時代以前の恋愛観・結婚観についてお聞きしたいと思います。江戸時代には、「色好み」「色事」といった概念が存在したと聞いたことがありますが、これらは現在の「性欲」や「恋愛」とどのように異なるのでしょうか?佐伯順子 紫式部『源氏物語』の「色好み」や西鶴『好色一代男』の「色事」を見ていてもそうですが、これは恋心、「人に惚れる」という意味での恋ですね。
明治以降の「恋愛」では、いわゆるプラトニック・ラブ(肉体に依存しない精神的な結びつき)を理想化します。魂(精神)と肉体は違っていて、肉体は非常にレベルの低いものだが、魂とか精神の世界は高尚で神にも近いのだ、と。だからプラトニック・ラブから恋愛は始まるべきだと明治時代の知識人は考えていて、その点を強く強調しました。
佐伯順子さんは、著書に『「色」と「愛」の比較文化史』(岩波書店)『一葉語録』(岩波現代文庫)などがあり、日本の文学や文化史、ポップカルチャーから、恋愛観・結婚観の歴史的な変遷やそこで見られるジェンダー観を研究している
仏教の中では「肉欲は罪深いものだ」という禁欲的な教えはもちろんあったのですが、それを杓子定規に信じている江戸時代の市民はあまりいませんでした。日本では、仏教寺院自体で、かわいい少年と肉体関係を持ち、それを「神仏との融合だ」「あの世に行く快楽だ」なんて表現した物語も書かれていたぐらいなので。
そういう考え方が主流だったので、色事というのは必然的に、肉体関係を持ちつつ一晩一緒に過ごして、関係が成立するということでした。明治以降のプラトニック・ラブの強調は、江戸時代以前の色事がこのような特徴を持っていたので、それに対する反動だと思うんですけどね。
中村香住さんは、女性声優とDisneyとテーマパークと百合が好きな社会学研究者。慶應義塾大学等非常勤講師もつとめる。レズビアンでクワロマンティック(人に抱く好意が恋愛感情かそうではないかを判断できない/しない)
佐伯順子 江戸時代以前の結婚は、武家の場合だったら家系を存続させる、商家だったらそのお店を存続させるという感じで、「家」を中心に回っているので、「惚れた腫れた」といった恋心と結婚は結びつかないんですよね。
お見合いすらなく、「あそこの家とここの家は家格があっているから」という感じで結婚させられてしまうんですよね。子供をつくるための結婚で、好きな人と結婚するわけじゃないから、惚れる人は別にできちゃう。ですので、明治以降の一夫一婦制の倫理観とは完全に相反しますが、当時の多くの男性にとって妻は妻であって恋人とは違うという感覚になってしまう。妻との関係は惚れたはれたと別次元と考えられてしまう。
逆に女性の場合は、特に武家であれば貞操観が重視されるので、極めて抑圧的でした。
──結婚は制度維持のための仕組みで、情愛や色事はその仕組みの外側にあったと。
佐伯順子 はい、ただし、地域社会の場合はまた違っていて、上方落語で『いいえ』という演目があります。役者さんが芸の修行として女の格好、いわゆる女方として旅をして、途中立ち寄った民家に一晩泊めてもらう。女だと思って娘と妻の部屋に一緒に泊めるんだけど、実は男なので、娘とも妻とも関係してしまう。そして、夫は夫でその役者のことを女だと思って関係する。翌日、家族3人で女方さんを見送る時に、みんな薄々気づいて「昨日あの子となんかあったんじゃない?」と互いに聞き合って、3人とも「いいえ」とはぐらかすんです。でも、それで丸く収まる。誰もお互いのことを強く糾弾しない。
赤松啓介さんの『村落共同体と性的規範―夜這い概論』(言叢社)などには、実際に落語に似た地域社会の女性と旅人との関係などが書いてあり、実は江戸時代以前の地域社会の女性の方が、近代的な概念を当てはめると、性的には自由だったと言えると思います。
──それが、明治以降は徐々に変化していったということですね。
佐伯順子 そうですね。例えば与謝野晶子さんの有名な『みだれ髪』を読むと彼女は奔放な女性のように見えますが、『みだれ髪』の晶子像は本当に一面でしかなく、むしろそれを彼女はのちに否定しています。
与謝野晶子『みだれ髪』/画像はAmazonより
清くなるということは、処女性を重視するという意味なのですが、こうした性的潔癖性の賛美は、北村透谷の恋愛論※などで喧伝されました。しかし、明治前半の地域社会の女性たちの間ではそうした性道徳が希薄で、10代くらいで夜這いなど、地域社会の性的習慣のなかで、性的に成熟してゆくことに対して、咎められることもなかった。
ところが、明治の近代以降になって「清い恋愛」が道徳的だという思想がだんだん普及してきたために、村の娘たちは処女性を大事にするようになり、文明の「進化」にふさわしい喜ばしい変化であると与謝野晶子は書いています。
※「近代日本と恋愛」のめぐる研究において、その原点として位置付けられるのが、評論家・詩人の北村透谷だった。彼は「厭世詩家と女性」という文章の中で、「恋愛は人世の秘鑰(ひやく)なり」と主張。今で言う恋愛至上主義の立場を打ち出した


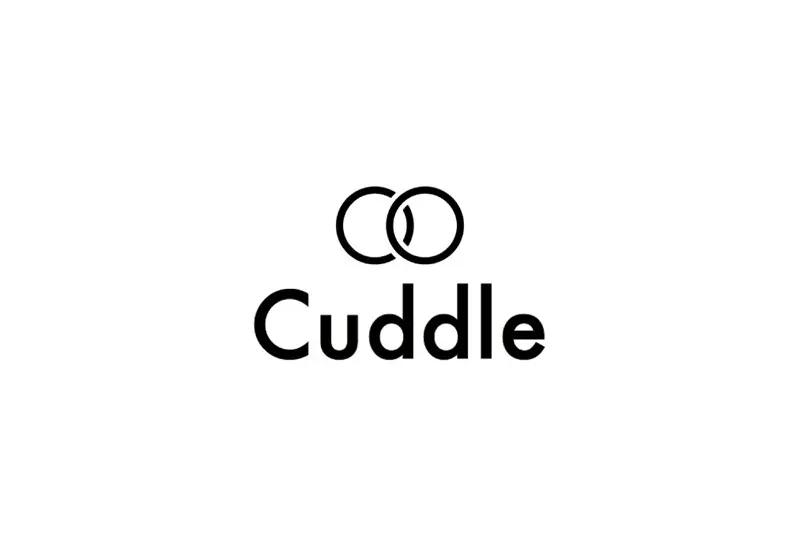



0件のコメント