門司港が象徴する北九州市の“多様性”
なぜポルトは生まれたのか?
1週間滞在させてもらった門司港のゲストハウス・ポルトは、この3月で1周年を迎えたばかり。ポルトに泊まっていると話すと、門司港の人たちは皆揃って「ああ、ポルトさんね」と合点がいったような顔を見せた。
滞在中、ポルトには様々な形で助けてもらった。地元民のおすすめ店を紹介・案内してくれて、行く先々で様々な人や文化に触れることができた。
冒頭で紹介した、食べログ上では閉店している焼肉屋・南大門もその一つだ。
ネットで調べたら閉店しているようで連絡先もなく一度は諦めたが、ポルトの女将さんに相談すると電話一本で予約をとりつけてくれた
ポルトの名物女将・長野さくらさん
ポルトで毎朝振る舞われた、頰がとろけるキッシュ。門司港の人気タルト店「S・tart・inn(エスタルティン)」から卸されていて、道理で美味しいはずだ。
絶品キッシュと女将さんお手製スープがポルトの朝食
最終日、「今日開いてるみたいです!」とポルトの人に教えてもらってかけつけた「S・tart・inn」@門司区(Instagram)。ご主人の貞岡さん(筆者撮影)
小倉の飲み屋で、東京にも何度か訪れたという人の「東京に住めないと思った理由が3つある」という言葉を思い出す。満員電車と、道行く人の歩く速度とその目線だと。「早足で歩く都会の人は、空を見上げん」。
誤解しないでほしい、これは単なる地方礼賛ではない。
ポルト代表・菊池勇太さん(筆者撮影)
最終日にようやくつかまえることができたポルトの代表・菊池さんは言う。これは、決してうそぶいているわけではなかった。
ポルトには、現在10人近くのスタッフが働いている。もとは菊池さん自身と、予約が入った時にだけ宿を切り盛りする1人がいればいい、くらいの想定だった。
他の事業の売上でまかなえる程度の赤字を覚悟していた。しかし、本人も予期せぬ形で、雪だるま式に人は増えていく。
「菊池くん、この人、仕事も住む場所もなくなっちゃったからポルトで働かせてやってくれないかな」。そうして出会ったのが、今ではポルトで運営するキッチンカーのレモネード専門店「SICILIA(シチリア)」のスタッフをつとめるsakiさん。
ポルトの女将も、大学4年でどこにも正社員として就職できなかった彼女を人づてに紹介された菊池さんが雇用したという経緯がある。
今では、年間数百万円の赤字を覚悟しているという。銀行から借り入れしながら給料を払い、なんとか続けている。
筆者は混乱してきた。疑問符だけが湧き上がる。
菊池さんは笑う。「どうしてこうなったか、自分でもわからないです(笑)」。
なぜ赤字を垂れ流すポルトを運営するのか?
税金対策と言われたら理解できるが、菊池さんは明らかに身を粉にして働いている側の人間だった。それくらいは筆者にも見抜ける。(筆者撮影)
現在31歳、門司港出身の菊池さんは、大学を出てからしばらく東京で、産業廃棄物の収集・処理を行う会社の新規事業に関わっていた。
環境省やシンクタンクらとの共同プロジェクトとして立ち上がったその事業は、ペットボトル1本を生産するのにどれくらいのCO2を排出しているかを算定して、その排出量をカロリー表示のようにラベルにして貼るというものだった。
しかし、菊池さんたちの研究の結晶であるそのラベルは、市場に出荷されるとペットボトルからたちまち剥がされてしまった。
「貼っても売れなかったから。必死に算定したのに、市場に出たら消費者の手に渡る前にラベルは消えてしまいました。今ではプロジェクト自体も存在していません」
気候変動に世界の関心がさらに高まっている今からしても、先見的なプロジェクトにも思える。
「社会を良くするためにはどうにかして環境負荷を下げる必要あって、その仕組みをつくることに興味があったんです。大学の論文もそれがテーマでした。けど、結局売れなきゃ支持されないってことがよくわかった」
消費者心理により近いマーケティングを学ぶため、農業関連の事業部も存在した福岡市内のリサーチ・マーケティング会社で6年働いたのち、2年前に門司港に戻ってきて独立した。
菊池さんは、建物自体の文化的価値を認めたのはもちろん、門司港における文化芸術の拠点であってほしいというオーナーの思いを汲んだ。
ポルトでは現在も、現オーナーの強い希望によって、国内外から手弁当で作家を招聘するアーティスト・イン・レジデンスのようなことが行なわれている。
「俺がやってるのは、経済活動だけが価値とされていることへのアンチテーゼなんですよ」
10年前、市場原理に叩きのめされた青年が、消費者心理を徹底的に学び、その原理を知り尽くした今再び故郷で市場原理へのリベンジに挑もうとしている。これは、北九州市の物語であり、彼の物語でもある。
本当の多様性とは何か?
菊池さんにとってポルトは、投資対象であり、アンチテーゼであり、経済合理性から外れた場所であり、門司港が体現する多様性の象徴なのだという。「地方から新しい生き方の提案をしないと、世の中が行き詰まったままだと思っていて。資本主義はこれ以上拡張する余地もないし、拡張したところで(人の生活が)豊かになる見通しは立たない。
イタリアや東南アジアとかを訪れると感じるんですが、そもそも都心より地方の方が、生き方として優れていると思うんですよね。働くこと自体に意味を感じない人が多い地域は良い街。それを育む土壌として門司港は向いてる。仕事より生きることを優先してる文化の方が優れているでしょう」
衣食住より遊の価値を信じるKAI-YOUとして、彼の考えに共鳴しないわけがない。
確かに、観光PRという観点からはネックになっていることがある、という話を筆者は聞いたことがある。それは、観光地である門司港だが、地域の足並みが揃わない、ということだ。
シーズンだろうが人気店だろうが、平日休んでいたり、逆に土日休んでいたり、そもそもその日の気分でお店がやっていたりやっていなかったりという場面を筆者は何度も目撃した。
仕事だから働いている、という感覚がない。明らかにこの地は、なにか筆者の知らない別の原理で動いている。
「飯を食うために仕事をするんじゃなくて、仕事をしてる人はそれが自分にとって大事な、生きることと同じだから働いている。やりたいことをやるために生きてるだけなんです」
日本一小さい店だの、1組限定の焼肉屋だの、そこをもてはやしているのは外部の視点。地元で人気の理由は、単に肉が旨いのとご主人が素敵だからに過ぎない。
1組限定も、マーケティング的な発想とは程遠い。体調が万全ではない高齢のご主人がさばける限界が4人というだけだ。
「南大門のおっちゃんに『客単価いくらで月の利益どれくらい考えてる?』って言っても意味ないでしょう」。
北九州市、小倉や門司港で多くの人と触れ合った今なら筆者にも理解できる。
みんな、無駄話に付き合ってくれる。なんなら道案内をしてくれて、時には一緒に酒にも付き合ってくれる。
菊池さんのやや露悪的な話し方は、おそらく半分は照れ隠しなのだろう。
ポルトのスタッフはじめ北九州市の人は、過剰な世話焼きだ。世話焼きは、生産性とは対極の、人間の性質だ。
「日本は、都心も地方も、資本主義的なピラミッド構造しかなくて、評価軸が一つだけなんですよね。単一のものさししかないから、『釣りバカ日誌』のハマちゃんとか『男はつらいよ』の寅さんみたいな人は生きられない。
けど、何してるかわからないけどなんとかなってる生き方に価値を見出しているからああいうキャラが生まれて、好かれてるわけじゃないですか。
人が望む理想は映画や漫画で描かれていて、どうやらそれが正解に近いとみんな認識しているものの、現実は効率性と生産性の高さだけが求められて、それを実現する気もない社会になってる。それは矛盾していますよね」
「菊池に後継を探してもらってんだよ」と、甘味処「梅月」のご主人
そういう生き方も素晴らしいと思うけど、誰しもお金は必要で、いい大人なので経済活動に精を出さないと社会人としてはいかんよな、とさえ思っている節がある。
だから、経済合理性から外れた存在や、それを描くフィクションは、ある種の憧憬だと思っていた。そうは言っても頑張らないと生きていけないよな、という覚悟(と諦め)。
「東京や同じ県内でも博多みたいな都心部だけで生きる人にとって、門司港はフィクションかもしれない。けど実際、寅さんみたいな人がゴロゴロいるんですよね。ここに来ないと、そういう人の顔を想像もできない」
菊池さんは繰り返す。「門司港には、多様なものさしが存在する。これが本当の多様性だと思う。それを実現するためにも、ポルトみたいな場所が必要なんですよ」。
「俺は、(女将の)さくらちゃんに投資してるんです。あんまり仕事はしないけど、でも健やかに生きてていいでしょ?って」
何やってるかよくわからない人が、よくわからないけどなんとか生きていられる場所。
強く押し付けがましい主張ではない。穏やかな時間が流れる門司港に存在する、懐の深い、優しいアンチテーゼ。
ポルトは、門司港そのものだと菊池さんは語る。「門司港自体、必ずしも経済的にうまくいってなくてもなんとかなってる」とも
門司港の名士といった一筋縄ではいかないコミュニティからは一切距離を置いているという菊池さん。「本当に地に足をつけて生活してる人とだけ関わってます。門司港の市場を歩いてて、俺を知らないおっちゃんおばちゃんはいないはず」。
門司港だけがあるべき姿だ、という主張ではない。彼が実現しようとするのは、あくまで「価値観や生き方の幅」だ。
「東京のようにマーケットがちゃんと機能してて働くことに特化した地域もあっていいし、そうじゃないところもあっていい。みんなが寅さんだったら機能しないけど(笑)、全体の一部だけでもそうであってほしいです」
“港”を意味するポルト(PORTO)。多様な人が行き交う街で、多様性を体現しながら提案する場所。
(筆者撮影)
アジールとしての門司港を通して、これまでとも違う北九州市の素顔に触れた1週間だった。
全国津々浦々をわたり歩いているわけではないが、少なくともいずれ筆者が東京を離れてリモートワークしながら暮らしたい街ランキング1位に、北九州市が急浮上したのは間違いない。
門司港の中央市場にて



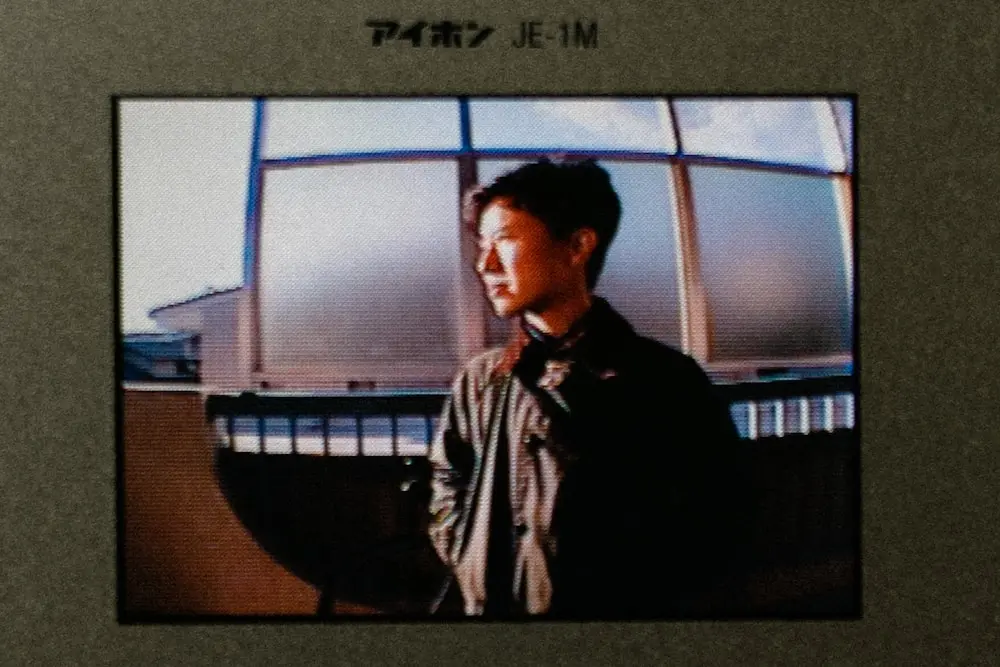

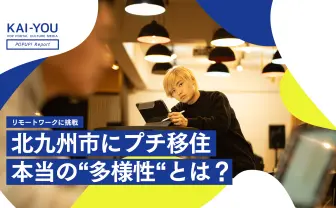
0件のコメント