本当にグリッドマンが、街で戦っていたのか?
通常、映画やアニメ、ドラマは、音楽や登場人物のアクションによって感情の流れを明らかにすることで、虚構の世界への没入を促す。だが雨宮監督作品は違う。無音と限られたアニメートによって、何か観客を虚構の世界へ没入させることを阻害しているように見える。「演出的に非常識な部分があることは自覚」(外部リンク)しての演出なので、阻害もある程度は意図しているのかもしれない。
思えば没入感の阻害は『インフェルノコップ』や『ニンジャスレイヤー フロムアニメイシヨン』で紙アニメのような表現を取った段階からスタートしていた。ただ、あの時点では単なる奇策として受け取られていたと思う。
つくりものであるアニメは動画や音楽によって、さもその世界を本当のように感じさせるようにするものだが、雨宮監督は意図して観客をのめり込ませない演出を入れる。現段階で判断できる彼の作家性と言っていい。
無音と静止画のようなリアリティラインによって、巨大ヒーローが街で激戦を繰り広げるシーンが、まるで現実から遊離したように見えてしまう。雨宮監督の日常描写によって、特撮作品の晴れ舞台である市街戦が不気味な印象に変わる異化効果をもたらしている。本当にグリッドマンが、ダイナゼノンが、怪獣が実在し、街で戦っていたのか?
雨宮哲監督のリアリティラインがもたらす、虚構との距離
虚構世界への没入を妨げる演出スタンスは、シナリオの構造と関わることでさらに膨れ上がる。『GRIDMAN』では怪獣との戦闘があっても街が修復し、被害に遭ったクラスメイトが最初から存在しなかったというミステリーが大きなフックとなる。その原因はアカネが生み出したものだと発覚。事態は全てアカネが生み出した虚構だったと気づかせる。
この構図は原作『電光超人グリッドマン』の設定(※)に倣っているのはもちろんなのだが、登場人物たちは、虚構どころか自分たちの現実すらも没入しきれていないかのように見えるのが異質だ。雨宮監督の演出によって「目の前で異常な現実が進行しているのに、まるで自分事と思えない」という空気感に繋がる。
(※『電光超人グリッドマン』では悪役が作り出した怪獣がパソコン通信経由でコンピュータに入り込み、プログラムを破壊する活動をする。グリッドマンはそんなコンピュータに入り込み、電脳世界にて怪獣たちと戦う設定。)
ここまでが『DYNAZENON』までに描かれたものである。現実感の無さ、見えない異様事態としての虚構というリアリズムとは、もしかしたら現実で陰謀論が渦巻く状況や、刻一刻と日本社会が崩れているのに何も手を出し切れない現実に重なる印象すらある。
振り返れば『GRIDMAN』も“街にぼんやりと存在する怪獣”が主人公たちにだけ見え、街の人々には知覚できないという異様な風景も、新型コロナ後の現在を予見していたような風景にも見える。
現実でも虚構でもない、雨宮哲監督が持つ鋭い作家性
その意味で『グリッドマン ユニバース』は、さらに一歩進んだアプローチを取っている。冒頭で書いたように「虚構世界の住人が虚構としてグリッドマンの演劇をつくる」構図だが、一方では、裕太たちが遭遇した異様な状況がなんだったのかを検証する作業のように見える。それは同時に裕太たちが、自分たちにとっての確かな現実とは何だったのか? を考え直そうとする試みでもある。演劇によって虚構をつくり直す過程で、彼らはある種の現実感を取り戻そうとしているかのようだ。それが僕には、より現代的な問題を描いているように思えた。
しばしば虚構を作ることは現実と無関係な世界を作ることだと思われるが、ここでは虚構を作る作業のなかで、壊れた現実にアクセスしなおす契機にしていると感じる。ある種の美術や文学が目指す姿勢に近い。特に映画前半部分はその緊張感の極地ではないか。
『グリッドマンユニバース』は一歩間違えばもっと恐ろしい映画になりかねなかった。なにせ雨宮監督はインタビューで「最初の1時間はアニメで、最後は実写でグリッドマンが戦うというアイデアも出ていましたが、お客さんが観たいものか疑問だったのでやめました」(外部リンク)と語っているからだ。
新条アカネ(ニューオーダー)
とはいえ、若干歯がゆくはあるも、映画前半でも十分な前進があったといえる。雨宮監督が提示したスタイルは、要素ごとに見てみれば決して新しくはない。だが、虚構世界へ没入させず、かといって現実世界にもリアリティがないと感じさせる態度は見たことはない。
雨宮監督が新作をつくり続ける限り、虚構世界に没入させない演出はどこかで炸裂するだろう。観客側の先入観を常に切り裂く刃先を隠し持っている。
6月30日(金)からはMX4D上映が決定
2

この記事どう思う?
関連リンク

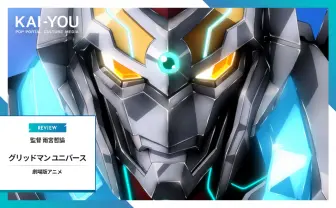
0件のコメント