わたしの数少ない苦手なものリストのうちに、ホラーとスリラーがある。KAI-YOU.netで昨年に映画コラム『悩みをひらく、映画と、言葉と』を連載した戸田真琴さんが、漫画家・押切蓮介さん原作の映画『ミスミソウ』上映に寄せて書き下ろし。押切蓮介ファンだという彼女の目に、『ミスミソウ』はどう映ったのか。
映画のコラムをさんざん書かせていただいておきながら、時には「いろいろな世界を覗き見たほうが人生は豊かになる」などと悟ったように書いておきながら、観に行く映画を選ぶ際には新作ラインナップから爽やかに除外する。
ホラー好きの友人と仲が良かった頃は、隣同士で並んで薄眼を開けてならば見ることができたけれど、それでも一人になった途端に帰り道の暗闇がぜんぶ得体の知れない不安を生み出す魔空間になる。2時間スペシャルでお茶の間向けのぬるいホラーが流れる間、指先をしわしわにさせながら無理して長風呂をした。画面を見なければいいということではなく、そこでホラーが流されている事実が怖かった。もっというと、人の死というものが心底怖かったのだ。
心霊モノもサイコスリラーも、根本には人の生死、それも生々しければ生々しいほどいいと言わんばかりの鮮烈な「死」があった。壮絶な死を遂げたものが悪霊と化したり、精神異常者が悦楽のままに人々を虐殺していく映画は、今わたしが生きていることのまろやかな平穏を、母さんの体温を受け継いだ身体を、一枚剥がしたらあのやわで赤黒い内臓がつまっているのだと見せつけてくるようだった。それがとても苦手だった。誰だってかんたんに死んでしまうのだと、嘲笑われているようで悔しかった。
だけれど私は、押切蓮介という男の漫画が大好きである。
今回紹介するのは、そんな押切作品の中でも随一の後味の悪さを誇る《メンチサイドホラー》、『ミスミソウ』である。
ホラーギャグ漫画家だと思って油断して読んでいたら、思わぬ文脈で出会ってしまった、シリアスでどこまでも悲しく、たくさんの人が無残に死にたえる漫画。「私の一番見たくないもの」の一つでもある。
一部では「トラウマ漫画」と称されるこの作品は、この春、内藤瑛亮監督によって完全実写化を遂げた。
ホラーの定義が「観客に恐怖感を与えるもの」、スリラーの定義が「観客にスリルを感じさせるもの」であるならば、この映画は確実に「ホラー」であり「スリラー」だけれど、その恐怖とスリルは決してスクリーンの中にとどまらない。
ホラーもスリラーも苦手なわたしがなぜこの映画の話をし始めているのかというと、この映画が、スクリーンの向こうから鋭い瞳とボウガンで、わたしたちを貫いて見せたからだった。
映画館のフカフカの椅子にすわり、ポップコーンをかじりのうのうと悲劇を眺める私たちを、ちゃんと傷つけてみせたからだった。
「他の世界だから怖くない」と願う人々
クラスで唯一味方をしてくれるのは、同じく東京から転校してきた過去を持つ相場晄のみ。それでも大切な妹と両親とともに、支え合って暮らしていた。
エスカレートする暴力に耐えかねた春花は、両親のすすめもあり登校拒否をするようになる。それによって、いじめの“標的”が春花に移っていたおかげで難を逃れていた元標的の佐山流美がまたいじめられるようになる。
いじめる側、いじめられる側、傍観する側、けしかける側、それぞれの役割を担う中で歯車が狂っていき、クラスメイトたちの手によって、春花の家族は焼き殺されることになる。
だれかが無残に殺されたとして、殺される側にも決定的なあやまちや運の悪さがあったに違いなかったり、虐殺をする側が精神異常者であったりすればいいとどこかで願っている。はたまた加害者にも大きな心の傷があって、復讐心ゆえの理由ある殺人であったりすればいい、あるいは過激なゲームや漫画に影響を受けた結果の事件であればいい、なんて定義づけてしまう人もいる。
とにかくそれが条理にかなったものであってほしいと願い、自分の身近にはそのような異常な出来事は起こらないはずだと信じ込みたがる。そして、恐怖やスリル、はたまた悲劇そのものまでもが、自分自身に決して降りかからないとわかった瞬間にエンタメとして機能することがある。
漫画『ミスミソウ』が《精神崩壊−メンチサイド−ホラー》として話題を呼び、映画『ミスミソウ』もグロテスクさに特化した予告がネット上で賛否を呼んでいた。退屈な平穏をぶち壊してくれるような、インパクトの強いものが見たい人や、「復讐もの」と聞いて悲劇から転じるカタルシスを求めて観に来る人もたくさんいるのだと思う。
だけれど、満を辞して完成してしまったこの映画は、チクリと刺すような刺激を求めている人たちのずっとずっと、先の方を歩いてしまっていた。
悲劇を「美しさ」で消化して、失われるもの
春花の家族を焼き殺した同級生たちは、決してフィクションの中だけに存在するある種のいかれた子供達という訳ではなかった。漫画も映画も同様に、話が進むにつれ加害者側のじっとりとした人間味が滲み出てくる。
大きな悲劇が、たったひとつの明快な原因のみによって実行されることなど、ほとんどないのだと思う。誰もを圧倒する音と熱さといやなにおいを撒き散らした大火事も、クラスメイトたちそれぞれが、人として、思春期のこどもとして色々なことを感じながら生きていたからこそ起こってしまったことだった。
そこには、痛覚を失ったサイコパスも計画性にすぐれた愉快犯も存在しない。なにかに怯えて人を傷つけ、傷つけた結果に対し怯える、どこにでもいるこどもたちしかいなかった。
ここに描かれている歪みと同質のものが、わたしたちの周り、あるいはわたしたち自身の中にもたしかにあるのだった。
わたしたちの苛まれているちいさな歪みのひとつひとつが、今と違う跳ねっ返り方をしていたら、ぜんぜん、別の世界の話とは思えなかったかもしれないのだ。
高畑勲監督が『火垂るの墓』で描きたかったのは、「逆境の中でも懸命に生き抜く少年少女は美しい」なんてことではなく、ただ「罪のないものたちが戦争によってずたずたにされついには息絶えてしまう姿」だったのだと思っている。
『ミスミソウ』の漫画を初めて読んだ時と同じで、そこには憧れるべきものや賞賛すべきものはなにひとつ描かれておらず、ただ口の中にじゃりじゃりと、怒りにも似た砂つぶが残っただけだった。
この怒りの矛先は映画の中の「不条理」にあり、それはやがて映画の中で死に絶えた罪なきものたちへの鎮魂の念に変わった。
『ミスミソウ』についても、全てを奪われ絶望した少女が鮮やかに復讐していく様を美しいと感じる人も多いのだと思う。私自身、理性を超えて魂の底からただ美しいと感じた。
春花の精神的支えになっていたクラスメイト・相場は逐一、春花をミスミソウに例えて慈しんだ。ミスミソウは、雪を割って紫色の花を咲かせる。その懸命さが春花のようだと相場は言う。
だけれどわたしたちは、誰かの血が流されたことを、それによって壊れてしまった心があることを、悲劇の美を構成するただの要素として納得してしまってはいけない。決して、いけない。
美しいものがぼろぼろに壊れていくことに対して、哀れみや歪んだ親近感を向ける人も少なくないと思う。弱者が逆境を懸命に生き、そして息絶えていく物語を小さい頃に名作として見てきた人も多いだろう。懸命さは美しい。運命に翻弄される様は美しい。そうして「美しい」と唱え続け、美しさを悲劇の免罪符にしてきた。美しさを感じることで、悲劇の要因に対する怒りを忘れてしまうのだ。
わたしが押切蓮介の漫画を好きだと思うのは、どうしようもない怒りを、決して誤魔化さずに漫画に噴出し続ける様に、ほんとうに救われているからである。
彼の漫画には、悲しみに溶けきらない忽然とした怒りがある。
『ミスミソウ』でも、観客の誰もが相場に同調し「逆境の中を生きる、か弱く美しい女」としての春花を観客として消費する中で、春花は決してその目線たちの、望む通りの姿でなどいない。
その鋭さは、かわいそうな女を視姦する観客席のわたしたちまで、さくり、とかろやかな音でつらぬいて、ほんとうの痛みを負ったものの絶望を教えてくれる。自分たちを傷つけた者たちに、誰一人としてやさしくするつもりはない。その切っ先は、今まで悲劇の中で犯され嘲笑われてきた全ての魂の復讐を必然と背負ってしまったように、そう思えるほどに、早かった。
この不条理な世界を生きるための、痛み
映画の中でさえ人が死ぬことが怖い私は、たとえフィクションの存在だからといって、死を軽々しく扱う行為自体がおそろしかった。スクリーンでしっかり隔たりを保って、あの死の生々しい絶望感を自分の日常には持ち込まないようにする、ということがどうしても上手にできなかったのだ。
誰かの死や絶望が、退屈な日常にちょっとした刺激を与えるエンターテイメントの一種になってしまうことが、ただただ怖かった。
だけれど『ミスミソウ』は、観客に対しても復讐をなし得る物語だった。原作を初めて読んだ時も、実家のこたつでぬくぬくとポテトチップスを食べながら平穏を貪る私自身を、漫画の向こうから罰せられたような気がして怖かった。
誰にも甘くない、誰に対しても毒になる物語がここにあった。そして、わたしたちはこの毒によって、いつか生き延びる瞬間が来るのだということも悟った。この世界に本当の悲しみが、誰かに消費されるためのやさしい悲しみではなく誰もが嫌な顔をするしかない「ちゃんとした」悲しみが、描かれていてよかったと思うときがくる。
いつも、この扉の一枚向こうには不条理な世界が待っているのかもしれないから。
彼女が流した血と彼らが流した血が、別の赤色に見えたこと。
それを見て張り裂けた胸のせいで、泣いてしまうことができること。
わたしが謝ることではないけれど、この世界で本当の本当のことを描くとき、それはいつも気持ちいいものになるわけじゃない。
あなたがなにも考えずにただ気持ちよくなる作品を作るためには、いろいろな「本当」を隠さなければいけない。
私たちは、しばらく自分を気持ちよくしてくれるものを求め、そういうものから優先的にお金を支払ってきた。だれもがお金の集まる作品をつくった。めぐりめぐって、映画館にも、テレビにも、漫画にも、本にも、雑誌にも、私たちを生ぬるく丁度いい温度で、傷つけずに守ってくれるばかりの作品が溢れかえった。
あなたを慰めたり、時には泣かせてデトックスさせてくれたり、スリルで退屈を吹き飛ばしてくれたり、ハッピーエンドで笑わせてくれたりする優しいエンタメの数々に守られてきた心には、『ミスミソウ』はあまりに辛く苦しく受け入れ辛いものに思えると思う。
これが、ただ人間性を失った主人公による「サイコで残虐な復讐劇」の一言で片付けられるのなら、どれだけ心が楽だっただろう。
それでも、本当に悲しいお話を見て、あなたの胸が痛んだこと。
誰かが死んでしまう瞬間に、見なければよかったと後悔したこと。
それ自体がこの世界の希望です。
この映画に描かれる歪みの数々と同じ質の歪みを背負ったまま、今日もなんとか破裂してしまわないようにおそるおそるまわっている、この世界の希望です。
その痛みを背負ったあとのあなたで、これから生きていてね。
思い出して悲しくなることに、なんの保証もできないけれど、痛みを背負ってしまえたことを、大切にして生きていてね。
美しい悲劇として消費されてきたすべての物語の地中で、踏みつけられてきたすべてのものへ、花を手向けるように。
痛んだ胸を張って、どうか、ずっと生きていてね。
文:戸田真琴 編集:長谷川賢人
戸田真琴さんのコラム連載

この記事どう思う?
映画公開情報
『ミスミソウ』
4月7日(土)より東京・新宿バルト9ほか全国で公開
©押切蓮介/双葉社 ©2017「ミスミソウ」製作委員会
配給:ティー・ジョイ
上映時間 :114分
レーティング:R15+

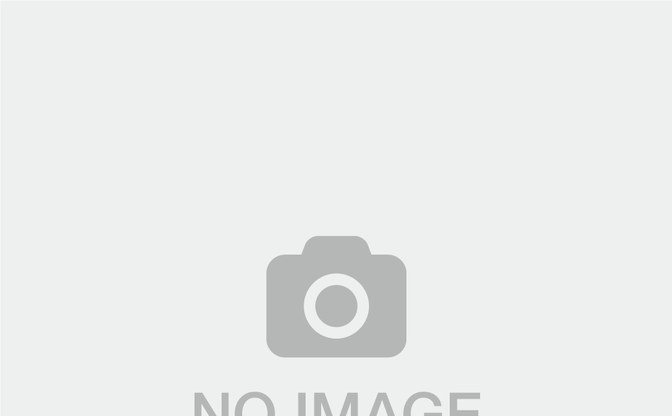


0件のコメント