「いれいす」リーダー ないこインタビュー 歌い手戦国時代を生き抜くヒント
2023.02.01
なぜWikipediaの英語記事名が「Virtual YouTuber」から「VTuber」に変更されたのか。ウィキペディア、バーチャルYouTuber(VTuber)双方の背景から解説
※本稿は、2021年に「KAI-YOU.net」で掲載された原稿を再構成している
2021年11月15日、英語版ウィキペディア(Wikipedia)で記事「Virtual YouTuber」の名前が「VTuber」に変更された。
移り変わりが激しいVTuberの世界において目立つことではないが、ウィキペディア上の事情や背景に着目すると大きなトピックだとわかる。
なぜ記事名が「Virtual YouTuber」から「VTuber」に変更されたのか。ウィキペディア、バーチャルYouTuber(VTuber)双方の背景から解説しよう。
目次
- そもそもウィキペディアとは
- なぜ変更された? 記事名変更には議論が必要
- 「バーチャルYouTuber」はいつから使われたか
- 「バーチャルYouTuber」略して「VTuber」
- “バーチャルタレント”となったキズナアイ
- 「バーチャル」と名のつくものたち
- VTuberは終わらないストーリー
日本語版ウィキペディアには「ウィキペディア」という項目がある。
本文冒頭にはこうある。
ウィキペディア(英: Wikipedia)は、世界中のボランティアの共同作業によって執筆されるフリーの多言語インターネット百科事典である。「ウィキペディア - Wikipedia」より
ウィキペディアは、誰でも参加できる百科事典をつくるプロジェクトだ。日本語版の他にも、英語版、中国語版、韓国語版など、300以上の言語で様々な記事が作成されている。中でも「バーチャルYouTuber」の記事は19言語で作成されており、各言語の記事を見るだけでも世界広まりを感じることができる。
記事名が変更された英語版ウィキペディアは、各言語のウィキペディアの中でも作成数・利用者共に最多であり、記事だけでも640.8万記事(管理ページなど一部除く)、活動中の登録者数は12.4万人と数多くのボランティアが参加し、記事の編集などを行っている(データは2021年11月15日時点、外部リンク)。
また余談であるが、今や世界で人気を集めるホロライブの記事もウィキペディアに存在する。
日本語版の「ホロライブプロダクション」や「カバー (企業)」の記事には概略だけで、歴史の解説がされていないのだが、英語版の「Hololive Production」の記事には、2016年からの詳細な歴史が解説されている。
今やホロライブがアプリ企業からはじまったことはあまり知られていないように思うが、英語とフィリピン語だけはこの情報を知ることができるのだ。
ウィキペディアは言語ごとに内容が異なるため、こうした言語ごとの違いを楽しめる。機械翻訳を使うだけでまた違った知識を得ることが可能だ。
ウィキペディアには英語版で「トーク」と呼ばれる、その記事の問題点や変更点などについて話し合うページが用意されている。「Virtual YouTuber」から「VTuber」への記事名の変更もそのページで議論された結果変更された。
この記事の続きを読むには
あと6266文字/画像4枚
アカウントを作成
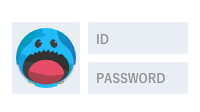
お支払い情報を入力
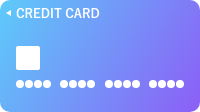
サブスク登録完了!

理由は、記事名を付ける際のウィキペディアのルール(ガイドライン)
様々なジャンルの最前線で活躍するクリエイターや識者を中心に、思想や作品、実態に迫る取材をお届け
様々な記事の中から編集部で厳選したイチオシ作品をご紹介