インディーゲーム、VTuber、TRPG…新世紀を切り開く「同人」という魔法
2021.01.27
『シン・ウルトラマン』が封切られた2022年5月。改めて、『シン・エヴァンゲリオン』で、映像と脚本面から、何が結実していたのかを振り返る。
※本稿は、2021年4月に「KAI-YOU.net」で掲載されたものを再構成している
2021年3月8日に公開された庵野秀明総監督による『シン・エヴァンゲリオン劇場版』。本作は他に類をみない映画であり、間違いなく歴史に残る大傑作となった。
しかし、すべてを語るにはあまりにも時間も理解も足りない。よってここでは“誰も観たことのない映像”と“フィクションの究極的な脚本”という2点にフォーカスして本作について語ろうと思う。
目次
- 誰も観たことのない、虚構と現実を超えた映像
- アニメの原点へのリスペクトと特撮へのオマージュ
- 「これまでにないアニメづくり」へ結集された総力
- フィクションの“究極”を成し遂げた脚本
- 「プロジェクトエヴァ」とは告白である──
- 引き裂かれたあらゆる可能性が1つになった、奇跡のような作品
本作は2つのアバンタイトル(AVANT1、AVANT2)と、4つの本編パート(便宜上、登場順にA、B、C、Dと呼称)という、合計6つのパートで構成されているが、その映像的な新しさは、AVANT1、AVANT2、Aという序盤3つのパートに凝縮されていると言っていい。
まずはAVANT1。3DCGによるエヴァ8号機と“使徒もどき”(Evangelion Mark.44A)の空中戦を描いたバトルシーンは、手描きの2Dアニメでは到底実現できないカメラワークの連続で、スタジオカラーが「新劇場版」シリーズを通して取り組んできた3DCGを活用した巨大ロボットのバトルの総決算ともいうべき内容になっている。
「カラースコープ」と名付けられた、通常のテレビ画面の16:9よりも横長の画角を活用したレイアウトは、前作『ヱヴァンゲリヲン新劇場版:Q』とは段違いのクオリティーであり、実写映画である『シン・ゴジラ』での経験が遺憾なく発揮されていると考えられる。おそらくは3DCG空間上にバトル全体の動きをある程度つくりあげ、その上で、同空間内でカメラを操作してアングルを探るという、実写でも2Dアニメでも絶対にできなかった手法がとられているのではないだろうか。
🔔CGメイキング映像を特別公開🔔その2
好評公開中『#シン・エヴァンゲリオン劇場版』AVANT1より、CGメイキング映像を抜粋して特別公開!
公式アプリEVA-EXTRAではプレミアム会員限定コンテンツとして、現在7カット分を公開中📲https://t.co/x4vRkcRztq#シンエヴァ pic.twitter.com/b4nToHqs1C
— 株式会社カラー (@khara_inc) March 26, 2021
続くAVANT2は、「動」そのものだったアクションパートのAVANT1から一転し、『ゴッドファーザー』などで知られるニーノ・ロータを思わせる“映画音楽”的劇伴とともに、主人公・碇シンジら3人のメインキャラクターが、赤く染まった大地を神奈川方面から静岡方面へと歩き続ける「静」のシークエンスだ。
技術的にはとくに目立つところのないタイトルバックパートではあるが、多くの観客が郷愁を誘われるであろう日本の風景が赤く染まり、やはり同じく真っ赤な瓦礫が浮遊し、首のない巨人が残置されている光景は、これまでに見たことのないイメージそのものであり、1995年放送のTV版『新世紀エヴァンゲリオン』で初めて第3新東京市を目にしたときの、あの不思議な感覚が再び書き換えられるようでもあった。
「背景美術が映画の品格を決める」とは庵野秀明総監督の師匠の1人でもある宮崎駿氏の言葉だが、そうした背景美術と美しく壮大な劇伴が『シン・エヴァ』を“映画”たらしめていると言っても過言ではないだろう(余談だが、このAVANT2は、『もののけ姫』のデイダラボッチを連想させる半透明の首無し巨人の描写も含め、呪われた運命を背負い故郷を追われたアシタカの旅立ちを美しい背景美術と勇壮な劇伴で祝福した同作冒頭へのオマージュ、そしてデイダラボッチの首が落とされた終盤へのアンサーとしても見ることができるだろう)。
そして第3村での生活を描いたAパートは、本編序盤でありながらも、ありったけの技術とアイディアが詰め込まれた、本作の映像的なクライマックスである。
静岡県浜松市の天竜二俣駅をモデルとした村のロングショットにはじまり、建物屋内の全景を見せる広角レンズによるカット、そして村内での会話劇、日常芝居、田植え仕事まで、徹底的に画面設計=レイアウトにこだわり抜かれていることに気づく。高畑勲と宮崎駿が確立したアニメの制作技法である「レイアウトシステム」、その原点に立ち返るような強いリスペクトがここに見て取れる。
そしてもちろん、そのレイアウトの中には、もはや庵野秀明のシグネチャーとも言える、『ウルトラマン』の名エピソードを奇抜なアングルワークとともに手がけてきた実相寺昭雄(※)へのオマージュも健在だ。カメラをのぞき込むアヤナミレイ(仮称)を手前に、奥にうずくまるシンジを置く構図などはその好例だろう。
※実相寺昭雄:「ウルトラ」シリーズを代表する監督の1人。ジャン=リュック・ゴダールなどを意識した独特な演出・カメラワークで知られる。有名なものでは『ウルトラマン』のジャミラ回、『ウルトラセブン』のメトロン星人とのちゃぶ台を挟んだ対峙回など。
だが、彼らはそこに止まらない。
この記事の続きを読むには
あと6121文字
アカウントを作成
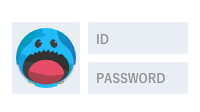
お支払い情報を入力
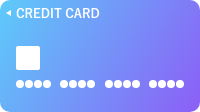
サブスク登録完了!

フィクションの“究極”を成し遂げた脚本
様々なジャンルの最前線で活躍するクリエイターや識者を中心に、思想や作品、実態に迫る取材をお届け
様々な記事の中から編集部で厳選したイチオシ作品をご紹介