この日開催された、分野を問わず本気でアーティストを志す次世代クリエイターを支援するプログラム「FUTURE CULTIVATORS PROGRAM 2017」(以下FCP2017)の最終作品発表会は、現代美術家・椿昇さんの強烈な言葉から始まった。
椿昇さん
「瀬戸内国際芸術祭」など全国の地方で開催される芸術祭も活況を呈し、現代アートというトピックが身近なものとして浸透しつつあるかのように見える。「日本のアート産業に関する市場調査2016」によると、ギャラリー、百貨店、オークション会社、美術館などの国内アート産業の市場規模は3341億円と、決して小さくないことが報告された。
しかし、当の日本のアーティストたちはどう考えているのか? 率直な話、食えていけてるのだろうか?
FCP2017にて審査員たちが時に辛辣に語った、「日本アートの問題点」と「アーティストが食べていく方法」をお伝えする。
取材・文:和田拓也 撮影:佐々木孝憲 編集:新見直
「FUTURE CULTIVATORS PROGRAM」とは?
左:古川周賢さん 右:椿昇さん
今年も、現代美術家として世界的に活躍し、京都造形芸術大学教授や森美術館理事を務める椿昇さんが講師となってワークショップを重ね、優秀者8名は京都でのフィールドワークに参加し、『脱皮』をテーマに作品を制作。
10月15日に開催された最終作品発表会にて、椿昇さん、恵林寺住職で現代美術に造詣の深い古川周賢さんを審査員に迎えてプレゼンテーションが行われた。
最優秀賞を受賞したのは、参加者の中で唯一の学生である今井志芳夏さんによる『脱皮の夢』。椿さんは彼女の作品に対し、こう評した。
椿 「日本人の極めて土着的で、強固な遺伝子を感じる無垢な作品。画力もある。自分の夢の中を私小説的に描いていて、なんとか表現というレベルまで持ってきています。日本には彼女のようなピュアな作品を支持する市場があるし、食べていける可能性はある」
最優秀賞を受賞した、今井志芳夏さん『脱皮の夢』
椿 「私小説をいかにうまく物語に置き換えるかという力技が必要になる。だけど、同時に彼女の無垢さが失われることにもなる。そこのアンビバレント(二律背反)を乗り越えないと、次のステップに進めませんよ。今回は、他が変化球なのに彼女はどストレートのスローボールを放ってきた。戦場でなにも知らずにとことこ歩いて、銃弾の雨をとおり抜けていった感じに近い」
“どうつくるのか”ではなく、”なぜつくる”のか?
『望月』(安田汐里さん)
古川 「アーティストが世界に出た瞬間、作品に本質的な意志や思想が論理的に含まれているかも重要になります。それがなければ、いくらビジュアルをいじくって後付けしても、結局ただの中途半端なギミック。目くらましにしかならない。さらに、論理性がないと英語にできないから海外と繋がることもできません」
椿 「デザインというのはストラクチャー(構造)、それによって『どちらを指し示すか』であって、最終的に出来上がった作品は視覚的なエンターテインメントでしかない。つまり、作品はあくまでもプロセスを可視化したもの。ゴーギャンの『我々はどこから来たのか、我々は何者か、我々はどこへ行くのか』のように、自身の精神に向き合った先に作品が存在するのであって、決して作品が先ではないんです」
この言葉を聞いて、筆者はミクスチャー・バンド「Rage Against the Machine」(レイジ・アゲインスト・ザ・マシーン)のギタリストであるトム・モレロ(ハーバード大学主席卒)の、「どう弾くかではなく、なぜ弾くかをいつも考えている」という言葉を思い出した。「どうつくるか」ではなく、「なぜつくるのか」。
それは、「作品をいかにデザインするか?」という問いかけにもなる。例えば、ナチュラルアメリカンスピリットというタバコにとって「オーガニックである」というコンセプトこそがデザインである。そのコンセプトに見合うビジュアルイメージをつくるのは、デザイン的な作業ではあるが、本質的にはデザインではない。椿さんはそう語る。
「なぜ敵を知ろうとしないのか?」
『脱・皮』(坂間真実さん)
では、その論理を作品に落とし込むために最も必要なものは何か。それは「教養」だ。これは作品の総評時、審査員の2人から「あまりにも教養がなさすぎる」という言葉をもって強調された。
古川 「現代のアート市場は徹頭徹尾、西洋の原理で動いています。欧米では、えげつない作品を浴びるほど見ることができて、普通に暮らしているだけでアートの素養くらいガキでも身につく。日本人がそこで戦うなら、彼らに負けない教養を身につけないと戦えるわけがない。なぜ敵を知ろうとしないのか? と。知った上で使いこなさなければならないし、知ればものの見方が変わりますよ」
椿 「アーティストがステップを上がれば上がるほど、作品に興味を持った人、さらに購入を検討としている人と、会話する相手の質も上がる。そのときに論理と教養が必ず必要になります」
古川周賢さん
幅広く、深い教養から生まれた意味合いは、作品の論理性をより強固にする。逆にそれがないものはいくら論理構築をしても、ギミックになってしまう。
作品において表現と教養が接続されていない。これは日本の多くのアーティストに見られる課題だと椿さんは指摘する。またその原因のひとつとして、日本の美術教育システムのあり方をあげる。
椿 「日本の美大の教育システムでは技術しか教えない。売れるための戦略や教養など二の次。入試でも一般教養なんてほとんど関係ないでしょ?
美大の授業でも、実技とセットで美学の話をしない。座学として受けているだけなので表現と教養が切り離されてしまう。結果、それらが相互に影響し合わず、表現の中に教養を落とし込めない。いま日本の美術教育のシステム全体を再設計しようという動きは少しずつ起きていますが」
しかし、教養を身につけ頭でっかちになってしまったアーティストなどそれこそごまんといるだろう。教養を備えた上で、最後には、それを削ぎ落とさなければならない──これが、およそ数ヶ月にわたるプログラムのテーマの一つに据えられた「禅」の思想だという。
『学び』(藤原誠人さん)
椿 「禅僧っていうのは、一般的に本を読むなって言われる。でも禅僧は上に上がっていこうと思うと膨大な数の経典を覚えないといけないからね。無垢、つまり禅に近いひとが一番ものを知ってるんだよ。世の中というのは残酷で、無垢なままではISのようなテロリストと変わらないから、知性が必要になる。一方で、アートというのは学びながらも自分を見失うことなく、無垢さを守らなければならないんです」
シンプルなものには美しさが宿るというが、身につけた上で余計なものを捨てた美しさの背景には無数の文脈が存在する。それがはじめから無い“シンプル風”のものは「簡易」なだけで人の心を動かすことはできない。削ぎ落としたというプロセスがあるからこそ、その純度と厚みが増すのだ。
敷居を低くした先にあるのは、100均かディズニーランド
『Fall Play』(遠藤知恵子さん)
椿 「現在のグローバルマーケットは敷居を低くすることで成り立っていて、敷居の低さの最大のかたちは安いということ。敷居を低くして自分の作品の価値を貶めてはいけない。なぜなら、それは100円均一ショップに甘んじることと同義だからです。
芸術祭をとっても、アーティストが地方自治体の奴隷になってる。お客さんは田舎の景色に触れたりスタンプラリーや自撮りをしたい。作品はほとんど見てないんです。金沢も200万人以上の入場者がいるけど、多くは通りすぎるだけ。わかりやすくした結果、みんなが通り過ぎていく」
グローバル化の波に乗って単に「楽しい作品」を推し進めていけば、その先でアーティストや芸術祭が対峙しなければならないのは、徹底して計算され尽くされたディズニーランドかもしれないと警鐘を鳴らす。
『蟬脱』(クボタノリコさん)
しかし、それ以外のところに本来のアートというものがあるのだとすれば、アーティストは市場の奴隷に甘んじてはいけないんです」
現代のグローバルマーケットでアーティストが食べていくということは、少なからず、市場の原理に迎合するということだ。そこに抗うということは、ある種のファンタジーともいえる。
『たいか』(清水智大さん)
アーティストの生存戦略とは?
椿 「作家のアイデンティティとマーケットという相反するものをどう取りまとめるか、アーティストは最初から考えておかないといけない。二元論ではなく、それらの「接点」というのは世の中に無数にあります。
例えば、タバコって本来はタバコの葉っぱを自分で買って、麻の紙で手巻きするとすごくおいしい。紙で巻くと紙のにおいがつくから。でも工業製品として売るにはそれはできない。本当のおいしさにたどり着くには、工業化社会では無理な部分があるんです。それと同じことが世の中にはたくさんあるんです」
マーケットに身を置きながらも、そこからどう逸脱するか。「常に脱出しようとするものにしか、周りは振り向きません」と椿さんは語る。
安全な奴隷になるのか、そうでないのか。月並みながらもそこはやはりバランスの問題だとしながら、考え続けることの重要性を説く。「常に相互作用の中で揺れ動きながら、それを楽しむ。考えるのを止めた瞬間、アーティストではなくなってしまいます」。
『失われた記憶/LOST MEMORY』(今村圭佑)
椿 「世の中にある無数の接点を見つけるには、絶対に教養が必要なんです。知的好奇心を維持し続けること。経済のシステムもそうだし、さまざまな教養が考えるときの道具になり、アーティストを自由にするんです。
美術だけの世界にいると、出口が1つしかないように感じてしまう。『どこどこのギャラリーで展覧会できる』とか、それしか目的がなくなってしまう。そうじゃない道が無数にあるのに。現代の市場システムではある程度のロジックとストラテジーが必要だけれども、意外にシンプルにできている。戦略のもと正確にやればいけるもんです。ですが、知らないことで、それに気付けなくなってしまう」
大きな流れには常にバグがあり、作家がそこに気付けるかどうか。椿さんの言葉を借りるならば、「自分だけがその穴をみつけて、決定論的な世界を鵜呑みにしている世界をいかにニヤリと笑えるか」ということだろう。
椿 「クリエイティビティはバグの中に生まれ続ける。リアリティを常に求めてアップデートすること。表層を舐めるだけではだめなんです」
当日発表された8作品をもっと見る






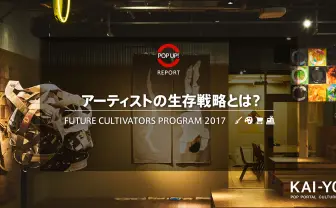
匿名ハッコウくん(ID:1396)
感性だけで売れないならもうそれアートじゃないだろ