はじまりは「人生のシミュレーション」というアイデア
──そもそも、この企画はどんな風に立ち上がったのでしょうか?
藤井賢二 展示会場のGOOD DESIGN Marunouchiさんの公募に出てみないか? と声がかかったのがそもそものはじまりでした。
藤井 賢二さん:株式会社たきコーポレーション取締役。本企画の発案者。
藤井賢二 公募だったので、ゲームをつくる企画というのが通るのか、不安はありました。
ただ、僕は昔ゲームが好きで、社内にも結構なゲーマーがいたりして。もしここで審査に落ちたとしても、どうにかして実現させたいと思えるくらい、ゲーム制作への熱量があった。それで、思い切って提案してみたら採用されたんです。
企画を練っていく中で、最初に出たのは「日常の出来事がゲームになったら面白いんじゃないか?」というアイデアでした。会社の面接みたいに、人生の大事なポイントをゲームにしてシミュレーションする。
「結婚編」「老後編」のような形で、人生の役に立って、子供でも遊べるゲームがいくつかあれば、面白い展示になるんじゃないかと思ってましたね。
最終的には、ゲームとして面白いものにするためにも、「ゲームから学びとれる要素とは何か?」というのを分析して、ゲームに落とし込むという方針に変わっていきました。
──展示されている8種類のインディーゲームはどのように生まれたのでしょうか?
藤井賢二 展示全体を楽しんでいただくために、ゲームのジャンルはバラエティ豊かになるよう、ある程度意識していました。
それから、仮説として立てていた「ゲームから学びを得る」という体験についてディスカッションを重ねたり、実際に学びを得たという方のnoteやポストを分析したりして。
そのうえで、社内のメンバーに協力してもらって、ゲームで勉強になったことをバーっと洗い出していったんです。
最終的に、集まったデータを分類してみると「ゲームから得られる要素」として8つのテーマが生まれた。そこから各ゲームをつくっていきました。
各ゲームに設定された学び
若者から80代まで、ゲームから学びを得た人は6割
──会場には、Webアンケートの結果も展示されていますね。
藤井賢二 ただゲームをつくって展示するだけでは、我々の仮説を押し付けることになりかねない。
「実際、世の中の人はどう思ってるんだろう?」というのを調査をして、結果を共有したほうが説得力が生まれると考えていました。
藤井賢二 そこで、500人ぐらいの方にご協力いただいて、Webアンケートを行ったんですね。
データが偏らないよう、ゲームが好きな人ばかりではなく、あまりゲームをやらないという人の回答も集めるように気をつけました。
プロジェクトメンバーの80代のお母さんもアンケートに答えたそう。さまざまな世代が答えている
「あなたはゲームからどのような学びを得たか」という質問に対しては、何か人生を生き抜くためのマインドセットや教訓、機微のような要素が多いのが印象的である。
重視したのは直感的にプレイできるデザイン
──今回はどうしてレトロゲームのような筐体をデザインしたのでしょうか?
川郁子 私は今回、ビジュアルのデザインやアートディレクションを担当しました。
検討段階では「スーパーファミコンっぽいデザインがいいかな?」とか、いろいろ意見が出ていたんですが、よりミニマムなデザインを考えていった結果、さまざまな世代がプレイしやすい、レトロゲームになっていきました。
川 郁子さん:株式会社たきコーポレーション UXデザインカンパニーIDEAL所属。今回の展示全体のデザインに加え、『ASTRO SURVIVOR』のゲームデザインも担当
藤井賢二 今の時代、ハイクオリティな映像を用いたゲームをつくることも可能です。ただ、僕たちはゲーム会社に対抗するようなゲームをつくりたいわけではなかったんです。
表現のレベルや仕組みを昔のレベルに落とすことによって、ゲームの新しい可能性を見つけたかったんですよね。
内山堅 シンプルなフォーマットには、理解がしやすいという利点もあります。今回は展示会なので、1プレイの想定時間は30秒から2分程度。
内山 堅さん:株式会社たきコーポレーション UXデザインカンパニー IDEAL代表。社外との進行窓口を担当。実はゲームを自分でつくった世代
内山堅 そのためには、プレイヤーが直感的にゲームを理解し、すぐ操作できるというスピード感が必要です。ストーリーや導入までの理解が長くなるとプレイしにくいですからね。
──レトロゲームのフォーマットでデザインしていくにあたり、意識したことはありますか?
川郁子 レトロゲームといっても、年代によって、絵のタッチが違うんです。そういうのにも詳しい人がメンバーにいるので、「あんな感じにしよう!」というアイデア出しはスムーズでした。
ゲームのデザインの一部
川郁子 今回出展しているゲームのうち、私がデザインした『ASTRO SURVIVOR』は、色数が多かったり、光の表現にこだわりました。どちらかといえば「最近のインディーゲーム」の雰囲気を取り入れた部分もあります。
ただ、全体的に、昔のレトロゲームのデザインをリスペクトしていきたかったので、そういう要素は研究して、取り入れていきました。
藤井賢二 まぁ、シンプルなゲームにしたのは、単純に2ヶ月しかない、という制作期間の問題もありましたけどね(笑)。
クリエイターたちの人生を変えたゲーム
──企画コンセプトの“ぼくたちは ゲームを通じて人生を 体験していたのかもしれない”というメッセージが印象的でした。皆さんの人生に影響したゲーム体験を教えてください。
藤井賢二 僕は、ベタですけど「ドラゴンクエスト」シリーズみたいなロールプレイングゲームが好きでした。
なんとなく誰かに話を聞いて、ヒントをもらいながら徐々に謎を解明していく。その経験は大人になっても、仕事に活かされている。未知のものに向かっていく時のノリは、なんとなくゲームから教わったような気がしますね。
川郁子 私の家ではゲームを買ってもらえなかったので、ゲームというと、小さい頃は友達の家でちょこちょこやるくらいでした。
それが、大人になってから「どうぶつの森」シリーズにめちゃくちゃハマってしまったんです。毎日何時間も同じゲームをやり続けるっていう体験をはじめてしました(笑)。
川郁子 田舎育ちなので、東京は、自然がなくて嫌だなと思うことがあって。それが、「どうぶつの森」の世界に行くと虫の声とかが聞こえてくる。なにもしないで、ただそこにいることを楽しんで、ふらふらするんです。
コロナ禍は特に癒しを求めて、虫の声を聴きにいったりとか、波の音を聴きにいったりとか。別世界への旅行みたいな感覚でゲームの世界に行ってました。
内山堅 僕はマイコン世代なので、自分でプログラムして簡単なゲームをつくったりしていた、最初の世代かもしれないですね。当時ハマったのは、ひたすら穴を掘ってエイリアンを埋める『平安京エイリアン』っていうゲーム(笑)。
※『平安京エイリアン』は、1979年夏に東京大学の理論科学グループ(略称:TSG)が開発した固定画面アクションゲーム
東大の学生さんがつくったゲームなんですが、ゲームコミュニティーですごい流行って、最終的にはコンソール(家庭用ゲーム機)のゲームソフトとして発売されたんですよ。小学生だった僕は、そのコンソール版を買ってもらって。めちゃくちゃ集中してプレイしてました。
基本的には、同じ挙動を繰り返す系のパターンがあるゲームが好きですね。シューティングとか、打つだけのゲームとか。自らの技術を上げていくトレーニング系のやつ。

この記事どう思う?
イベント情報
勇者はUXデザインから生まれる?「人生の大切なことをゲームから学ぶ展」
- 会期
- 2024年3月15日(金) - 4月14日(日)
- 11:00 - 20:00 *最終日は18時閉館
- 会場
- GOOD DESIGN Marunouchi
- 入場料
- 無料
- ※混雑状況により入場制限を行う場合がございます
- 主催
- 公益財団法人日本デザイン振興会
- 株式会社たきコーポレーション
- 公式サイト
- https://gamekaramanabu-ten.com/
- ティザームービー
- https://www.youtube.com/watch?v=tvzq7YaWu8Y
- 公式X
- https://twitter.com/gamekaramanabu
- お問い合わせ
- 人生の大切なことをゲームから学ぶ展 企画チーム(株式会社たきコーポレーション)
- info@gamekaramanabu-ten.com
関連リンク
藤井 賢二
株式会社たきコーポレーション取締役、オンラインデザインスクール D.TOKYO TAKI Design master 講師、オンライン教育サービス Coloso. 講師。
これまで多岐にわたる商品広告やブランド広告のアートディレクション、クリエイティブディレクションに従事。
UXを基調としたデザインコンサルティングを行う。社会貢献活動「TAKI SMILE DESIGN LABO」のリーダーとして活動するほか、さまざまなプロジェクトでアートディレクターとしても活動。
慶應義塾大学大学院システムデザイン・マネジメント研究科修了。
慶應義塾大学 グローバルリサーチインスティテュート(KGRI)健康寿命延伸プロジェクト 研究員在籍。慶應義塾大学大学院システムデザイン・マネジメント研究科Education Labメンバー。

内山 堅
株式会社たきコーポレーション UXデザインカンパニーIDEAL 代表
出版社勤務を経て、2005年より当社に在籍。主にクリエイティブ施策のプロデュースおよびプロダクション管理を担当。
【代表的なプロジェクト】
・JR九州「九州新幹線」開業ロンチキャンペーン
・ベネッセコーポレーション「こどもちゃれんじ」リブランディング
・ソフトバンク IoT関連プロジェクト
・環境省「ナッジ実証事業」 コンテンツ配信2019-2021
・文化庁「文化財多言語解説整備事業」xRコンテンツ配信 2020-2021
・佐賀県「歩くライフスタイル推進事業」デザインアドバイザリー 2019-
【主な受賞歴】
・グッドデザイン賞
・Apple App Store Rewind
・コードアワード
・広告電通賞

川 郁子
株式会社たきコーポレーション UX デザインカンパニーIDEAL所属
三重県出身。一児の母。
Webチーム、社内新規事業開発チームを経て、現在はUX専門部署IDEAL(アイデアル)所属。
Web、アプリケーション、動画、グラフィック、体験型コンテンツなど、媒体にこだわらず、デザインを担当。 特に、キャラクターを使用したコンテンツを多く制作。
【主な受賞歴】
・グッドデザイン賞
・Apple App Store Rewind
・広告電通賞
・ADFEST




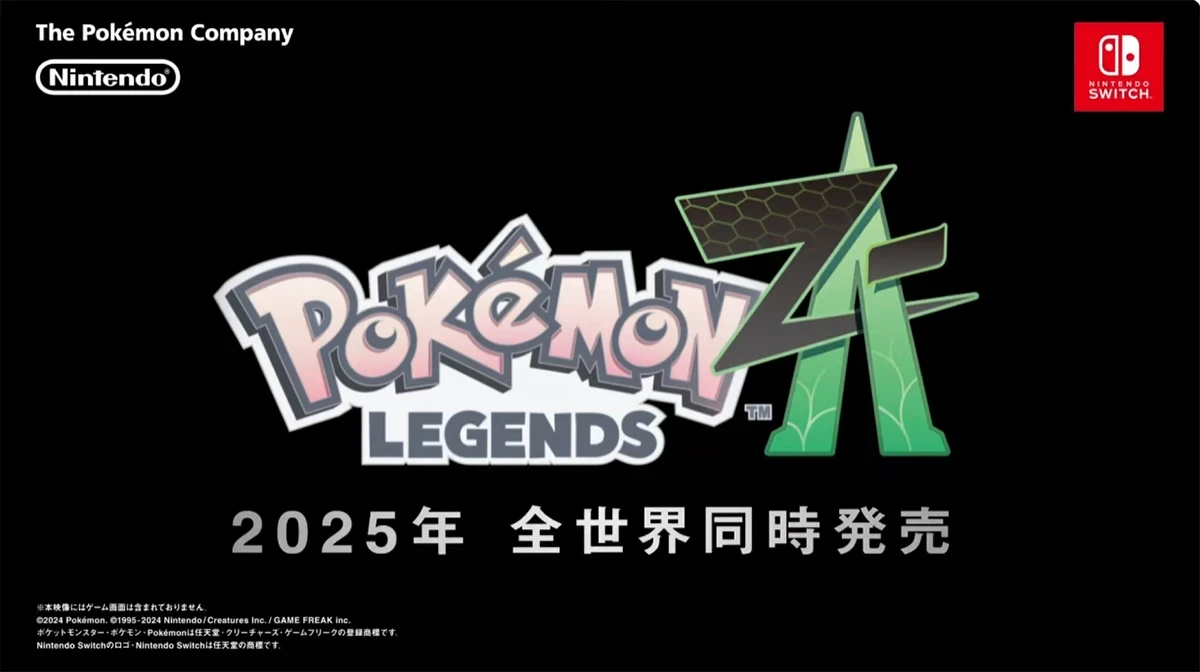

0件のコメント