若いオタクはアニメからVTuberに流れたのか? 7つのポイントから考察
2022.07.31
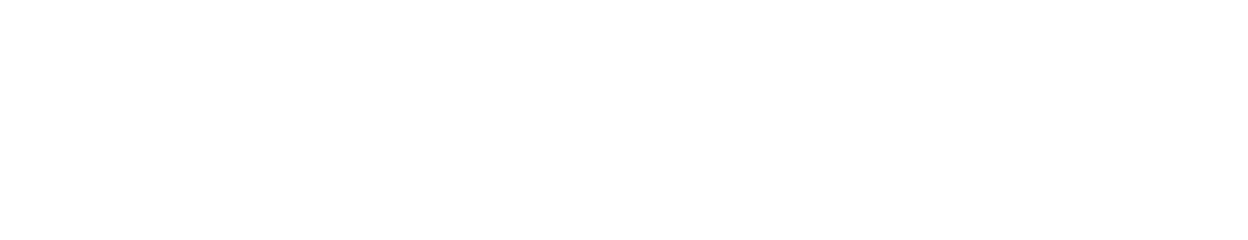
停滞した「カルチャー誌」の象徴といえる存在だった『STUDIO VOICE』は、御多分に洩れず休刊を余儀なくされていた。
新生した同誌が提示する、実践の場としての雑誌の本懐。
日本の「カルチャー誌」と呼ばれるものに対して、長いこと不信の気持ちを抱いていた。
「カルチャー誌」の定義は曖昧だが、映画や音楽からサブカルチャーまで広義の文化的な事象を扱い、主に若い世代に向けてつくられる、グラフィカルでありながらテキストも読ませる一連の雑誌、といえばひとまずの定義になるだろうか。具体的にいえば、2009年5月に休刊した『エスクァイア日本版』、同じく2009年8月に休刊した『STUDIO VOICE』に代表されるような雑誌のことである。
これらの「カルチャー誌」の休刊にはさまざまな理由があっただろうが、それらを少しも面白いと思えなくなっていた当時の私には、残念というよりは当然という気持ちのほうが強かった。ところがここ数年、休刊していたこれらの雑誌が復活している。
『エスクァイア日本版』は2016年に、〈世界有数の男性誌『Esquire(エスクァイア)』の精神を引き継ぎつつ「The Style Manual for Successful Men(成功者のためのスタイルマニュアル)」をコンセプトにしたハイエンド・ファッション誌〉と称する『エスクァイア ザ・ビッグ・ブラック・ブック』という名で、ハースト婦人画報社から年3回刊のムックとして復活した。もちろん私は、復刊後のこの雑誌を一度も手にとったことはない。

『エスクァイア・ザ・ビッグ・ブラック・ブック』日本版創刊号/書影はAmazonより
『STUDIO VOICE』は休刊後も発行元のINFASがオンライン版の更新を継続し、2012年と2013年に一度ずつ紙の特別号を出すなど、復刊の機を伺っていた。休刊から6年のブランクを経て2015年4月に年2回刊での復刊が決まったとき、復刊号は店頭でチラッと見かけたように思うが、やはり手に取ることもなかった。いわゆる「カルチャー誌」にはもう、存在する意味はないと思っていたのだ。
執筆:仲俣暁生 編集:新見直
目次
- カルチャー誌の〈かったるさ〉と対峙した新生『STUDIO VOICE』
- 〈動く〉実践の場としての雑誌
- 旧来型「カルチャー誌」の終焉
復刊後の『STUDIO VOICE』に初めて新鮮な驚きを感じたのは、2018年春に出た通巻412号を手にしたときだ。
「見ようとすれば、見えるのか?」という言葉が表紙に踊る、ドキュメンタリー/ノンフィクションを特集した号だった。映画監督フレデリック・ワイズマン(近頃、『エクス・リブリス ニューヨーク公共図書館』が日本で異例の大ヒットをした)とロバート・クレイマーの1997年の山形国際ドキュメンタリー映画祭における対談を、同映画祭のWebアーカイブから転載して巻頭に置き、ブックデザイナーの鈴木一誌へのロングインタビュー等を配したその特集は、リニューアル以前の『STUDIO VOICE』を記憶する者にとっては懐かしい書き手の名も散見されるとはいえ、何かがこの雑誌で起ころうとしているということを予感させた。
この記事の続きを読むには
あと3714文字
アカウントを作成
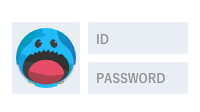
お支払い情報を入力
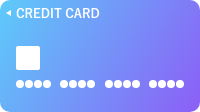
サブスク登録完了!

カルチャー誌の本懐とは?
様々なジャンルの最前線で活躍するクリエイターや識者を中心に、思想や作品、実態に迫る取材をお届け
様々な記事の中から編集部で厳選したイチオシ作品をご紹介